本記事は、小山 昇氏の著書『生成AIでわかった 経営者のための人材定着術』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

AI活用を成功させるための3つの要素
企業がAIを利用するおもな目的
「AI」とは「Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)」の略で「人工知能」を意味します。人間の代わりに考えたり、判断したり、自動的に作業したりするプログラムのことです。人間の知能を模倣し、学習・推論・問題解決などのタスク(作業)を実行する技術全般を指します。
「生成AI」は、AIの1分野であり、データから学習したパターンや関係性を活用して、テキスト、画像、動画、音声など、さまざまなコンテンツを新たに生成します(生成=新たに生み出すこと)。
経営者にとっては経営判断の支援ツールとして、社員にとっては業務効率化のツールとして、AI(生成AI)を有効活用できます。
「生成AI」も含めて、以降すべて「AI」と表記します。
企業がAIを利用するおもな目的
①単純作業から解放されて生産性が向上する
日々の繰り返し作業や定型業務を自動化すれば、単純作業から解放され、生産性が向上します。データ入力や経理処理、在庫管理などをAIに任せることで、社員は付加価値の高い業務に集中できます。
②AIに一定の業務を任せれば、省力化・無人化できる
24時間365日休むことなく作業させることができるため、作業人員の削減が可能です。AIを活用すれば、ある程度のトラブルにも自動的に対応できるなど、省力化・無人化に貢献します。
③品質の均一化が実現する
AIの導入により、技術レベルの個人差を解消できます。特定のスキルがなくても、業務に従事できる環境を整えることが可能です。また、手作業で発生しがちなミスを減らすことができるため、品質の安定化と信頼性の向上が期待できます。
④不足している労働力を補完できる
定型的な業務をAIが代替することで、労働力不足の解消に大きく貢献します。AIは、定型業務や大量のデータ処理を自動化できるため、限られた人員でより多くの業務をこなすことが可能です。
⑤顧客対応を強化できる
AIを活用したチャットボットや自動応答システムにより、24時間体制での顧客サポートが可能です。これにより、顧客満足度の向上が期待できます。
⑥市場の変化に迅速に対応した意思決定ができる
AIは、大量のデータを迅速に分析するため、顧客のニーズに合わせた戦略をいち早く立てることができます。
⑦需要の高い商品やサービスを開発できる
AIは、新商品やサービスのアイデアを生み出したり、既存の製品やサービスを改善したりするための強力なツールです。
顧客のフィードバックや市場のトレンドを分析し、需要の高い商品やサービスの開発が可能です。
ツールを導入しただけでは、AIを活用できない
2020年9月に「武蔵野経営サポート」のサイト内『武蔵野コラム』において、「AI活用と生産性向上の関係性とは【業務効率/生産性向上】」と題する記事を掲載しました。
この記事では、マイクロソフトと「IDC Asia/Pacific」が共同で実施したAIに関する調査を参考に、AI活用を成功させる3要素を紹介しています。
AI活用を成功させる3要素
①従業員のITスキルを高める
AIを活用した業務プロセスの自動化やデータ分析を行うためには、社員が新しいツールやシステムを効果的に活用できるスキルが必要です。
武蔵野は、全社員に「ITパスポート(情報処理技術者試験の一区分)」の取得を推奨するなど、スキル向上のための取り組みを進めています。
[ITスキル向上のための武蔵野の取り組み/一例]
●社内推進チームによる勉強会
社長・幹部向けZoho勉強会(Zohoは企業のIT化・業務効率の向上をサポートするクラウド型ソリューション)、ジェミニ勉強会を実施。
●全従業員による生成AI活用
2026年までに全従業員が生成AIを活用できるようになることを目指す。
●ITパスポート取得推奨
全社員のITパスポート取得を推奨し、試験合格時より毎月5,000円の手当を支給。
②インサイト(洞察)を得るためのツールを導入する
AIを効果的に活用するには、データから有益なインサイト(洞察)を引き出すツールの導入が重要です。AIをどのように活用して次のアクションにつなげるのかを分析するツールを導入しておくと、AI活用の効果が高まります。
武蔵野は、生成AI「ジェミニ」とデータ分析ツール「Looker Studio(ルッカースタジオ)」を組み合わせて活用しています。この組み合わせにより、データの可視化と分析が容易になりました。
③風通しの良い組織文化をつくる
AI導入の効果を最大化するためには、組織全体での価値観共有が必要です。従業員がAIを受け入れ、積極的に活用する組織文化をつくることで、AI導入の成功率が高まります。
部門間の連携がうまく働かなかったり、連携することに抵抗感を抱く社員がいたりすると、社内のAI化は進みません。AI活用を成功させるためには、部門を越えた情報共有や連携が重要となってきます。
2019年6月1日付で、DXの推進を強化するため、社長直轄の経営企画部(現DX事業部)を新設。各部門から人財を集結し、全社でのDX推進に取り組んでいます。また、ジェミニの活用法を各部署が発表する「ジェミニ大会」を実施するなど、部門を越えた情報共有を進めています。
AIを活用すれば、業務効率や生産性を向上させるだけでなく、労働力・職人・技術者不足にも対応できます。しかし、そのためには、AIを活用できるだけの従業員のスキルや、インフラの整備(たとえば、わが社の場合は2002年から電話回線を光回線に切り替えた)、組織文化の刷新が必要です。
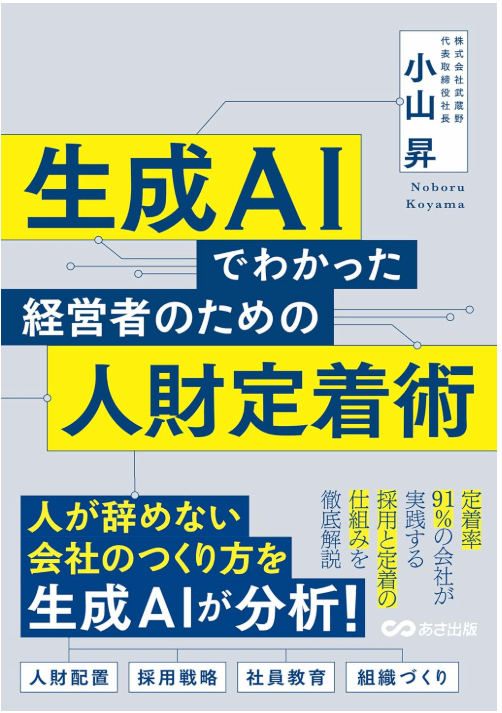
1948年、山梨生まれ。東京経済大学卒業後、1976年に日本サービスマーチャンダイザー(現・武蔵野)に入社。一時期、独立して自身の会社を経営していたが、1987年に株式会社武蔵野に復帰し、1989年より社長に就任。赤字続きだった武蔵野を増収増益、売上75億円(社長就任時の10倍)を超える優良企業に育てる。2001年から同社の経営の仕組みを紹介する「経営サポート事業」を展開。現在、700社超の会員企業をサポートし、400社が過去最高益となっているほか、全国の経営者向けに年間240回以上の講演・セミナーを開催している。1999年「電子メッセージング協議会会長賞」、2001年度「経済産業大臣賞」、2004年度、経済産業省が推進する「IT経営百選最優秀賞」をそれぞれ受賞。2000年度、2010年度には日本で初めて「日本経営品質賞」を2回受賞。2023年「DX認定制度」認定。2025年3月、健康経営への取り組みが評価され、健康経営優良法人「ホワイト500」に認定。
本書は、「勤続10年以上社員の退職者が10年で5名」「入社3年以内新卒社員の定着率91%」を実現する武蔵野の社内ナレッジをデータ化し、AIによって分析・検証。「人が辞めないマネジメント」の要諦をまとめたものである。『1%の社長しか知らない銀行とお金の話』『成長する会社の朝礼』『人が輝く経営のすごい仕組み』(あさ出版)、『会社を絶対潰さない 組織の強化書』(KADOKAWA)、『「儲かる会社」の心理的安全性』(SBクリエイティブ)、『改訂3版 仕事ができる人の心得』(CCCメディアハウス)など著書多数。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
