本記事は、永谷 顕氏の著書『非IT人材で成果が出る DX成功ルール』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

[成功ルール]
市民開発を進める上で大切なのは「とりあえずつくってみる」こと
ツール導入当初は、質より量を優先する
DXの市民開発を進める上で大切なのは、「正しくやること」ではなく、「早くやること」です。とくに業務効率化を目的としたシステム導入では、最初から100点を目指すのではなく、「まずは手を動かして試してみる」「自分の手でアプリをつくってみる」ことが重要です。
キントーンのようなノーコード、ローコードツールを使いこなすためにもっとも大事なことは、「とりあえずアプリをつくってみる」ことです。
DX化を進める上で避けるべきは「考えすぎる」ことです。最初から完璧なアプリをつくろうとすると、開発に時間がかかり、導入が遅れてしまいます。
まずは簡単なものからつくってみる。そして、運用をはじめてみる。そうすることで、実際の業務での使いにくさや改善点が明確になり、より現場に適したアプリへと改良できます。
ツールの導入当初は、「質より量」です。質を問わないことでアプリ開発に対する心理的ハードルが下がり、社員が自由に試行錯誤できる環境が生まれます。
「失敗してもいい」「まずはやってみよう」という文化が育つことで、DX化のスピードが向上します。
量を重視することで、失敗を恐れずにチャレンジできる環境が生まれます。はじめてつくったアプリがうまく機能しなくても、それは次の改善につながる大事な経験です。こうした積み重ねが、よりよいアプリの開発につながり、結果的に業務の効率化を大きく前進させます。
「つくる → 試す → 直す」のサイクルを回すことが、市民開発への近道です。
[成功ルール]
「環境整備」が習慣化されると、DXが定着しやすい
環境整備をすると、情報の整理整頓ができる
ミヨシテックでは、「環境整備」という取り組みを経営の柱に据えています。
環境整備とは、『仕事をやりやすくする「環境」を「整」えて、「備」える』ための活動のことです。整理・整頓・清潔を徹底することで、仕事の効率化と業績アップにつなげています。
環境整備には、「社内がキレイになる」だけでなく、
「社長と社員の価値観が揃う」
「やってはいけない仕事と、やらなくていい仕事が明らかになる」
「社員の感性が磨かれる」
「定位置管理が実現する」
「PDCAサイクルが回り出す」
といった、多くのメリットがあります。
環境整備の「整(整える)」には、「整理」と「整頓」、2つの意味があります。
- 「整理」=捨てる
必要なものと不必要なものを分け、徹底して捨てます。
「やらなくていい仕事」「必要のない情報」も捨てます。「やらないもの、いらないもの」を仕分けすると、「本当に必要なもの」が明らかになります。
データを分析するには、大切な情報とそうでない情報を見分ける力が必要です。
- 「整頓」=揃える
物の置き場を決め、向きを揃え、いつでも、誰でも使える状態を保ちます。名前、数字(数量)、色、記号などで管理して、置き場や置き方を明示します。
情報の管理の方法も決められています。情報の置き場所を決めておかないと(どこに、どの情報があるのかが分からないと)、情報が活かせないからです。
社員一人ひとりが、形を整えて、決められたことを、決められた場所にきちんと整頓していく。社員全員が同じ方向に向かって行動することで価値観が揃い、会社として団結力が高くなります。
環境整備の実施状況を定期的にチェックする
ミヨシテックでは、4週に一度、全部署を対象に「環境整備点検」を行っています。
「環境整備点検シート」には、項目ごとに「評価」の欄が設けられていて、「○」か「×」かを判断し、チェックをします。
「×」がつけられた項目があると、社員は「どうして○がもらえなかったのか」を検証し、「どうすれば○がもらえるのか」を考え、改善に取り組みます。そうしなければ、来月もまた「×」がついてしまうからです。
当社の社員は、
- 「環境整備を実行する」
↓
「4週に一度、チェックを受ける」
↓
「できていなかったことを改善する」
というサイクルを定期的に回しています。
すなわち、日常的にPDCAサイクルを回しているわけです。
◎PDCAサイクル
Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのプロセスを循環させて、業務改善を進める考え方。
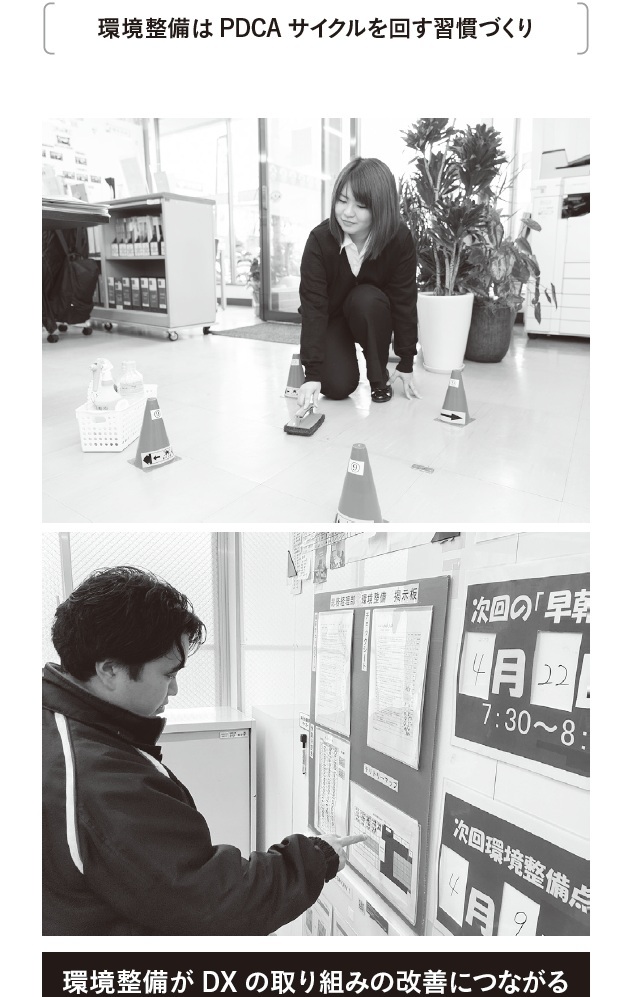
わが社でキントーンやRPAの改善が進むのは、環境整備によって、
「やったことをやったままにするのではなく、チェックを受けて評価を決める。そして、さらに改善を加えて次につなげる」という意識が社員に根づいているからです。
このようにしてPDCAサイクルを回す習慣をつけることで、DXの取り組みが改善され、より高いレベルの成果を得ることができるようになります。
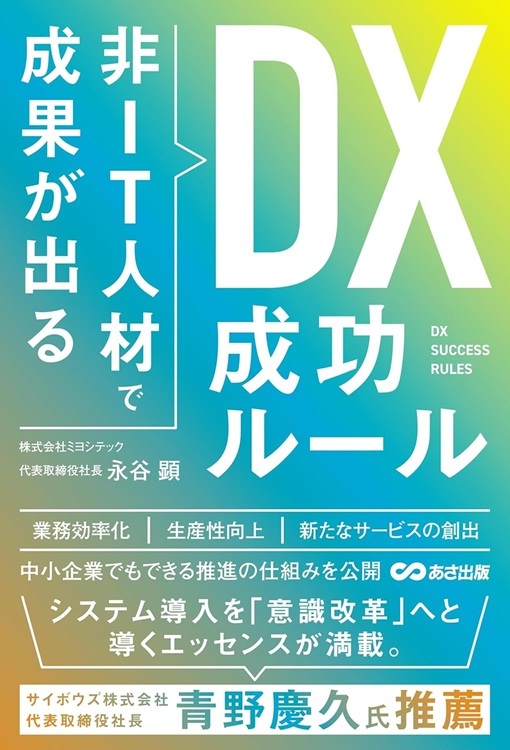
1973年、兵庫県西宮市出身。1996年、神戸商船大学(現・神戸大学海洋政策科学部)卒業。1998年、神戸商船大学大学院修了。同年、株式会社ミヨシテック入社。
2008年より現職。
「決めた目標に脇目もふらず突き進む」「必要であれば、既存のシステムを容赦なく壊す」ことから、「ブルドーザー社長」と呼ばれる。島根県松江市観光大使。
株式会社ミヨシテックは非IT人材のみでDX化を推進し、2022年7月「DX 認定」、「kintone AWARD 2022」ファイナリスト、「DXセレクション2024」優良事例企業に選定される。同社のDX 化の取り組みを学ぼうと、国内外から視察が絶えない。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
