本記事は、野呂 エイシロウ氏の著書『「話がつまらない」をなくす技術』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

- なぜか好かれる人は、結論を語らない
- 煙たがられる人は、必要もないのに結論づける
煙たがられる人が陥りがちな根本的な勘違いがあります。会話には必ず結論がいる、と思っていること。そして、そこに行きつけないのをとても嫌がるのです。
でも、僕は、結論のない話など当たり前だと考えていますし、それどころか相手が望んでいないのであれば、結論を語らないようにしています。それでも一向に構わないのです。
会話の相手が、深刻な悩みを抱えていたとします。仕事関係でも、男女関係でもよくあるシチュエーションです。僕もよく相談を受けます。
こんなとき、相談している側は、必ずしも相手に結論を求めているわけではありません。若い頃と違い、今の僕はそのことをよくわかっているので、「相談に乗ってよ」と言われれば、ただ相槌を打ち、相手の話した内容をオウム返ししながら、基本的には黙って聞いているだけです。
そして相手から「どうしたらいいと思いますか?」と聞かれて初めて、自分の考えや結論を言うことにしています。
話を聞いた結果、たとえ僕が100%自信がある解決策を思いついたとしても、相手から請われない限り絶対に語りません。
相手が何を望んでいるか考えましたか?
なぜこんなことを大真面目に守っているのかというと、会話の相手が何を求めているかは、あくまで相手のなかにしか存在しないからです。
もしかしたら、彼(彼女)の頭のなかにはすでに結論めいたものがあり、僕にはただそれに対する賛同を求めているだけなのかもしれません。
あるいは、結論が出ない、出せないことと知っていながら、ただ真剣に耳を傾けてもらう相手が欲しくて話を振ってきただけなのかもしれません。
つまり傾聴してもらえればそれで十分で、「ああ、話したらスッキリしました。明日からまた頑張ります!」となるかもしれないのです。
相手がその会話を通じて何を望んでいるかを正確につかむことこそが、僕が考える会話の本質です。
それが「相談に乗ることそのもの」であるなら、結論などまったく邪魔な、不要な要素です。たとえ万能の解決策であったとしても、のみ込むべきだと思います。
コンサルタントとしての僕のスタンスも、基本的には変わりません。クライアントから結論を求められれば、自分の考え方をお伝えします。反対意見やネガティブな要素を述べてほしいと頼まれれば、やはり自分の考えと合致していようといまいと、考えられるリスクや問題点を指摘するでしょう。
しかし、いくら社長が迷い悩んでいようと、僕が望まれてもいないのに結論を言うのは絶対にやってはいけないことです。それは大きなお世話ですし、そもそも僕はコンサルタントにすぎないのであって、その会社が失敗しても責任の取りようがないからです。
コンサルタントとしてやるべきことは、結論を語ることではなく、社長やクライアントが選びたいほうを後押しすることです。それが僕の仕事です。
その結果が失敗に終わったとしても、本物の経営者であれば、決して僕を責めることはありません。
ワシづかみポイント
会話には、必ずしも結論は必要ない
何を望んでいるかは相手の心のなかにある
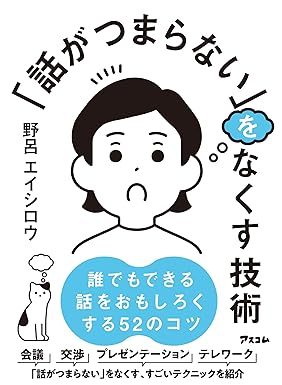
学生時代に「現役の学生」を武器に電機メーカー、広告代理店との会議に参加。学生向け家電企画の立案、宣伝、PRに携わる。その後、『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』で放送作家デビュー。『ザ!鉄腕!DASH!!』『奇跡体験!アンビリバボー』『ズームイン!!SUPER』などに携わり、テレビ局独特の“笑い”にあふれた会議で、話し方や雑談力、提案力を鍛えられる。放送作家としての「番組をおもしろくするネタづくりのノウハウ」をいかし、30歳の時から“戦略的PRコンサルタント"としての仕事をスタート。
企業の商品やサービスを一般の人に「おもしろそう!」「欲しい!」と思ってもらうような独自の戦略立案を行っている。
クライアントには、「SoftBank」「ライフネット生命」「GROUPON」「Expedia」「ギルト・グループ」「hulu」「Folli Follie」「ビズリーチ」「ルクサ」をはじめ、金融機関、自動車会社、アパレルブランド、飲食店など、国内外の企業250社以上があり、“かげの仕掛人”として活躍している。笑える講演も人気を呼んでいるが、引き受けるのは月に1度まで。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
