2016年の電力小売り自由化以前、ほとんどの地域では電力会社が独占的に営業していた。このような電力市場の土壌を作り出した男が、松永安左エ門である。電力市場の熾烈な争いの中で松永が成し遂げた功績をたどる(文中敬称略)。
(本記事は、小川裕夫氏の著書『東京王』=ぶんか社、2017/10/28=の中から一部を抜粋・編集しています)
【関連記事 『東京王』より】
・ 東京の知性を育んだ初代総理の教育熱――伊藤博文
・ 一大商業都市目指し奮闘した資本主義の父――渋沢栄一
・ 東京駅を建てた男の栄光と未踏の夢――辰野金吾
・ 群を抜く政策立案能力、東京発の「メイド・イン・ジャパン」−−大久保利通
・ GHQをも退けた「電力の鬼」実業家−−松永安左エ門
電力自由化スタート
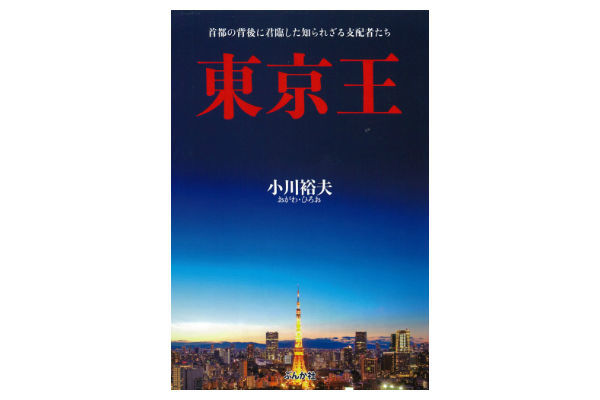
平成28(2016)年4月1日、家庭向けの電力小売りが自由化された。それまで日本の電力は、地域ごとに電力会社が独占的に営業していた。東京圏なら東京電力、大阪圏なら関西電力といった具合に消費者である私たちは電気の購入先を選ぶことはできなかった。地域ごとに決められた電力会社と契約する仕組みは、、電力会社に半強制的に電気を買わされていたということでもあり、そうした地域独占市場で競争原理は働かない。電力の完全自由化は電力会社の地域の枠を取り外したのみならず、他業種からの参入も促した。今後、電気料金の値下げやサービスの向上が期待されている。
電力業界に変革を迫った電力自由化という波は、地域独占という電力会社の体制を大きく刷新するきっかけになるとも目されている。しかし、ここに至るまで電力会社がなぜ地域独占を維持できたのか? といったことも疑問として抱かざるを得ない。そもそも電力が地域独占化したのは、昭和26(1951)年の9電力会社設立まで遡らなければならない。しかし、日本の電力会社の歴史はもっと深い。電力史をひも解くと、電力は日本の近代化に欠かせないツールであったことが窺える。
深刻な原料不足
日本の電力史は鎖国が解かれ、世間が文明開化を謳歌するころより幕を開ける。明治11
(1878)年に工部大学校に日本初のアーク灯が点灯したことから電気の歴史が始まった。明治 19(1886)年には、東京電力の前身となる東京電燈が発足。翌年には、名古屋・神戸・京都・大阪といった都市部でも相次いで電力会社が設立されていった。電力会社として一足先に設立された東京電燈は、家庭に電力を供給するため発電所を東京・日本橋に建設した。以降、東京電燈は急速に発電所を建設していく。それほど電力は世間の人々から期待されるエネルギーだった。近代化を急いでいた政府としても、電気で工業化を進め、それで生産力が向上すれば殖産興業・富国強兵が達成できると踏んだ。政府は電気に期待した。
しかし、日本には石炭や石油といった火力発電に必要な化石燃料が乏しかった。原料がなければ、大量の電力を生み出す火力発電所を建設しても発電所を稼働させることはできない。それが、電力に携わる関係者の衆目一致した悩みだった。
電力関係者が悩む中、福澤諭吉は違う見解を持っていた。日本の国土は山々に囲まれ、険しい山や谷がある。それらを利用すれば各地に水力発電所をつくることができる。水力発電所をたくさん建設すれば、電気は大量に生産できる。石炭に頼らずとも、電力を大量に生み出し、日本は最先端の近代国家として歩むことができる—。
福澤の考えを愚直に実行したのは、娘婿の福澤桃介だった。桃介はアメリカで鉄道員を経験した。帰国後、その経験を買われて北海道炭礦鉄道に勤務する。そこで石炭販売のノウハウを会得する。桃介は体調を崩して北海道炭礦鉄道を退職するが、その後に会社を設立し、慶応義塾の後輩・松永安左エ門をヘッドハンティングした。
松永は福澤諭吉の思想に共鳴し、長崎県壱岐島から上京。慶應義塾の門を叩いた。めでたく入塾したものの、松永は学問が自分には不向きであることを悟った。それを福澤に相談すると、実業界に転身することを勧められて、日本銀行に入行する。
用地買収の鍵は「酒」
日本銀行に入行した松永だったが、札を数える毎日の業務に嫌気が差していた。そんなところに、桃介から「一緒に会社をやらないか?」という誘いを受ける。桃介が松永をヘッドハンティングした理由は、電力事業に参入するためだった。
当時、東京や京都などの都市部では、電気は新時代の文明だと理解されていた。しかし、都心部では小さな火力発電所を建設することが精一杯。福澤諭吉が指摘した険しい山や谷を利用して水力発電所を建設するには、地方の農山村に出向き広大な土地を買収しなければならなかった。しかし、農山村は農業が主産業であり、土地は手放すことができない財産だった。さらに先祖代々受け継いできた土地だ。そう簡単には手放せない。桃介は土地を譲ってくれるように、山間地の農家を訪ねて説得を重ねた。いくら大金を積まれたからといって、東京から「土地を売ってくれ」と訪ねてきた見知らぬ若造に簡単に「はいそうですか」とふたつ返事をする人間はいない。桃介は何度も土地の所有者を訪問し、膝を交えて話し合った。重ねて交渉するうちに、桃介は相手に最も心を開いてもらうには酒を交わすことが有効だと悟る。しかし、桃介は病気がちで、毎晩のように酒を飲むことができない。そこで桃介は酒に強い松永に土地の交渉役を任せた。酒の強い松永は桃介に代わり、売買交渉をまとめていく。こうして松永は桃介の右腕として才覚を表していく。
巻き起こる電力戦
福澤・松永の転機は、日本屈指の採炭の地・九州に事業を興したときに訪れた。それまで福澤・松永の石炭販売は、軌道に乗っているとは言い難かった。しかし、福澤と松永は明治42 (1909)年に福岡を拠点とする福博電気軌道を設立。福博電気軌道は、現在で言うところの路面電車を運行する鉄道会社だ。石炭を販売する傍ら、売れ残った石炭を発電事業に回し、発電事業で生み出した電気の余剰分を鉄道の動力源に回す。まさに、一粒で3度おいしい商売に早変わりした。福博電気軌道の社長には桃介が就任したが、桃介は翌年に買収する東邦電力や奈良を中心に水力発電事業を展開していた関西水力発電の経営に忙しく、実質的に福博電気軌道の指揮をとったのは松永だった。
石炭販売・電力事業・鉄道経営の3本柱で九州に確固たる勢力を築いた松永は、福博電気軌道を軸に九州各地の電力会社を合併しながら事業を九州一円に広げていく。他方で、九州の電力事業を松永に一任していた桃介は、名古屋を拠点に電力事業の拡大に成功していた。桃介の経営手腕は凄まじく、名古屋で展開していた電力事業は関西方面にも進出する。大正11(1922)年には自身が九州で経営していた電力会社と統合し、新たに東邦電力を発足させた。盟友・松永も東邦電力の副社長に就任する。新たに発足した巨大電力会社・東邦電力の本社は東京に置かれた。東邦は東京に電力を供給していない。営業区域外に本社を置くという行動は明らかに不可解だが、これは東邦電力が東京進出することを見据えての準備だった。
当時、電力会社は地域独占ではなく、各社はそれぞれが営業活動で客を奪い合っていた。電気が普及してくる大正期になると電力会社の営業合戦は熾烈を極め、その激しさから電力戦と呼ばれるまでになる。東邦が東京に攻め込もとしたとき、東京を地盤にしていた電力会社・日本電力や東京電燈が迎え撃った。日本電力は自分たちの地盤である東京を死守するだけではなく、逆に東邦の地盤である名古屋に殴り込みをかけて反撃もしている。
こうした争いのほかにも中小電力会社が乱立し、各地域で小競り合いが起きていた。松永は電力会社が私利私欲で戦えば電力不足が必ず起こり、それは国民生活を不便にする。国民生活が不便になることは、日本のマイナスになると考えた。そこで松永は、電力会社は発電事業に専念し、送電網を整備・保有・管理して供給だけを担当する大日本送電株式会社の設立を各地の電力会社に提案する。松永のアイデアは、今般議論されている電力の発送分離に近いものだった。いたずらに消耗戦を繰り広げたくなかった電力会社の社長たちも、一度は松永の提案に賛成した。しかし、いざ統合に動き出すと利害調整で計画は難航。結局、話はまとまらずに頓挫した。
東京決戦での敗北
大日本送電株式会社の計画が白紙に戻ると、再び各地で電力戦が繰り広げられる。電力の競争は国家のため、国民のためにならないとの主張をしていた松永にしても、東邦電力の経営者なのだから、自社の利益のためには戦わざるを得ない。
東邦が東京進出するにあたり、もっとも手強い敵は東京電燈(東電)だった。松永は東邦の東京進出に際して、まずは静岡県や神奈川県の小電力会社を買収。さらに東京電力(東力)を設立して、東京での電力戦を勝ち抜こうとした。東電と東力の電力戦の火ぶたが切って落とされると、松永は大口契約先である鉄道省と東京市電に営業をかけ、あっさり契約を結ぶことに成功する。しかし東電も負けじと各家庭に契約攻勢をかけて対抗した。
東電と東力の電力戦は激しさを増し、世間の話題をさらうことにもなった。松永が危惧したように、激しい電力戦は国民の利益にならない。事態を収拾するべく、三井財閥の総帥・池田成彬が仲介役に立って、停戦勧告がなされた。池田は戦前期に総理大臣にも推薦されるほどの財界の重鎮で、その池田からの提案ということもあって、東電と東力は昭和3(1928)年に合併する。合併によって東電と東力の電力戦は終結したが、合併後の新会社は東京電燈となった。実質的に、電力戦は松永の敗北だった。
東力が東電に合併されたことで東京圏の出城を失った松永だったが、東邦電力は中部・九州で確固たる地盤を築き、こちらの経営は順調だった。ところが、電力業界に思わぬ暗雲が立ち込める。電力は民間企業に任せるのではなく、政府が統括すべきとの意見が軍部を中心に広がってきたのだ。
松永は電力の国家管理に反対し、講演でも政府批判を公然と口にした。そのため、政府から危険人物としてマークされることになる。
昭和13(1938)年、政府は電力管理法を施行。電力事業は電気庁の下に一元管理された。こうして国家の電力統制が始まり、民間企業による電力事業は姿を消した。
最強企業・東京電力誕生

松永の前半生は電気とともにあった。電力業界から引退させられていた松永が、再び表舞台に登場するのは敗戦後だった。敗戦後、日本に乗り込んできたGHQは民主化を進めるため、さまざまな制度改革を断行した。国営事業だった大蔵省所管の塩とタバコの専売を日本たばこ産業に、運輸省の鉄道事業を公共事業体の国鉄へと移管。そのほか、過度経済集中排除法による財閥の解体、小作農を廃止する農地開放などに着手したが、同時に電力事業の再編成も進めた。電力管理法で実質的に国営となった電力事業は、GHQによってあるべき電力体制の姿が検討される。実業界から引退していた松永は、審議会委員長として引っ張り出された。
日本政府内では電力再編問題はさまざまな案が出された。政府内では電力は戦前期のように国家管理することが望ましいとの意見が強かったが、これが松永の意見と対立。また、GHQと松永の意見も合わず、電力問題は暗礁に乗り上げかけたが、松永案はマッカーサーの意見に屈せずに自分の主張を押し通した。占領期、白洲次郎はGHQの最高責任者・マッカーサーと互角に渡り合った人物として有名になったが、松永も電力再編問題でGHQに一歩も譲らなかった。こうして、松永が主張する9電力体制が採用されることになり、昭和26(1951)年に最強企業と謳われた東京電力が誕生した。
9電力体制が発足後も、東京電力と中部電力、北陸電力と関西電力といった具合に電源開発や営業区域などによる縄張り争いが起こり、松永はそのたびに調整を続けた。さらに、戦災復興から脱却してきた日本経済は高度経済成長を迎え、戦前期には弱かった重工業が伸びてくる。家庭の電化も進み、電力不足が顕著になる。特に、首都圏の電力不足は深刻だった。
福澤諭吉の薫陶を受けていた松永は、日本の電力は水主火従であるべしと考え、関東や南東北の山々に水力発電所を建設するべく、駆け回った。
小川裕夫(おがわ ひろお)
フリーランスライター・カメラマン。1977年、静岡市生まれ。行政誌編集者などを経てフリーランスに。2009年には、これまで内閣記者会にしか門戸が開かれていなかった総理大臣官邸で開催される内閣総理大臣会見に、史上初のフリーランスカメラマンとして出席。主に総務省・東京都・旧内務省・旧鉄道省が所管する分野を取材・執筆。