(本記事は、近藤駿介の著書『202X 金融資産消滅』ベストセラーズの中から一部を抜粋・編集しています)
「世界最大の機関投資家」が負っている宿命

2014年10月31日にGPIFが基本ポートフォリオを「リスク選好型」に変更してからも、GPIFは「外的追い風」もあって順調に収益を確保してきました。基本ポートフォリオの変更がこれまで結果オーライになってきたこともあり、GPIFが「世界最大の機関投資家」であるがゆえに一般の投資家とは異なる運用上の制約や宿命を抱えていることについては話題に上ることもありませんでした。
しかし、基本ポートフォリオの変更が今のところ結果オーライであるからといって、GPIFが「世界最大の機関投資家」であるがゆえに背負う宿命が変わることはありません。では、「世界最大の機関投資家」であるGPIFが背負っている運用上の宿命とは何でしょうか。
それは「評価益を実現益に変えることはできない」ということです。GPIFは、2001年に公的年金資金の市場運用が始まって以来2019年9月までの18年間に約67・9兆円の収益を生み、年率3・02%の収益率を得ていると公表しています。しかし、この67・9兆円という収益は、当たり前のことですが一般の投資信託などと同じように保有する株式や債券を時価評価した場合のものです。つまり、実際に市場で売却して確定した利益ではなく、評価損益を含んだ収益額です。
2014年10月31日に日銀が打ち出した「異次元金融緩和」の拡大に合わせるようにGPIFはその基本ポートフォリオを「リスク選好型」に変更することで国内株式の買付余力を作りました。この基本ポートフォリオ変更に基づいてGPIFは国内株式の持ち高を2014年9月末の23兆8635億円から2015年3月末には31兆6704億円まで約7・8兆円増やしたのです。
GPIFが半年間で国内株式の持ち高を約7・8兆円増やしたことで株価も大幅に上昇することになりました。GPIFの国内株式の運用においてベンチマークとなっている「TOPIX配当込み指数」は、基本ポートフォリオの変更を決めた10月末時点で1822・08ポイントでしたが、2015年3月末には2128・30ポイントまで306・22ポイント、16・8%もの上昇を記録することになりました。
こうした市場全体の上昇によって2014年9月末時点で23兆8635億円の評価であった国内株式の価値も27兆8725億円程度まで拡大したと考えられますので、こうした相場上昇の影響を考慮すれば、2014年10月31日に基本ポートフォリオの変更を実施したGPIFは、2015年3月末までに約3・8兆円の国内株式を買増したことが想像されます。
3・8兆とも推計されるGPIFによる大規模な買付が日本株の大幅上昇の原動力になったことは論ずるまでもないことです。しかも、株価上昇をもたらしたのは多額の買付規模だけではありません。「世界最大の機関投資家」が国内株式への投資を増やすというアナウンスメント効果が、実際の大規模な買付額と同じくらい大きなインパクトを及ぼしたことは想像に難くありません。
2014年9月末時点で130兆8846億円もの運用資産を持っていた「世界最大の機関投資家」と称されるGPIFが基本ポートフォリオを変更し、国内株式の資産構成割合を12%から25%へと倍に引き上げるならば、単純計算で約17兆円もの投資資金が日本株市場に流れ込んでくることになると誰もが考えることでしょう。このニュースを耳にした投資家は、ほぼ全員がGPIFに先んじて日本株に投資しようと考えるはずです。何しろ自分よりもずっと大規模な資金を持つGPIFが日本株に大量の資金を振り向けることが確定しているのですから、それはほとんど損をする可能性がない投資だからです。
時としてこうしたアナウンスメント効果が実際の買付効果を上回る場合すらあります。それが「世界最大の機関投資家」であるGPIFに関するものだとなればなおさらです。安倍政権はアベノミクスの効果を強く印象付けるために、「世界最大の機関投資家」であるGPIFによる国内株式の組入比率引き上げ決定というアナウンスメント効果を最大限に利用して日本株の上昇を誘った格好になりました。
しかし、「世界最大の機関投資家」によるアナウンスメント効果は、組入比率を引き上げる局面だけで発揮されるものではありません。逆もまた真なりで、「世界最大の機関投資家」が市場で売手に転じることになった際の逆アナウンスメント効果も世界最大級のものになることを忘れてはならないのです。
そして、金融市場の恐ろしい鉄則の一つは、「買う時の流動性はあるが、売るときの流動性はない」ということです。つまり、「世界最大の機関投資家」の買い情報に伴うアナウンスメント効果よりも、「世界最大の機関投資家」の売り情報によるアナウンスメント効果の方が、市場への影響度が大きくなるのが普通なのです。
GPIFは2001年から2019年3月までの18年間に65・8兆円の収益を上げてきました。そして、この65・8兆円にも及ぶ大きな収益の42・2%に相当する30兆3793億円は基本ポートフォリオ変更を行った2014年度以降の5年間で稼ぎ出したものです。
さらに、この5年間に獲得した30兆3793億円の収益のうち、国内株式で37・6%の11兆4100億円の収益を上げており、それは41・2%、12兆5201億円の収益を上げた外国株式に次ぐ規模になっています。つまり、2014年度以降の5年間で稼ぎ出した収益額の78・8%、8割近くは国内株式と外国株式という内外株式で得たものになっているのです。
2014年10月31日に行った基本ポートフォリオ変更は、GPIFの運用収益拡大に大きな貢献をしてきました。しかし、基本ポートフォリオ変更によって稼いだとされている運用収益も、今後は絵に描いた餅になる可能性を秘めていることには注意が必要なのです。
仮にGPIFが年金給付に必要な財源を確保する目的でこの多額の収益を確定しようとしたらどうなるでしょうか。収益を確定するためには市場で保有資産を売却し、現金に変える必要があるのです。
2019年6月末時点で160兆6687億円という大規模な運用資産を誇るGPIFは国内株式を37兆7642億円保有しています。2014年度以降の5年間で国内株式によって11兆4100億円の収益を上げていることからすると、仮にその1割、1兆1410億円の収益を確定しようとしたら、単純にいうと保有している国内株式の1割を売却すればいい計算になります。国内株式の保有額は37兆7642億円ですから、1兆1410億円の利益を確定するためには、単純計算で3兆7764億円を市場で売却する必要があることになるのです。
前述したように、2014年10月31日に基本ポートフォリオを変更したGPIFは、その後2015年3月末までの5か月間の間に推計で3兆8000億円程度の国内株式を買い付けています。つまり、この5年間に国内株式への投資で獲得した11兆4100億円の収益の1割を実現益に変えるためには、単純計算上基本ポートフォリオを変更した際に新たに買い付けた金額約3兆8000億円とほぼ同規模の国内株式を売却する必要があるということになります。
2014年10月31日に基本ポートフォリオを変更してから2015年3月末までの5か月間にGPIFが推計3兆8000億円強の国内株式を追加購入したことで、TOPIX配当込み指数は1822・08ポイントから2128・30ポイントまで16・8%上昇しました。「買う時の流動性はあるが、売るときの流動性はない」という市場の鉄則に則れば、たとえ買い付け金額と売却金額がほぼ同額だとしても、市場価格への影響は売却時の方が大きなものになる可能性が高いのです。しかも売り手が「世界最大の機関投資家」と称されるGPIFであればそのアナウンス効果も加わりますからなおさらです。
単純にいえば、GPIFが「世界最大の機関投資家」だということは、GPIFの売りを単独で吸収できる投資家がこの世に存在しないということです。「世界最大の機関投資家」であるGPIFが基本ポートフォリオを変更した際には、日本株への投資配分を17兆円増やすということを耳にした投資家が、より高い価格でGPIFに売りつけることができると確信しGPIFに先回りして日本株を購入したことで、相場は大きく上昇しました。
では、こうした投資家が、GPIFが日本株を売却するという方針に接した際にはどのような投資行動をとるでしょうか。
常識的に考えられることは、GPIFに先んじて日本株をGPIFよりも高い価格で売却しようとすることです。こうした投資家の行動によって、GPIFは希望する価格よりも低い価格で売却することを迫られることになるのです。
また、日本株への投資配分を増やす意図を持っている投資家がいたとしても、資金規模では「世界最大の機関投資家」であるGPIFに太刀打ちできませんから、GPIFの売り物に真正面から買い向かっていくことはあり得ない話です。つまり、たとえ日本株の投資配分を増やそうとする投資家がいたとしても、彼らはGPIFの資産を評価している時価で買ってくれる投資家ではないのです。
2014年10月31日にGPIFが基本ポートフォリオを変更してから5か月間で推計3・8兆円の国内株式を購入したことでTOPIX配当込み指数が16・8%の大幅上昇を記録しましたが、反対にGPIFがほぼ同額の国内株式を売却することになったらTOPIX配当込み指数の下落率は上昇時の16・8%を大きく上回る可能性が高いと考えなければなりません。それが市場のシビアな現実なのです。
この原稿を書いている2019年12月時点で、日経平均株価は米中貿易交渉の第一弾合意などを好感して1年2か月ぶりに2万4000円台に乗せてきました。仮にGPIFがこの株価水準から評価益の1割を実現益に変える目的で3・8兆円の国内株式の売却を始め、日経平均株価とTOPIX配当込み指数がともに16・8%下落すると仮定した場合、日経平均株価は2万円前後まで4000円前後下落する計算になります。
これに、売却時の方が買付時よりも市場インパクトが大きくなる可能性が高いことを考慮すれば、GPIFが基本ポートフォリオの変更を決めた2014年10月31日の1万6413円前後まで下落してしまうケースもあり得ない話ではないといえそうです。つまり、「世界最大の機関投資家」であるGPIFが、この5年間で積み上げた収益額の1割を実現益に変えようとするだけで、株価が元の水準に逆戻りしたとしても決して不思議なことではない状況なのです。
株価が元に戻るだけなら別に大したことではないと感じる人も多いかもしれません。しかし、株価水準が、GPIFが基本ポートフォリオ変更を決めた2014年10月31日の水準に戻るということは、2014年度以降の5年間に上げてきた11兆4100億円の収益の1割に相当する1兆1410億円を実現益として確保することと引き換えに、残りの10兆2690億円の収益のほとんどを失うということなのです。もちろん、2014年10月31日の水準に戻ることが確定している訳ではありませんが、収益の一部を実現益に変える度に、残りの評価益の多くが失われていく構図は変わらないのです。下落相場の中で資産の現金化を図ることの恐ろしさは、日本人は1990年のバブル崩壊局面でも痛感しているのです。
GPIFが基本ポートフォリオを変更した2014年10月直前の9月末時点でGPIFの国内株式への投資比率は18・23%、投資金額は23兆8635億円でした。それに対して2019年6月末時点での国内株式への投資比率は23・5%、投資金額は37兆7642億円と投資比率で5・27%、投資金額にして13兆9007億円も多くなっています。実現益を確保するために国内株式の1割、3兆7764億円を売却したとしても投資金額は約34兆円と2014年9月末時点よりも10兆円以上も多く、国内株式の構成比も24%前後と6%弱も高い状況であり、株価の変動の影響を受けやすくなっています。これは換言すれば評価益を実現益に変え難い状況になっているということでもあります。「世界最大の機関投資家」であるGPIFは、評価益を実現益に変えることができないという宿命を背負っている。
これが、政府やGPIFの運用戦略を決めている有識者たちや、日本の投資家が見逃している「世界最大の機関投資家」が抱える宿命であり、マーケットの厳しい現実なのです。
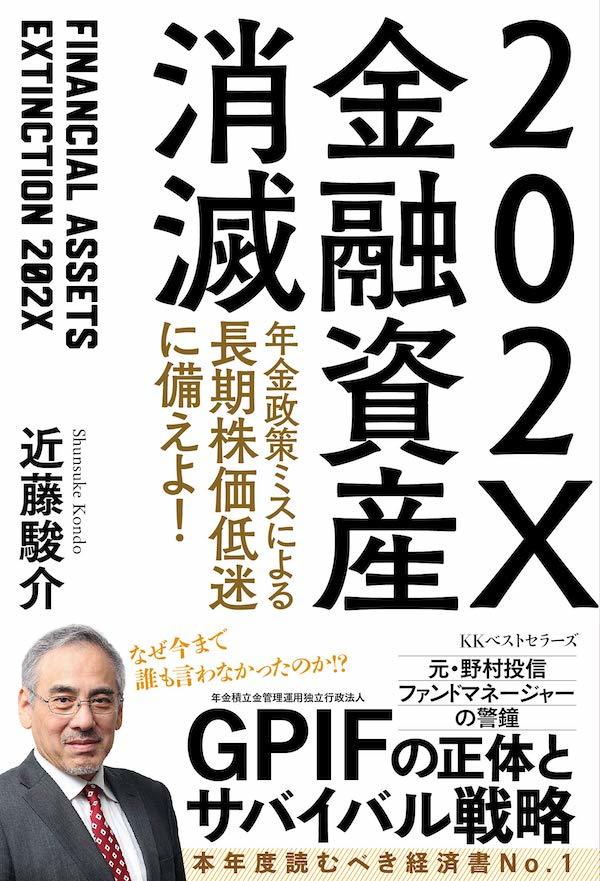
金融・経済・資産運用評論家。1957年東京生まれ。早稲田大学理工学部土木工学科卒業。大手総合建設会社勤務を経て、31歳で野村投信(現・野村アセットマネジメント)に入社。ファンドマネージャーとして25年以上にわたり、株式、債券、デリバティブ、ベンチャー投資、不動産関連投資など、さまざまな運用を経験。90年代中頃には合計約8000億円と日本最大規模の資金を運用していた。現在は、評論家、コンサルタントとして活動し、テレビ、webメディア、雑誌などにコメント提供や記事執筆をしている。著書に『1989年12月29日、日経平均3万8915円』(河出書房新社、2018年)などがある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
