(本記事は、近藤駿介の著書『202X 金融資産消滅』ベストセラーズの中から一部を抜粋・編集しています)
効果が剥げ落ち始めた「異次元の金融緩和」

日本経済が直面していた円高・株安という危機を短期間で救ったという点において「異次元金融緩和」は大成功でした。しかし、「異次元金融緩和」が実施されてから6年半以上が経過した2019年12月時点でも、「消費者物価の前年比上昇率2%の物価安定の目標を、2年程度の期間を念頭に置いて、できるだけ早期に実現する」という本来の目標は達成できる目途が立っていない状況です。
価格変動の大きい生鮮食料品を除いた消費者物価コア(以下「消費者物価コア」)の前年同月比上昇率を見てみると、消費税が5%から8%に引き上げられた2014年に一時的に「2%の物価安定目標」を上回って推移したことがありましたが、消費増税の影響を除くとアベノミクスの目標である「2%の物価安定目標」を上回ったことはありません。
2019年10月から消費税は8%から10%へと2%引き上げられました。この2%の消費増税によって消費者物価は0.77%程度押し上げられるとみられていましたが、同時に物価押下げ効果が0.57%程度あると見込まれている幼児教育・保育無償化が実施されたこともあり、2019年11月時点の消費者物価コアの前年同月比上昇率は0.5%に留まっています。「異次元金融緩和」は、短期間で円安・株高という目に見える派手な成果を生むことには成功しましたが、本来の目的である「2%の物価安定目標」の達成に近付けていない状況が続いているのです。
こうした状況は、本来なら安倍総理や黒田日銀総裁にとって好ましいことではありません。特に黒田日銀総裁は2013年4月に「異次元金融緩和」を導入した際に「2年程度の期間で2%の物価安定目標」を達成すると大見得を切り、自ら「2%の物価安定目標」を達成するまでの期限を2015年4月に設定していましたから、焦りを感じていたに違いありません。
円安・株高だけが先行し、自らが設定した期限までに「2%の物価安定目標」を達成できなければ、「異次元の金融緩和」という政策自体に疑問の目が向けられかねません。それは回りまわって「デフレからの脱却」の象徴でもあった株高にも影響を及ぼす危険性を秘めているものです。
そうした中、2014年4月には消費税が5%から8%に引き上げられたことによって個人消費が予想以上に低迷してきました。
消費増税という特殊要因に伴う駆け込み需要や便乗値上げなどによって、消費者物価コアは2014年4月の消費増税実施時には3%台に乗せ、2014年5月には3.4%に達し、表面上は「2%の物価安定目標」を達成した形になりました。しかし、専門家の間では3%の消費増税によって消費者物価コアが概ね1.5%嵩上げされるというのがコンセンサスでしたので、3.4%という消費者物価コアの上昇も消費税増税の影響を除いたら1.9%と、「2%の物価安定目標」に届いていないといえるものでした。
2014年4月に実施された3%の消費増税に伴う、消費者物価コア前年同月比上昇率の統計上の嵩上げ効果は、2015年3月までの1年間限定のものであり、黒田日銀総裁が設定した「2%の物価安定目標」の期限である2015年4月には統計上消費増税による消費者物価の押し上げ効果が消滅することは明白でした。こうした中、想定以上の消費増税に伴う駆け込み需要の反動が出てきたこともあり、消費者物価コアは2014年5月の前年同月比3.4%上昇をピークに低下に転じ始めてしまいました。
消費増税が国内景気に悪影響は及ぼさないと繰り返してきた安倍政権と、2015年4月までに「2%の物価安定目標を達成する」と豪語した黒田日銀総裁にとってこうした動きは由々しき問題でした。
同時に、「大胆な金融緩和」と「異次元の金融緩和」に対する期待と、消費増税を控えた駆け込み需要で景気が上向いたことなどを背景に順調に推移してきた株式市場でも、消費増税後の消費の落ち込みが想定以上だったことなどから、その上昇に陰りが見え始めてきました。「デフレからの脱却」の成果を示す象徴であった株高に陰りが見え始めるというのは、「株価先行型」の景気回復を目指していたアベノミクスには極めて危険な兆候であり、何かしらの手を打つ必要が出てきたのです。
黒田総裁が自ら設定した「異次元の金融緩和」の目標達成期限である2015年4月まで半年を切り、消費増税に伴う消費の低迷と消費者物価コアがピークアウトしたことが明らかになり始めた2014年10月に、黒田日銀総裁と安倍内閣は協力し合うかのように新たな追加策を打ち出すことになりました。
2014年10月31日、黒田日銀は市場に不意打ちを食らわせるかのようなタイミングで「『量的・質的金融緩和』の拡大」に踏み切りました。
追加緩和の具体的内容は「マネタリーベースが、年間約80兆円(約10〜20兆円追加)に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う」というものでした。このタイミングでの追加緩和を想像していなかった市場はこの決定を好感し、半年近く1万4000円〜1万6000円台で推移していた日経平均株価は2万円を目指して再浮上し始め、なかなか110円を突破できないでいたドル円も120円を目指して動き出し始めたのです。
市場が予期しないタイミングでの金融緩和拡大で再び円安・株高を演出したことで、マスコミはこれを「黒田バズーカ第二弾」として称賛し、黒田日銀に対する信頼と畏敬の念を一段と高めるようになりました。しかし、想定しないタイミングで「黒田バズーカ」が放たれたことで市場は大きく反応しましたが、マネタリーベース、市場に出回る資金の量を増やすことだけで株高を演出できたわけではありません。「黒田バズーカ」には株高を演出するために必要な資金が用意されていたのです。
「ETFおよびJ-REIT(注1)について、保有残高が、それぞれ年間約3兆円(3倍増)、年間約900億円(3倍増)に相当するペースで増加するよう買入れを行う」(日本銀行「『量的・質的金融緩和』の拡大」2014年10月31日)
黒田日銀は2013年4月4日に打ち出した「異次元の金融緩和」で「戦力の逐次導入はしない」と宣言してそれまでの年間購入額が5000億円であったETFの購入額を2倍の1兆円に引き上げました。しかし、2014年10月31日に打ち出した「黒田バズーカ第二弾」ではさらにその3倍の年間3兆円まで一気に引き上げ、中央銀行が「異次元のリスク」を抱え込むことにしたのです。ETFの年間購入額を2兆円増やしたのですから、株式市場が上昇に転じるのは当然のことでもありました。
しかも、この時日銀がETF購入額を一気に3倍増やすのに呼応するように日本株を購入する主体が現れました。それが公的年金を管理運用し、「世界最大の機関投資家」といわれる「年金積立金管理運用独立行政法人」、通称「GPIF」でした。
注1 J-REIT 多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションといった複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品。REITとは“Real Estate Investment Trust”の略で、Jは日本のJAPANを意味している。一般的に「不動産投資信託」と呼ばれるように法律上は投資信託の仲間。ETF(上場投資信託)と同様に証券取引所に上場しており、株式と同様に売買が可能。
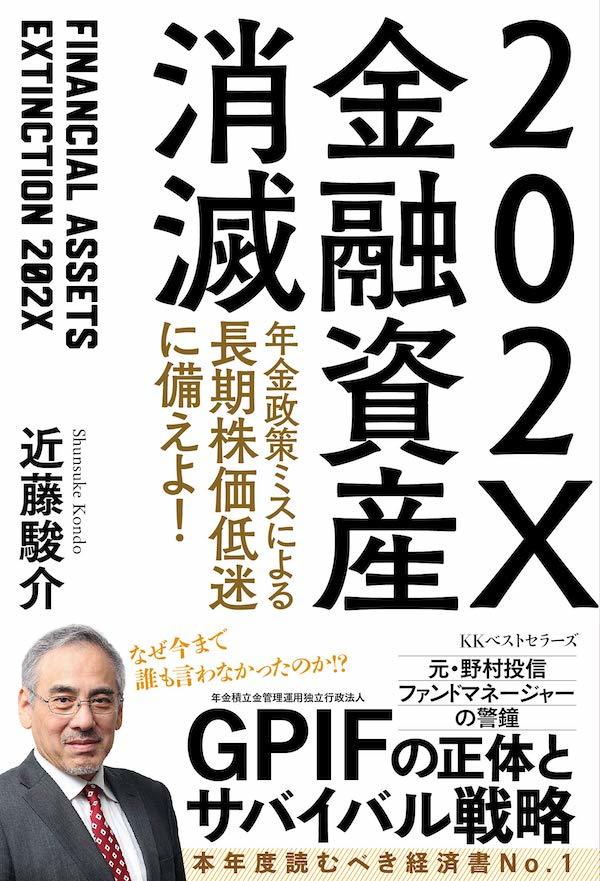
金融・経済・資産運用評論家。1957年東京生まれ。早稲田大学理工学部土木工学科卒業。大手総合建設会社勤務を経て、31歳で野村投信(現・野村アセットマネジメント)に入社。ファンドマネージャーとして25年以上にわたり、株式、債券、デリバティブ、ベンチャー投資、不動産関連投資など、さまざまな運用を経験。90年代中頃には合計約8000億円と日本最大規模の資金を運用していた。現在は、評論家、コンサルタントとして活動し、テレビ、webメディア、雑誌などにコメント提供や記事執筆をしている。著書に『1989年12月29日、日経平均3万8915円』(河出書房新社、2018年)などがある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
