映画などで米国のホワイトハウスが登場する作品を観ていると、こんなシーンが描かれていることがある。緊急時にオーバルオフィス(大統領執務室)で、補佐官たちが大統領を取り囲んで何やらブリーフィングをしているシーンだ。テーマとなるのは世界のどこかで発生した軍事衝突の話であったり、あるいは米国内でテロが起こされる可能性だったり、何か危機的状況が近づいているような話。その時、大統領は首席補佐官にこう尋ねる。
「で、我々のオプションは?(What is our option?)」
「はい。担当のジャックが説明いたします」首席補佐官がジャックに目配せした。
「2つあります。ひとつは我々の意思表示としてインド洋に展開中の第7艦隊を派遣してけん制する。もうひとつは……」
上記の会話で大統領は選択肢という意味で「オプション」という言葉を使っている。要するに何らかの対応判断が必要なシチュエーションが発生した際に、どういう対応をしたらよいのか、取り得る手段の選択肢を「オプション」と呼んで専門スタッフの意見を聞いているわけだ。
上記の会話の続きを解説すると、ジャックは大統領に2つの「オプション」を示し、それぞれの選択肢にそれぞれ成功した場合の果実(リターン)と、期待通りに進まなかった場合のリスクを提示する流れとなる。そして、大統領はその「リターンとリスク」のバランスを考慮しつつ、自国にとってベストと思われる方法を採用することになる。
実はこれが「オプション」と呼ぶ金融商品の特徴ととてもよく似ている。
すなわち、オプションとはあくまでも「選択肢」であって、どれを採用するかは自由であり、あるいは採用しないのも自由ということだ。筆者が知る限り、日本の投資の教科書では、オプションは「買う権利」と「売る権利」で、その「買う権利を売る」とか「売る権利を買う」といった説明から始まることが多いように見受けられる。まるで「とんちクイズ」のようで頭がこんがらがる人もいることだろう。せっかく、オプションについて勉強しようと思っても、入り口でこんがらがるからドンドン分かりづらくなる。
たとえば、いま500円のものを「400円で買う」「500円で買う」あるいは「500円で売る」「600円で売る」という選択肢の話と考えたら、オプションの本質を捉えやすくなるのではなかろうか。そもそも「option」という英語自体が「選択肢」という意味を含んでいるのだから。
「選択肢」を売り買いするとは、どういうことなのか?
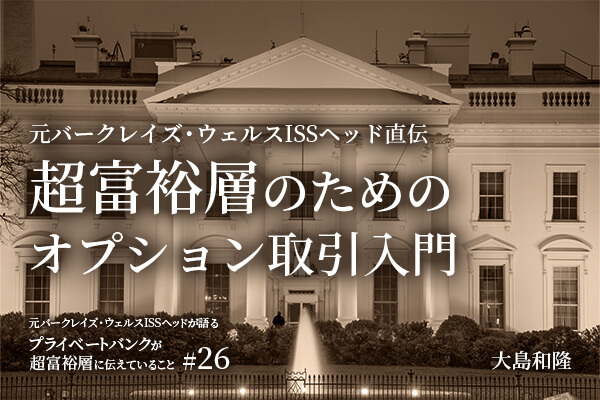
オプションを学ぶ際に混乱しやすい、もうひとつの側面として、その「選択肢」を売ったり、買ったりするという取引の部分が指摘される。だが、この話は保険契約に置き換えるとわかりやすくなる。すなわち、保険契約者と保険会社の関係だ。自動車保険、火災保険、あるいは海外旅行保険など損害保険をイメージしていただくとわかりやすい。
たとえば、自動車保険(車両保険)は「事故が起きたら、その損害を保険会社に補填してもらう」というのが基本となるが、保険契約者の多くが毎年「万が一の安心のため」に保険に加入しており、実は長年の支払総額とその効用を金銭面だけで比較すると損をするケースもある。
仮に毎年10万円の保険料を払っているとして、実際にその累積支払額以上の保険金を請求する確率はどれくらいだろうか。万が一、大きな事故でも起こしたら大変なので「安心料」として保険料を払って納得している人もいることだろう。
実はこれがオプションの「買い」と「売り」の代表的な側面を表している。すなわち、保険契約者をオプションの買い手、保険会社をオプションの売り手と考えてみよう。この場合、オプションの買い手である保険契約者が一生涯事故を起こさなければ、オプションの売り手の保険会社が儲かることになる。
一方、保険契約者はどうだろうか。一生涯事故を起こさず、保険料が無駄になったことについて「損をした」とがっかりするだろうか。何年も無事故を続けて「保険会社ばかり儲けさせてしまったな」と自嘲することはあるかもしれない。だが、事故を起こした時には充分な補償が得られるとはいえ、そもそも「事故を起こさなければそれに越したことはない」と考えるのではないだろうか。
実はオプションも保険も、その価格の算定根拠は「万が一、○○となったら」という事象の発生確率に基づいている。その想定される事象が発生した場合には必要な金額が支払われるが、何も起こらなければ支払われない。だからこそ、その事象が起こりそうであれば保険料が高くなり、起こる可能性が低いのであれば保険料は安くなる。正に確率論の世界だ。





