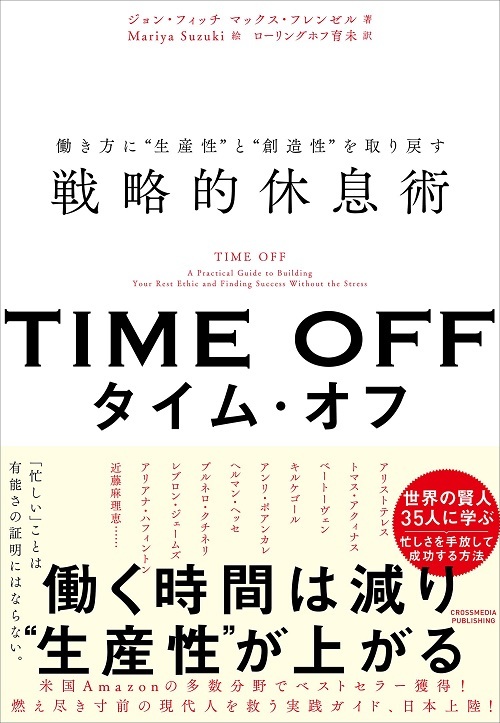本記事は、ジョン・フィッチ氏とマックス・フレンゼル氏の著書『TIME OFF 働き方に“生産性”と“創造性”を取り戻す戦略的休息術』(クロスメディア・パブリッシング)の中から一部を抜粋・編集しています。

「ひとつへの集中」を打ち壊そう
オルダス・ハクスリーを知っているだろうか。小説『すばらしい新世界』や『島』を発表し、ディストピアやユートピアについて描いた人物だ。
しかし近年のサイケデリックなものへの関心の高まりにより、彼のノンフィクション作品『知覚の扉』にも注目が集まっている。
これは人間や社会の存在における根本的な問いを投げかける作品だ。とくに彼が心を痛めていたのは、周りの人たちがバランスを失っていることと、彼らの「〜にほかならない」という態度だった。
ハクスリーは、見識の狭さや専門分野を重視することが社会問題になっていると考えただけでなく、教育の問題点にもなっているのではないかと思い巡らせた。
彼のエッセイ集『内なる神聖なもの』(原題『The Divine Within』未邦訳)で、彼はこう述べている。
「すべてのことが仕分け棚の中で進んでいる。しかし学術施設に必要なのは仕切られた棚同士をつなぐための大工仕事をする人たちだ。すべての棚の声が聞こえ、みんなでなにができるのか考えることが必要なのだ」
現代の僕たちにとって、いちばん有効で、しかもスマートな選択は、仕切られた棚の中をのぞき、それぞれの空間をつなぐ人になることだというわけだ。詳しく説明しよう。
リラックスしていなければアイデアは温まらないのだろうか。
そんなことはない。他のことをしているときも、アイデアは温められている。ウォーラスはこう述べる。
「いくつかの課題に同時に取り組む方が、良い結果を生む場合が多い。いっぺんに始めると手をつけられない課題がいくつか出てくるが、それでいい。ひとつの課題に取り組んでいるうちに、自然とその他の課題も進むはずだ」仕事とは関係ないことにいそしむのは、現代の「高尚な余暇」である。タイムオフを習慣化している人からすれば当たり前のことなのだ。
そう考えると、友達に料理をふるまうことを「仕事」と言うこともできるだろう。しかし、それには仕事とは異なる意義がある。日々の仕事から少し抜け出すことができるという。それがアイデアの温めには欠かせないのだ。
英国人アーノルド・ベネットは、1908年の自著『自分の時間』(三笠書房 2016年)で、いろいろなことをすること自体がタイムオフになりえると主張する。休息と同じくらい効果的らしい。
アーノルド・ベネットは次のように書いている。
「なんだって? (就業時間外の)16時間でエネルギーを使い果たしてしまうと、就業時間8時間の効率が落ちるというのか? そんなことはない。まったく逆で、効率は上がる。まず、従業員にいちばん学んでほしいのは、働き続けることのできる強いメンタルなのだ。腕や足のように疲れるようでは困る。メンタルが求めているのは変化だ。休息ではない。睡眠以外の休息は逆効果だ」
余暇にエネルギーを費やせば、すべての活動においてエネルギーが持続できるようになるのだ。
アーサー・ケストラーも彼の著書『創造活動の理論』(ラテイス 1967年)で、創造的な活動によって考えを温めることを勧めている。
課題が複雑であるほど、無意識下での成果が大切だと彼は述べる。常識や普通だと思われていることをぶち壊すことが大事で、思考にクリエイティビティが生まれるのだ。
「創造的な行動には、革命的で破壊的な一面があります」
歴史上、その犠牲はあちこちで出た。流行り廃れた芸術の主義だったり、天動説だったり、フロギストン(酸素の発見前まで、燃焼の際に放出されると考えられていた架空の物質)だったりする。
その壊す力は、探求によって湧いてくる。常に学び直すことと遊び心が欠かせない。
ケストラーはまた、まじめすぎてはいけないと言う。
「まじめな人は、頭が多面的でなく平らだ。適応力は高いが破壊力は低い。頭は良くても保守的では、革命など起こさない。指示がないと学ぶことができず夢に向かうことができないんだよ」
異なる音楽ジャンルのミュージシャンの経験が、よい例かもしれない。
ジャーナリストのデイビッド・エプスタインは『RANGE 知識の「幅」が最強の武器になる』(日経BP 2020年)で、クラシック音楽のミュージシャンは幼年期から専門的にスキルを身に付けるために多くの時間を費やし、規則に則ったレッスンを繰り返し受けると指摘する。意図された訓練の見本となる子供たちだ。そしてケストラーの言う「まじめ」な人たちだ。
一方で、トップレベルのジャズミュージシャンは、幼年期から形式ばった訓練を受けた例が少ないという。さまざまな楽器を試し、自分なりに実験を重ね、自分に合ったものを見つける。楽譜の読み方を学ばない人たちも少なくない。
クラシック音楽の重要な細かい技能を蔑んでいるわけではないが、厳しい訓練を長年受けると「即興演奏」がとても難しくなる。
ジャズ(幅がある)からクラシック(ひとつにしぼる)への転向はより簡単だし、逆の転向よりも実際に多い。広く学んだあとにひとつのことに深く潜る方が、深い穴を掘ってその穴の中から違うところを目指そうとするよりも簡単なのだ。
エプスタインは、巨匠ギタリストのジャック・チェッキーニの言葉を引用している。チェッキーニもジャズから始めて、クラシックギターへの愛に目覚めたひとりだ。
「ジャズミュージシャンはcreative(創造的)なアーティストで、クラシックミュージシャンはre-creative(再・創造的)なアーティストなんだよ」
人工知能(AI)にとっても、創られたものを再現すること(re-creating)は、創り出すことよりも簡単だ。
事実、本記事の共著者であるマックスは人工知能と音楽の交差点で働いている。アーティストと企業のパートナーと協力して、コンピューター技術が人間のクリエイティブなプロセスにどう役立つのか研究している。遊んだり、様々な選択肢を試したりしながら、音楽を届ける新しい方法を考えているのだ。
AI音楽の実験では、クラシックやテクノなどのジャンルの作曲家やパフォーマーの真似をさせる。厳しいルールやきちんとしたパターンがあるため、機械にとって学びやすいからだ。
一方で、ジャズ音楽の即興演奏は、機械にとっては手が届かないところにある。最新のアルゴリズムは、狭い領域(ドメイン)での性能は上がっているが、ドメインを越えて散らばるアイデアをつなげるのは苦手だからだ。そしてこの傾向はすぐには変わらないだろう。
自問してみてほしい。今までジャズのリズムで仕事をしてきただろうか?
それともクラシック音楽の厳しいルールに従ってきただろうか?
これからは、ジャズのリズムを多めに取り入れてもいいかもしれない。
AIが活躍する未来では、ひとつのことしかできない人よりも、多くをこなせる人の方が強いのだから。
ひとつにしぼらないのであれば、すべての経験をひとまとめにしなければならない。そのためには、休息と静寂が必要だ。
オルダス・ハクスリーはクラシック音楽の大ファンで、とくに、音のない時間は作品において大切だと考えていた。
「休息は静寂」(原題「The Rest is Silence」未邦訳)と題されたエッセイで、彼はこう述べている。
「すべての優れた音楽で共通するのは静寂である。ベートーヴェンとモーツァルトに比べたら、ワーグナーの押し寄せる音は静寂において貧しい。後者があまり重要視されない一因かもしれない。いつも話しているから響かないのだ」
世界の美しさを前に僕たちは一歩下がり、そのすべてに身を浸たす。
タイムオフの静けさと、仕事が交わるようになれば、仕事自体のクリエイティビティや成果も高まるに違いない。
ひとつのことを極めなければ成功できないなんて、誰が言ったのだろう。
時代が進むにつれて、ひとつのことしかできないことは、苦しみしか引き起こさなくなるかもしれないのに。
ひとつ以上のものに秀でることは可能だ。実際に成し遂げた人も多い。しかし、そのためには仕切られた棚の中で閉じこもっていてはダメだ。
ひとつのことだけに集中するのでなく、多くのことを同時に自由にやってみよう。そして共通点を探そう。重なる面白いところに目を向けよう。一石二鳥だ。
そんなふうに生き、仕事をすれば、新しい繋がりが見つかり、可能性が広がるだけでなく(しかもAIに負けないですむ)、タイムオフを組み込んだ日々が始まるのだ。
すべての興味をしっかりと抱きしめれば、燃え尽きることなく成功や目的地にたどり着くことができる。