これまで「ふるさと納税」には「お得な制度」という、高額所得者にとって大きな魅力があることを説明してきた。ここで少し視点を変えて、この制度が果たしてきた「社会的な役割」についても触れておきたい。そこには、経済的な利点はもちろんだが、富裕層にとってはマストともいえる「社会貢献」や「フィランソロピー」のツールとしての側面があるからだ。
「社会貢献」のツールとしての側面に着目
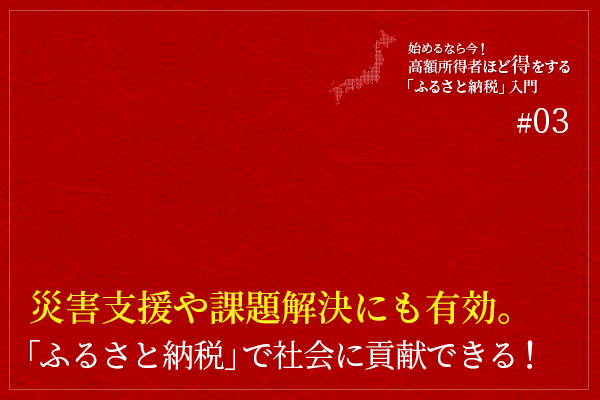
2018年7月、西日本を中心とする地域を猛烈な豪雨が襲い、甚大な被害が出たことは記憶に新しい。テレビでも連日、その被害の状況や避難所の様子などが映し出されていた。その様子を見て「自分にも何かできないだろうか」と思った人も少なくないだろう。自由な時間や行動力があれば現地に飛んで行って、ボランティアとして作業することも可能だが、多忙なビジネスマンにとってそれは現実的ではない。やはり寄付や募金などで経済的に支援することが有効な方法だ。
実はこの災害の直後から、広島県呉市、岡山県倉敷市といった被害の大きい自治体に対し、ふるさと納税を通して寄付が集まり始めた。最大手のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」では、発災からわずか2週間の間に全国から合計10億円以上の寄付が集まったという。しかも、寄付とともに多く寄せられたのは、「返礼品はいらないから、とにかく役立ててほしい」という寄付者からの温かいメッセージだった。
2016年の熊本地震では寄付総額18億円に!
日本はいわば「災害大国」で、毎年のように地震をはじめ、台風、豪雨など、各地が災害に見舞われている。同サイトでは2014年の長野県内の地震を機に、「災害時に機動的に寄付を集めるための窓口」として、被災自治体に「災害時緊急寄附申込みフォーム」の提供をスタート。被災自治体が災害直後からスムーズに寄付を集められるよう、受け皿となるフォームを無償で提供し、数々の災害に対応してきた。
さらに、2016年の熊本地震の際には、多忙を極める被災自治体に代わって、被災地以外の自治体が代理で寄付を受け付ける「代理寄附受付」も開始した。災害直後、被災自治体の職員は被害状況の把握や住民対応に追われ、寄付者への対応にまで手が回らない。そこで、被災していない自治体が寄付者への「寄附金受領証明書」発行、発送などの関連業務を代わりに引き受ける。その結果、被災自治体に対し、代理受付分を含めて総額18億円以上もの寄付が集められたのだ。
東日本大震災で有効な支援手段として注目
ふるさと納税の制度には、もともと構想段階からこうした「災害支援」や「自治体同士の連携」の発想があった。制度発案者の一人である西川一誠福井県知事は、かつて福井豪雨の際に宝くじの2億円当せん券が匿名で寄贈されたのを機に、全国からボランティアが集まり、支援の輪が広がったことから、他地域への支援や連携を制度化することを着想したという。
そうした成り立ちや理念を体現するかのように、制度開始から数年間あまり知られていなかったふるさと納税が一躍認知度を上げたのは、2011年の東日本大震災のときだった。各地から未曾有の被害状況が報じられる中、被災自治体にピンポイントで支援の気持ちやお金を届けられる有効な方法として注目を集めた。
募集団体の信頼性を確かめるのが困難な「募金」や、分配に時間のかかる「義援金」に比べ、自治体へ直接、スピーディーにお金を届けられ、しかも寄付額のほとんどが税金から控除されるため、安心して寄付することができる。その有効性が口コミやメディアなどで徐々に広がり、横ばいだった利用件数や寄付総額が2011年度には増加。やがて「返礼品はもらえなくても、今すぐ現地の役に立ちたい」という思いの受け皿となり、今では災害のたびに活用されている。
クラウドファンディング型が増加
ふるさと納税が果たしてきた社会的な役割は、何も災害支援だけにとどまらない。最近では、環境保全や貧困問題など、地域が抱えるさまざまな課題解決のために、自治体がふるさと納税の制度を利用して寄付を募る「クラウドファンディング型」の寄付募集が増えている。