本記事は、伊藤佑介氏の著書『インターネット以来のパラダイムシフト NFT1.0→2.0』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています
これからのNFT活用における問題点と課題

手数料の高さ
プレイヤーであるマイナーが、ビットコイン賞金ゲットゲームに参加するために、ブロックチェーンシステムを動かしています。そしてこのゲームでは、新規発行された6.25ビットコイン(2022年2月時点の価格水準換算で約3,125万円相当)の賞金が勝者に渡されます。実はその際、勝者がもらえるもうひとつ別の賞金があります。
それは、箱の中に入っている4,000個の取引データのそれぞれひとつずつからもらえる送付手数料です。ビットコインを他の人に送金する人は、ゲームの勝者へ賞金として支払う送付手数料を、自分で自由に金額を設定して送金することになっています。なお、この送付手数料は、ガス代と呼ばれることもあります。
当然、ゲームに勝利してそれをもらえるかもしれないマイナーたちは、なるべく送付手数料が高く設定されている取引データを箱に入れます。つまり、高い送付手数料を設定した取引データほど、上限が4,000個の箱に入れてもらいやすくなり、結果的に早く送金してもらえることになります。
なぜ、新規発行の6.25ビットコインという賞金があるのに、わざわざ送付手数料も賞金としてゲームの勝者に渡すようにしているのでしょうか。
それは、ビットコインには2,100万ビットコインという総発行量の上限があるからです。今後ずっと10分に1回開催され続けていくゲームで、このまま賞金として新規発行のビットコインを勝者へ配り続けていくと、2140年には上限に達し、それ以降のゲームでは、新規発行の賞金がなくなることが分かっています。そのため2140年以降は、このゲームの賞金は送付手数料だけになるということです。
もしも賞金が新規発行のビットコインだけだったとすると、2140年以降のビットコインのブロックチェーンシステムはどうなるのでしょうか。
言わずもがな、2140年以降はなんの賞金ももらえなくなるので、全てのマイナーがゲームをやめるでしょう。そのためマイナーは、ゲームに参加するためにビットコインの取引データを記録していたコンピューターを停止します。もちろん、マイナーのコンピューターがなければ、新しい取引データのチェックがされることもありません。つまり、2140年以降に新規発行の賞金が全くなくなれば、ビットコインのデータは全て消えてなくなり、その後の新しい取引もできなくなるということです。以上の理由から、マイナーが仮想通貨をインセンティブとして動かしているブロックチェーンシステムには、送付手数料の賞金が必要であるということが分かるでしょう。
NFTを発行するのに今1番使われている、イーサリアムというブロックチェーンシステムも、イーサという仮想通貨をインセンティブとしてマイナーが動かしています。そのため、そこで発行したNFTを送信する際にも、ゲームの勝者となったマイナーに支払うための送付手数料を、仮想通貨のイーサで支払います。
しかし、最近この送付手数料が高すぎることが問題となっています。例えば、イーサリアムのブロックチェーンシステム上に発行されたNFTの送付手数料は、高いときで数千〜数万円相当の仮想通貨のイーサが必要になります。これだと、250円で買ったNFTを、他の人に2倍の500円で販売したとしても、利益は出ません。それどころか、マイナスになってしまいます。
以前は、この送付手数料は数円程度でした。なぜこんなに高くなってしまったのでしょうか。理由は2つです。
ひとつ目の理由は、仮想通貨の価格が高騰しているからです。
支払いで使われる仮想通貨の価格が、最近上がってきています。そのため、法定通貨の円で換算した送付手数料の金額がとても高くなっているのです。
次に2つ目の理由は、NFTを送付する人が急増しているからです。
前述のとおりゲームのプレイヤーであるマイナーは、勝ったときになるべく多くの送付手数料を賞金としてもらえるように、箱に入れる4,000個の取引データを選ぶ際、高い送付手数料を設定している取引データから先に入れていきます。
NFTを送付する人の数が少なく取引の数も少なかったときは、低い送付手数料を設定しても、しばらく待っていれば箱の中に入れて送付してもらえていました。しかし2021年から急激にNFTを送付する人の数が増えてきたため、今ではNFTの送付手数料を一定程度以上に高く設定しなければ、送付してもらえなくなってしまったのです。
つまり、仮想通貨の値上がりと、NFTを送付する人の増加という2つの要因によって、NFTの送付手数料が高すぎるという問題が発生しています。
環境への負荷
ブロックチェーンシステムを動かしているマイナーは、ビットコイン賞金ゲットゲームで1番にアタリ番号を見つけるべく、自分の持っている高性能のコンピューターを365日24時間フル稼働させています。全マイナー合わせて1秒の間に1垓回以上といった天文学的な回数の計算を行う高性能のコンピューター群は、膨大な電力を使っていることになります。ビットコインの年間消費電力は、ひとつの国が1年間で消費する量に相当すると言われるほどです。
公益財団法人自然エネルギー財団によると、2020年に発電された世界の電力のうち、61.3%が石炭、石油、天然ガスといった化石燃料を使った電力発電となっており、やはりビットコインの膨大な電力消費が環境に与える負荷は大きいことが分かります。
また、この膨大な電力を消費する、アタリ番号を見つけるための計算は、ゲームの難易度が常に一定程度高くなるように、参加するマイナーが多くなるほど必要となる回数も増えるように調整されています。そうすることで、どれだけ多くのマイナーで競い合ったとしても、アタリ番号を見つけるのに少なくとも10分程度はかかるようにして、ビットコインのデータが改ざんされにくくしているのです。
これに対して、「ビットコインのデータが改ざんされないようにする、ただそれだけのために過剰に電力を浪費して、環境に負荷を与えていいのか」という疑問の声が、世界中で上がっています。
そこで、この問題の解決に向けて、大量の電力を消費しなくともデータが改ざんされないようにできる、別の新たなゲームを採用したブロックチェーンの研究が行われています。
互換性のなさ
NFTは、二次流通されても作家に収益が還元されるように設定できます。
もちろん作家からすると、最初に収益還元率を決めて、作品をNFTとして1度販売してしまえば、その後は世の中にたくさんあるどのNFTマーケットで二次流通されたとしても、同じ料率で収益が還元されるのが1番望ましいことです。
実はこのNFTの二次流通時の収益還元というのは、「やろうと思えばできる」ことですが、「必ずされる」ことではありません。では誰が「やろうと思えばできるのか」というと、それを二次流通させるそれぞれのNFTマーケットです。つまり、異なるNFTマーケット間を転々して二次流通されても、収益還元されるNFTマーケットと、されないNFTマーケットが出てきてしまうということです。また、複数のNFTマーケットで販売した場合でも、二次流通時の収益還元率が必ずしも全てのNFTマーケットで同一になるとは限りません。
なぜなら、NFTマーケット同士は競合関係にあるため、それぞれ自社の戦略に従って競争優位性が高まるように、収益還元率を設定するからです。
例えば、NFTマーケットAが作家への収益還元率を5%にしているのを見たNFTマーケットBが、「作家への収益還元率を高くして、競合から作家を奪おう」と考えて収益還元率を10%に設定することもあるでしょう。あるいは、別のNFTマーケットCは、「作家への収益還元率を低くして、二次流通でユーザーが得られる転売益を増やし、競合からユーザーを奪おう」と考えて、収益還元率を3%に設定することもあるかもしれません。
この場合、NFTマーケットBはNFTを販売してくれる作家を増やす戦略、NFTマーケットCはNFTを二次流通させてくれるユーザーを増やす戦略ということになります。
以上のように、NFTを販売する作家の立場から見ると、NFTマーケット間に収益還元ルールの互換性がないという問題が存在しています。
一方で、NFTマーケット間を横断してできることもあります。それは、全NFTマーケットの二次流通取引の透明性を一貫して確保できることです。
これまでは、作家は自分の作品が二次流通市場で、いつ、どのマーケットで、誰から誰へ転売されたか知る術がありませんでした。しかし、前述のとおり、NFTであれば所有者が誰から誰に変わったかという移転情報が、絶対に改ざんされないデータとして、ブロックチェーンシステム上で広く世の中に公開されます。
そして実は、ブロックチェーンシステム上には移転情報だけでなく、各NFTマーケットがあらかじめ設定した料率で収益を還元した取引実績情報も、絶対に改ざんされないデータとして記録、公開できます。
つまり、作家はブロックチェーンシステム上のデータを見れば、自分の販売した作品が、それぞれのNFTマーケットにおいて、設定した収益還元率で取引されたのか、もしくは収益還元なく取引されてしまったのか、いつでも自分でチェックできるということです。
他方、フリマアプリで自分の作品が転売された場合、その取引データはフリマアプリ企業の社内システムに記録されるので、見ることすらできません。また、たとえ将来、フリマアプリが作家へ収益還元を行うようになり取引データを公開したとしても、企業内部のシステムに記録されたその取引データは自由に書き換えが可能なため、取引の透明性は担保できません。
そう考えると、現状NFTマーケット間の収益還元ルールの互換性まではないにしても、NFTによって二次流通の取引の透明性を一貫して確保できることは、これまで二次流通の取引実績を知ることすらできなかった作家にとって、大きな意義があると言えます。
今後NFTの二次流通市場がますます広がっていく中で、NFTマーケット間の連携が進み、こうした収益還元ルールの互換性の問題解決が期待されています。
使い勝手の悪さ
NFTを購入して所有するためには自分のウォレットが必要になりますが、これがNFTのサービスの使い勝手を悪くする大きな要因となっています。簡単に言うと、次の2つの点でユーザーにとって不便を生じさせているのです。
ひとつ目は、ウォレットの利用に際して、人間が到底暗記できないようなパスワードを、自分で忘れないように自己管理させられることです。普段使っているWebサービスのパスワードは、英数字と記号を組み合わせた10文字前後のものです。しかし、前述したMetaMaskの説明のとおり、NFTのサービスでユーザーアカウントに相当するウォレットのパスワードは、12個もの単語からなる長いパスフレーズとなっていて、覚えておくことは困難です。もし、あるWebサービスを使おうとして「パスワードとして、12個の単語を入力してください」とログイン時に求められたら、誰もそのサービスを使わないでしょう。
また、ウォレットのパスワードとして、この12単語のパスフレーズではなく、プライベートキー(秘密鍵)と言われる数十文字の英数字を使うこともできます。しかし、それに至っては単語にすらなっておらず、意味のない文字の羅列でしかないため、もはや人間が暗記することは不可能です。
2つ目は、その12個の単語もしくは数十文字の文字列のパスワードを忘れたり、メモをなくしたりしたら、そのユーザーアカウントに二度とログインできなくなり、持っていた全てのNFTを失うことです。
Webサービスであれば、パスワードを紛失しても、そのサービス運営会社による再発行が可能です。しかし、NFTのサービスを利用するための、ユーザーアカウントに相当するウォレットのパスワードは、一度紛失してしまうと誰も再発行できません。
もし、パスワードを紛失して、サービス運営企業へ問い合わせても「パスワードは再発行できません。もう二度とログインできないため、そのユーザーアカウントで購入した商品も使えなくなりますが、当社は一切対応できません」と返してくるWebサービスがあったとしたら、誰も利用しないでしょう。
以上のように、現状ではNFTのサービスを利用するために使う、ユーザーアカウントに相当するウォレットで覚えられない長さのパスワードを使わせられる不便さと、パスワードを紛失すると二度とログインできなくなり、持っていたNFTを失う不親切さの2つの問題があります。つまり皆さんが普段使っているWebサービスのように、当たり前なレベルで快適に利用できるようにはなっていないのです。
この問題に対しても、ウォレットをユーザーに代わってサービス運営企業が管理したり、パスワードを複数人で管理して1人が紛失しても問題のないようにしたりと、いろいろな解決に向けた取り組みが現在行われています。
処理速度の遅さ
一般的に、クレジットカード会社の決済システムは、1秒間に数千件以上の取引データを処理できます。その一方で、ビットコインのブロックチェーンシステムは、1秒間に数件程度の取引データしか処理できません。なぜ、ビットコインのブロックチェーンシステムはこれほどまでに遅いのでしょうか。
その理由は、データが改ざんされないように守ってくれている、ブロックチェーンの箱にあります。つまり、箱はデータを守ってくれている一方で、処理速度を遅くするボトルネックにもなっているということです。イメージしやすいように、ここからはざっくりとした仮定の数字と計算で説明します。
この箱は4,000個の取引データが入るとゲームが始まり、10分間=600秒間で終わって閉じられるので、1秒間に6件(=4,000個÷600秒)程度の取引しか処理できないことになります。では、どうすれば1秒あたりに処理できる取引件数をもっと増やせるのでしょうか。
答えはとても簡単なことで、箱に4,000個よりもたくさんの取引データを入れられるようにするだけです。では、箱を1,000倍に大きくして、4,000,000個も取引データが入るようにしたとしましょう。すると、1秒間に6,666件(=4,000,000個÷600秒)も処理できるようになります。1秒間に数千件処理するクレジットカード会社の決済システムと同レベルです。しかしビットコインは、誕生の2009年から13年たった今も変わらず、1秒間に6件程度しか処理できません。こうして簡単に解決できるのに、一体なぜ箱を大きくしないのでしょうか。
それは、箱を大きくすると、このゲームに参加するプレイヤーであるマイナーが、前述したとおり、ゲームの参加条件として自分のコンピューターに記録しなければならない、過去全ての取引情報の総データ容量が大きくなりすぎるからです。
2009年から2022年現在までの間に、ビットコインの4,000件の取引データが入る箱は、約70万個も閉じられて鎖でつながっています。
この70万個の箱に入っている過去全ての取引情報の総データ容量は、約400GBです。400GBを保存するのにかかるクラウドストレージの月額料金はだいたい数千円で、年額でも数万円程度です。
しかし、箱に入る取引件数を4,000件から4,000,000件へ1,000倍に増やして、クラウドストレージにかかる費用も単純計算で1,000倍になるとすると、月額料金で数百万円、年額で数千万円にも跳ね上がります。
以上の前提で、実際に処理速度を早くするために箱を1,000倍に大きくしたとします。するとおそらく、現在ゲームに参加している約1万人のマイナーの多くが、年間数千万円もの費用を負担できずにゲームから離脱するでしょう。
そうでなくとも、この先20年、30年、40年と時間が経過するごとに総データ容量は比例して大きくなっていくので、将来ますますマイナーの数は減少していくことが予想されます。
ブロックチェーンシステムのデータが改ざんされないのは、多くのマイナーがこのゲームに参加し、その参加条件として過去全ての取引データを保管して、かつ新しい取引データをチェックしてくれているからです。
そんな中で、上記のように箱をむやみに大きくしてマイナーが著しく減ってしまうと、データが改ざんされるリスクが高まるため、ビットコインは2009年から今までずっとデータの処理速度が遅いままになっているのです。
ただし、この問題を解決しようとする技術開発もさまざま進んでいます。
そのひとつとして、取引データの箱を閉じるのに10分も時間がかかる、ビットコイン賞金ゲットゲーム自体をなくして、処理時間を速くする新しい方法が開発されています。その新しい方法では、今まで10分かけてゲームで決めていた、取引データをチェックした後に箱を閉じる人を、どう決めるのでしょうか。
一言で言うと、最も大切にしているモノを、人質として差し出した人に決めます。人質とは何かというと、資産として保有している仮想通貨です。
具体的には、賞金を求めるマイナーたちに、人質として自分の仮想通貨を差し出させます。その中で、最も高額の仮想通貨を差し出したマイナーが選ばれて、データをチェックした後に箱を閉じます。このとき、正しくチェックして箱を閉じれば、賞金の仮想通貨がもらえるという流れです。
もしも取引データのチェックで不正をしたら、人質として差し出していた高額な仮想通貨は全て没収されてしまいます。そのため、選ばれたマイナーは、差し出して預けている高額な仮想通貨が没収されないように、不正をせずにしっかりと取引データをチェックしようとするのです。
この新しい方法だと、10分もかかっていた箱を閉じる作業が数秒で終わるため、処理速度を早くできます。
また、これまでの方法は「10分間のあてずっぽうの計算にかけた費用が無駄になるから、取引データのチェックで不正なんかしないでおこう」とマイナーに思わせていましたが、新しい方法では、「人質に預けた高額な仮想通貨が没収されるのは嫌だから、取引データのチェックで不正なんかしないでおこう」と思わせるようにしています。
つまり、不正をさせないための人質を、「自分が10分間で費やしたコスト」から「自分がこれまで数年にわたって蓄積してきた資産」という、より重要度の高いものとすることで不正を防ぎ、かつ箱を閉じるマイナーを決定する時間を大幅に短縮して、取引の処理を高速化させられるのです。
この新しい手法は、ビットコイン以外では既に利用されており、採用するブロックチェーンシステムが増えてきています。
未整理の法解釈
現在、実はNFTについて、定義もルールも法的には定められていません。一方で、同じブロックチェーン技術を使っている仮想通貨(正式名称:暗号資産)は、資金決済法という法律で、“財産的価値”と定義されています。この資金決済法の第1条では、以下のようにその目的が記載されています。
「この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、暗号資産の交換等及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする」
そして上記のとおり、この法律には「財産的価値である仮想通貨の利用者を保護」をするためのルールが定められています。
同じブロックチェーン技術を使っているということから、NFTのビジネスをする企業は、この資金決済法の仮想通貨の定義と照らし合わせて、仮想通貨には該当していないことを確認しています。そうすることで、仮想通貨に定められたルールが自社には適用されないことを確かめているのです。
また、著作物であるコンテンツに紐付く保証書データであるNFTの場合、著作物の定義とルールを定めている著作権法を確認することも大切です。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。これに対してNFT自体は、著作物であるコンテンツに紐付く保証書データにすぎないため、著作物にはあたりません。ただし、NFTが紐付けられたコンテンツデータは著作物です。
そのため、NFTのビジネスをする企業は、NFTとそれが紐付けられたコンテンツデータを一体として捉えて、資金決済法にも増して、著作権法についてよく確認する必要があります。この著作権法の第1条では、以下のようにその目的が記載されています。
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
上記のとおり、この法律には、「文化的所産であるNFTが紐付けられたコンテンツデータの権利者を保護」するための取り扱いルールが定められています。
ここまでで説明してきたように、資金決済法と著作権法を比べてみると、仮想通貨は“財産的価値”であって、NFTが紐付けられたコンテンツデータは“文化的所産”であるという区別がつきます。
また、仮想通貨を対象としている資金決済法が“利用者を保護”するためのルールを定めているのに対して、NFTが紐付けられたコンテンツデータを対象としている著作権法は“権利者を保護”するためのルールを定めているという点も、大きな違いです。
ただし、上記の整理を踏まえても、コンテンツに紐付く保証書データとしてのNFT自体については、今なお法的な整理がされていない状況に変わりはありません。
NFT自体はこれまでも説明してきたように、何かを保証するための単なる技術的な手段にすぎません。そのため、そのただの技術的な手段自体は、資金決済法でいうところの財産的価値になることも、著作権法でいうところの文化的所産になることもありません。
結局は、NFTという手段を利用して、社会の誰のためにどんな役に立ちたいかという、その目的に尽きます。
投資家のために、NFTという手段を使って資産運用に役立つサービスを実現したいのであれば、そのサービスが生み出す財産的価値の利用者である投資家を保護するために、資金決済法に従ってビジネスをする必要があるでしょう。
また、コンテンツクリエイターのために、NFTという手段を使って創作活動に役立つサービスを実現したいのであれば、そのサービスが生み出す文化的所産の権利者であるコンテンツクリエイターを保護するために、著作権法に従ってビジネスをする必要があるでしょう。
一方、未整備ということではなく、NFTについて明らかに間違った法解釈がされていることもあります。
それは、一部のNFTのサービスで見られることがある、「購入するとNFTの所有権が得られる」という法解釈です。所有権について定めている民法85条では、所有権の対象となる「物」を以下のように明確に定義しています。
「この法律において『物』とは、有体物をいう」
無論NFTはご存じのとおり、有体物ではなく、データという無体物です。つまり、現時点で日本の法律では、NFTを購入しても、そのNFTというデータの所有権は認められていないのです。
NFTについて現時点では法解釈が未整理で、それ自体の法的な定義やルールはありません。そのため、「NFTという手段を何の目的に利用するか」によって、資金決済法や著作権法の定めにしっかりと従い、かつ民法などその他の法律についても、よく確認するようにしましょう。
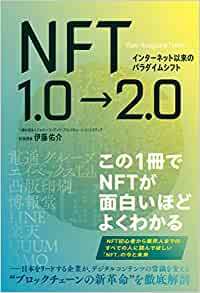
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
