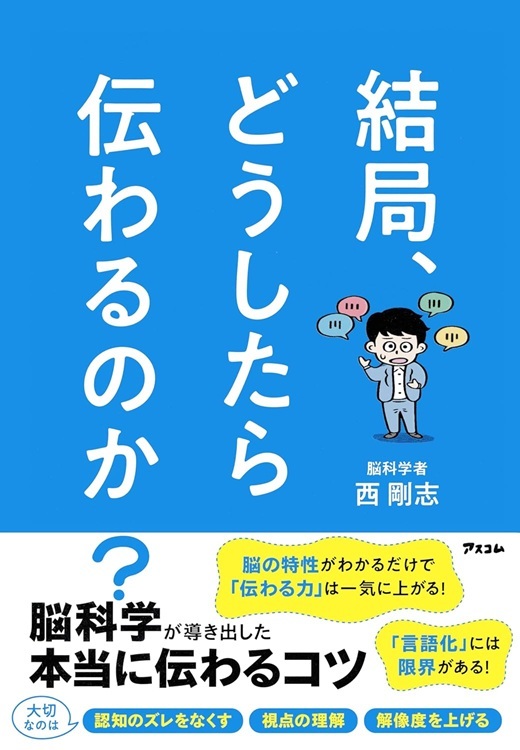本記事は、西剛志氏の著書『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。
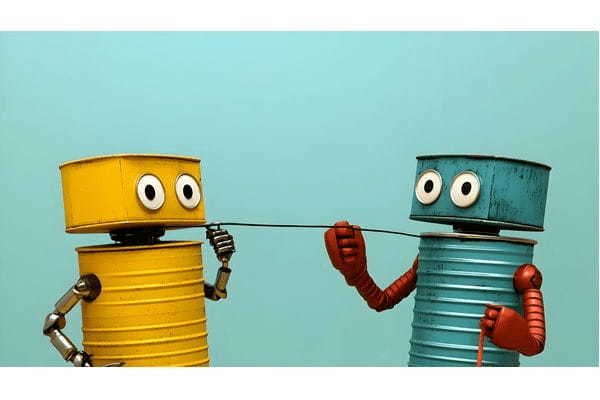
話すスピードで伝わり方が大きく変わる
いきなり結論ですが、話すスピードを合わせると、同じことを話していたとしても、相手に伝わりやすくなります。
たとえば、相手の顔が見えないコールセンターでは、「話すスピード」を活用しているそうです。
コールセンターには苦情の電話もよくかかってきますが、この苦情電話に対応するときに、話すスピードを合わせることはとても効果的です。
相手がすごい勢いで怒っているときに、コールセンターの窓口対応の人がゆっくりとした口調で「たいへん、もうしわけ、ございません」と応えたら、相手はさらに怒る可能性があります。これは想像してもらえたらわかるんじゃないでしょうか。話すスピードが違うと、相手はこちらを「敵」とみなす傾向があるのです。
なので、コールセンターでは相手のスピードに合わせて話すのが多いようです。
(早口で)「大変申し訳ございません。私たちの不手際でこういったところがあり、本当に申し訳ありませんでした」
とにかく最初は相手に合わせて早く話します。そこで相手にとってこちらは敵ではなく味方だと思ってもらいます。
次に話すスピードをだんだん遅くしていきます。そうすると、相手が今度はこちらの話すペースに合わせてくれるようになってきます。相手との間に信頼感が生まれるからです(これを同調といいます)。
そして、落ち着いたトーンで会話ができるようになっていきます。
この話すスピードはさまざまなことに活用できます。
以前、高い売り上げを上げている営業職と、売り上げがなかなか上がらない営業職の人を調べたことがあります。そのときに興味ぶかいことがわかりました。
それは、売り上げが高い営業職の人は、相手に合わせて話すスピードを変えていたのです。
実際に営業をしている最中の音声を録音させてもらい、どう違いがあるかを分析しました。すると、売り上げが上がらない人は自分のペースで話している人が多いということがわかりました。
一方で、売り上げが高い人は、人によって毎回話すスピードを変えている人が多かったのです。
そこで、成績が悪い営業職の人にも「相手のペースに合わせて話をするように心がけてください」とお願いして実践してもらったところ、驚くことにたったそれだけで10~20%も営業成績が上がりました。
話すペースをただ合わせただけで、です。
これならば、すぐにでも真似できますよね。
コミュニケーションでは、言葉(言語)以外の部分、いわゆる非言語の影響が大きく左右します。
上司と部下のコミュニケーションがうまくいってないと感じるならば、上司は部下の話すスピードに合わせて話をしてみてください。
夫婦関係や親子関係がうまくいってないと感じたならば、相手の話すペースを意識して、会話をしてみてください。
ここで少し話が脱線しますが、ちょっとした伝え方、話し方のコツで営業成績が上がる方法がほかにもあります。すべてエビデンスがある方法です。それをここで紹介します。
方法(1) 名前を呼ぶ
私も車や保険、金融商品などいろいろなトップ営業マンと会いましたが、商談で共通していたのが、相手の名前を呼ぶということでした。
「立ってください」といきなり言われると、エッ! と思うかもしれませんが、「西さん、立ってください」と言われると、立ってもいいかなと感じないでしょうか。名前を入れるだけで、印象が変わります。
これを「ネームコーリング効果」と呼んでいます。クレアモント大学の研究でも、初対面の男女を集めて15分間話してもらう実験をしたのですが、そのとき男性に協力してもらい、2つのパターンを試してみました。
① 女性の名前を呼ばないで会話する
② 女性の名前を呼んで会話する
すると、②の女性のほうが2倍以上も男性に対して「親しみやすい」「社交的」「もう一度会ってみたい」という印象を持ったのです。
私たちの脳は、名前を呼ばれると、自分のことを意識してくれている、大切に思われていると感じるため、相手に対して信頼感を感じます。
夫婦関係でも、長年連れ添っていくと、最初は奥さんを名前で呼んでいたのが、「おい」「お前」、もしくはそれすら呼ばなくなってしまうことがありますが、これは夫婦の信頼関係も損ねる恐ろしい行為だといえるでしょう。
信頼感は、製品のよさよりも商品の購入決定に2倍も影響するといわれています。営業職の人にとっては相手の名前を呼ぶことは必須のスキルだと思います。
方法(2) 複雑でなくシンプルに伝える
営業成績がよい人の特徴として、「わかりやすい言葉を使う」という共通点があります。
プリンストン大学の研究では、「長文で難しい表現」と「短くてやさしい表現」を使った場合に、文章の印象がどのように変わるかを調べました。
その結果、同じ内容でも、言葉がやさしくてシンプルなほうが、知的だと思われ評価が高くなりました。
私たちの脳には「利用可能性ヒューリスティック」という簡単なものを好むバイアスや、処理のしやすさを好む「流暢性の処理(認知容易性〈Processing fluency〉)」というバイアスがあります。
これらのバイアスは、理解しやすいほうを正しいとする脳のクセです。
難しい表現のほうが知的なイメージがありますが、そんなことはないのです。
たとえば、難しい表現で「私たちの体内に含まれるドコサヘキサエン酸の化学構造が、私たちの細胞膜の柔軟性のダイナミクスを可能にして、脳の高度認知機能が上がるのです」と伝えられるとどうでしょうか?
何を言っているかよくわかりませんよね。それよりも簡単な表現で「魚の油に含まれるDHAが、私たちの脳に作用して集中力や記憶力などを高めるのです」と伝えたほうが、よりスマートに感じるし、好感度も高く、伝わりやすくなります。
また脳のバイアスのひとつに「
言葉にはリズム感が大切といいますが、それは脳の特性だったのです。
CMやキャッチコピーでは下記のようによく使われている言葉です。
はやい、うまい、やすい
インテル、入ってる
やめられない、とまらない
セブンイレブン、いい気分
心に残る広告コピーも脳の特性を生かしているのです。
方法(3) マイナス面を伝えてから、プラス面を伝える
営業のシーンで、お客さんにいいところだけを見せようとすることは逆効果です。
ドイツの研究で、下記の3つのお店の広告を見せて、どのお店がよいか評価をしてもらいました。
- ① このお店はくつろげるお店です。
② このお店はくつろげますが、駐車場がありません。
③ このお店は狭いですが、リラックスしてくつろげるお店です。
その結果、最も評価が高かったのは、③の短所を伝えて、長所を最後に伝えるグループでした。
最初にデメリットを話すと正直な人と思われるためか、信頼感が上がります。そして、その後にメリットを伝えると、デメリットと比較されることで、よりメリットを受け入れやすくなるのです。
いいことばかり話す人はむしろ怪しまれがちです。両面を話すと「正直な人」と認知されて、「その人から買おう」という購買欲も上がることがわかっています。