本記事は、菊地 正俊氏の著書『アクティビストが日本株市場を大きく動かす 外国人投資家の思考法と儲け方』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

日本は株主権が強すぎるのか?
日本経済新聞は2024年12月に「資本騒乱 膨張アクティビスト」との特集記事を連載しましたが、どちらかといえば、アクティビストに対してネガティブな内容でした。その12月2日の記事では、「気がつけば『ファンド天国』」だとし、日本は他国より株主の権利が強いと指摘しました。アクティビストから企業を守る立場にある西村あさひ法律事務所の太田洋弁護士も、2023年5月に上梓した『敵対的買収とアクティビスト』で、「わが国では、米国やドイツと異なり、少数株主権が非常に強い」という問題を指摘しました。
東証が2018年10月に株式取引における最低売買単位(単元株式数)を100株に統一したことで、株主提案を行なうためには、議決権の1%か300個以上の議決権を6カ月間保有すればよいことになりました。提案数も株主1人当たり10個までできます。一方、米国では株主提案を行なうためには、1~3年以上の保有が必要で、提案数も1株に1個に制限されています。欧州では株主提案に議決権の5%以上の保有が求められています。また、臨時株主総会の招集請求権の行使要件も、日本は議決権の3%以上の株式を6カ月間保有すればよいとされています。米国では多くの企業が本社を置くデラウェア州の法律で、会社は定款で臨時株主総会の招集請求権を制限できます。英国では臨時株主総会の招集を求めるのに議決権の10%以上の保有が必要とされています。
以前から電力会社に対する個人株主による環境関連の株主提案が多く出されていましたが、NTTでは2023年6月末に1:25の株式分割を行ない、投資単位が大幅に下がったこともあり、2024年6月の株主総会では個人株主から取締役1名の選任提案がありました(賛成率5.4%で否決)。アクティビストに否定的な見方をする専門家からは、会社法を改正して、株主権を制限すべきとの意見が出ています。
ただ、日本ではまだ株式持合が依然多く、株主提案が成立することもめったにないため、実質的な株主権が強いかどうかは議論の余地があるでしょう。
アクティビストに大きな影響を与えるスチュワードシップ・コード改訂の議論
2025年2月に金融庁でスチュワードシップ・コードに関する有識者会議が開かれ、スチュワードシップ・コード(SSC)改訂の最終案が提示されました。実質株主を判明しやすくするために、欧州式の導入が予定されています。大量保有報告書を出さなければいけない5%までは、投資先企業に知られずに株を集めたいと考えるアクティビストが少なくありません。
現行のスチュワードシップ・コードは指針4-1で、「株式保有の多寡にかかわらず、機関投資家と投資先企業との間で建設的な対話が行なわれるべきであるが、機関投資家が投資先企業との間で対話を行なうに当たっては、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて、企業に対して説明することが望ましい場合もある」としていますが、改訂案では指針4-2として、「機関投資家は、投資先企業との間で建設的に対話を行なうために、投資先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべき」を新たな指針として追加する案が議論されました。
投資家サイドの有識者からは、①日次で保有比率の開示を求められても対応できないので、月末値などの開示にせざるを得ない、②アセットオーナーとの契約上、保有比率を開示できないケースもあるので、その場合は〝Comply or Explain〟を適用し、遵守しない理由の説明が許されるべき、③保有比率の開示のためのシステム対応に多大なコストがかかる可能性があるなどの課題が表明されました。一方、事業会社サイドの有識者からは、SSCに署名していない海外投資家は規制対象外となるが、できるだけ実質株主判明に海外投資家が含まれるような制度設計にすべきだとの指摘がありました。今回はスチュワードシップ・コード改訂によるソフトローでの対応になりますが、将来的には会社法改正による義務付けが検討されています。
日本でも協働エンゲージメントは普及するか?
日本がスチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードを輸入した英国では、複数の機関投資家が共同で企業と対話する協働エンゲージメント(英語で〝Collective Engagement〟)が盛んに行なわれていますが、日本では大量保有報告制度の重要提案行為や共同保有報告書の問題があるため、協働エンゲージメントがやりにくい面がありました。しかし、2024年5月の金融商品取引法改正によって、複数の投資家が「経営に重大な影響を与えるような合意」を行なわない限り、大量保有報告制度の「共同保有者」に該当しないことが明確化されました。金融商品取引法改正の詳細は、金融庁の省令で規定されるため、その公表を待っている段階にあります。
配当方針や資本政策の変更といった、企業支配権に直接関係しない提案を共同して行なう場合等は、共同保有者として大量保有報告書を提出しなくてもよくなる予定です。現行スチュワードシップ・コードは指針4-4で、「機関投資家が投資先企業との間で対話を行なうに当たっては、単独でこうした対話を行なうほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行なうこと(協働エンゲージメント)が有益な場合もあり得る」としていますが、これを「機関投資家が投資先企業との間で対話を行なうに当たっては、単独でこうした対話を行なうほか、他の機関投資家と協働して対話を行なうこと(協働エンゲージメント)も重要な選択肢である。対話のあり方を検討する際には、投資先企業の持続的成長に資する建設的な対話となるかを念頭に置くべきである」と改訂する案が示されました。
金融庁の有識者会議では、投資家サイドの有識者から、協働エンゲージメントは政府によって促進されるべきではなく、運用会社自らの選択肢の1つの扱いでよいのではないかとの指摘がありました。一方、事業会社サイドの有識者からは、協働エンゲージメントで企業への圧力が高まったり、「ウルフパック」が行なわれたりする可能性があるので、金融庁に相談窓口を設けたらどうか、金融庁の大量保有報告違反のエンフォースメント(法執行)も弱いとの指摘がありました。ウルフパックとは、複数のアクティビストがひそかに協調して、株式の買い集めなどを行ない、時期を見て、対象企業に対して共同して要求を突きつける行為をいいます。アクティビストが活発な米国で、「ウルフパック」はネガティブな意味で使われることが多くなっています。
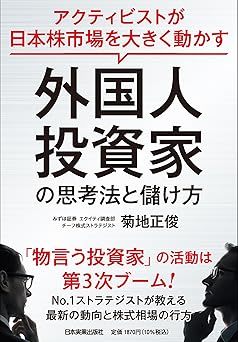
著書に『低PBR株の逆襲』『米国株投資の儲け方と発想法』『相場を大きく動かす「株価指数」の読み方・儲け方』、『日本株を動かす外国人投資家の思考法と投資戦略』(日本実業出版社)、『アクティビストの正体』(中央経済社)、『良い株主 悪い株主』(日本経済新聞出版社)などがある。
金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け
厳選された有料記事を月3本までお試しできます
