生命保険業界を巡る経済環境
◆国内金利
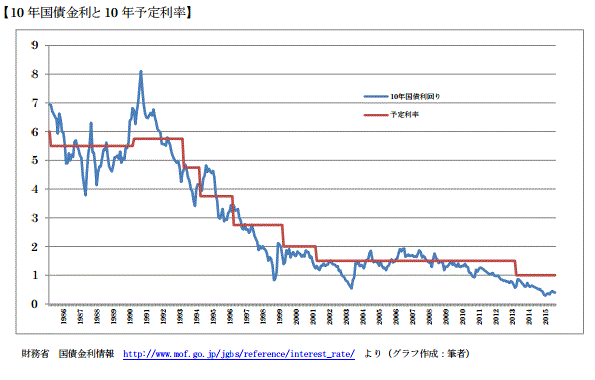
上のグラフは10年国債の流通利回りの推移を示したものだが、今の金利状況からみると、1980年代以前には、6~8%という高い利回りがあったことに今さらながら驚く。
その当時は、保険の教科書通りに、予定利率は金利状況と長期性を考慮して安全に決めるということが可能であった。そして、実際の運用が予定利率を上回ることが当たり前であり、そのかなりの部分が毎年の配当金という形で顧客に還元されていた。そして多額の配当金(の予想)は募集の際に、一定の説明ルールの下で、大きなアピールポイントとなっていた。
その後、どんどん金利は下がっていく。4%とか2%になっても、当時はそれを「超低金利」と表現し、いくらなんでも、そろそろ上がるだろう、と思っているうちに、今では1%をも切って久しい。
この間、予定利率のほうも、当然のことではあるが、グラフに示すように引き下げられてきた。ただこれは、その時点の新規契約から引き下げる、ということであって、既存契約の高い予定利率を引き下げるわけではない。それが10~30年など相当長期間続くわけである。
すると例えば「20年前の予定利率4.75%の契約が今も継続していて、それに対して1%以下の資産運用しかできていない」という状況もありうる。もちろん、資産側も同様で「今金利は1%を切っているが、10年前の債券を保有しているので、そこから2%稼げる」など逆もあり、その総体の比較で利差益か逆ざやとなる。
今、生命保険各社が「逆ざやが解消」と言うのは、会社全体の話であってそれはそれで喜ばしいのだが、個々の契約をみると、「長期継続契約の逆ざや」「新しい契約の利差益」などが混在しているはずであろう。こうした契約者間の格差は、配当金に差をつけることで解消されればいいのだが、実際には配当金がほぼないため、調整できないのが実情と思われる。
ところで、資産運用側は、運用しようとしている資金が、どんな特性のものか把握し意識しているのだろうか?おそらく、1980年代前半までは、はっきりとは意識していなかったのではあるまいか。というより、金利と予定利率の差に余裕があり、次に述べるように株価も右肩上がりであるなど、収支上の問題も少なく、把握する必要もなかったのではないか。
その後状況はシビアになり、
・区分経理(何らかの特性の異なる保険種類は、収支も区分して管理することで、料率や配当もそれぞれに応じて設定でき、説明も明確になる仕組)の導入、
・ALM(予定利率や保険期間、貯蓄性の有無、保険料の払い方など負債の特性に応じて、資産運用方針を決定するなどの経営手法)の進展
・ディスクロージャー上の要請などにより、相当高度に、負債特性を意識した資産運用がなされているものと思われる。