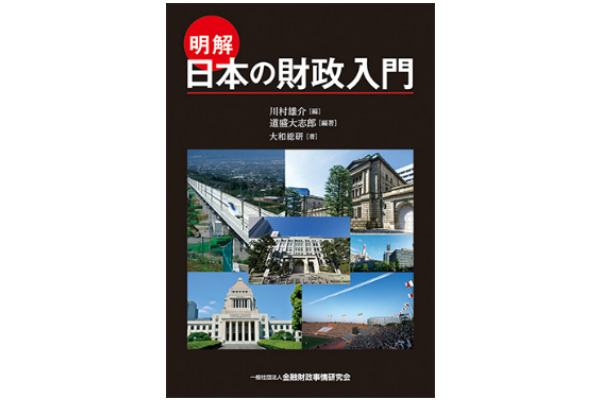さまざまなサービスを国民に提供するために、政府は多くのお金を必要とする。その資金はどう調達されているのだろうか。いうまでもなく、最も基本的な調達方法は、私たち国民に対する課税である。なかでも、身近な税金である所得税は、税収全体の約3割を占める。
(本記事は、道盛 大志郎 著,編集, 大和総研 著, 川村 雄介 編集『明解 日本の財政入門』きんざい 2016/10/4 の中から一部を抜粋・編集しています)
税額の計算方法5つのステップ
所得税は、1月1日~12月31日の1年間に得た個人の所得に課される税である。所得は、収入から必要経費を差し引いて計算される。所得はその源泉や性質によって税を負担する能力(担税力)が異なることから、給与所得、事業所得、譲渡所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、退職所得、山林所得、雑所得の10種類に分類される。
原則として、それぞれの分類ごとに計算された所得金額の合計額に税率を乗ずることで税額を計算するが、この課税方法を総合課税という。一部の所得は、他の所得と合算しない分離課税が適用される。
総合課税の税率は、所得が高いほど高くなる超過累進税率が適用されており、現在は5~45%の7段階に設定されている。超過累進税率とは、一定の所得金額を超えると、その超えた部分について高い税率を適用するものである。
たとえば、100万円の所得で税率が10%、200万円の所得で税率が20%という超過累進税率が設定されていると仮定すると、所得が300万円のケースでは、最初の100万円分に10%、100万円を超えた200万円分に20%が適用されて、税額は50万円( = 100×1 0%+(300 -100)×2 0%)になる。
税額の計算方法は5段階に分かれる。まず、第1段階として個人が得た1年間の収入を給与、事業、利子、配当などの性質に応じて10種類に分類する。
第2段階では所得の分類ごとに収入から必要経費を差し引いて所得金額を算出する。必要経費の計算方法は所得によって異なり、事業所得のように実額を経費にするケースがある一方、給与所得のように実額ではなく経費相当額を給与所得控除という概算で求めるケースもある。
第3段階では計算した所得を合算し、そこから所得控除を行って課税所得を算出する。所得控除とは、納税者の家族構成、社会保険料や医療費の支出などの個々の事情を考慮して、一定の金額を所得から差し引き、課税されるベースを調整するものである。具体的にはすべての納税者に適用される基礎控除のほか、所得のない配偶者がいる場合に適用される配偶者控除など14種類の所得控除がある。
第4段階では課税所得に超過累進税率を乗じて、税額を算出する。納税者の負担能力を考慮した税率構造となっており、所得税には所得を再分配する機能が備えられている。また、景気がよくなって給料が増えると負担率が高まり、不景気で給料が下がると負担率が下がるということを通じて、景気の変動を自動的に小さくする役目も所得税は果たしている。
最後に、第5段階として、計算した税額から税額控除を行う。税額控除には配当控除のように法人税と所得税との二重課税の調整を目的とするものや、住宅ローンの残高に応じた税額控除のように特定の政策目的をもったものがある。
配偶者控除はどう見直す?
これからの所得税制について、現在、税制調査会など政府のなかでは、結婚して子どもを産み育てようと希望している若年層や、もっと働きたいと考えている低所得者層により配慮すべきではないかという視点から議論が進められている。また、ライフスタイルの多様化に伴い、働き方の違いによって不利にならない中立性の確保も課題である。
大きな方向性としては、若い世代が自らのニーズに応じて働くことができ、希望すれば結婚ができ、子どもを産み育てられる生活基盤を確保していくということである。これまでの税制はどちらかといえば高齢世代を弱者ととらえたものであったが、これからは年齢ではなく負担能力をふまえて再分配機能を再構築していくということになるだろう。
特に注目されるのは、中立的な税制を構築するために配偶者控除をどう見直すかである。配偶者控除とは、納税者に所得の少ない配偶者がいる場合、38万円の所得控除を受けるものである。配偶者控除を受けられるのは、配偶者の所得が38万円(パートの場合、給与所得控除65万円とあわせて収入が103万円)以下の場合である。この場合、配偶者自身も自身の基礎控除が38万円あるため、課税されない。
配偶者控除に対しては、配偶者の収入が103万円を超えると納税者本人が配偶者控除を受けられなくなったり(配偶者特別控除という別途の控除を受けられる場合はある)、勤め先からの家族手当が支給されなくなったりするため、配偶者が就労を抑制する要因になっているという指摘がある(2017年の税制関連法改正により、2018年からは配偶者控除を受けられる給与収入の額が「150万円以下」に引き上げられる)。
今後の見直しの選択肢としては、配偶者控除を廃止する案や、配偶者控除にかえて配偶者自身が控除しきれなかった基礎控除を納税者本人に移転できるようにする案、個人ではなく夫婦世帯を対象とする新たな控除を導入する案などがある。
老後の生活に備えるためには自助努力が必要性
もう1つの注目点は、公的年金の給付水準が中長期的に抑制されていく見込みとなっているなかで、老後の生活に備えるための自助努力を税制で支援する必要性である。現在、個人に対して老後のための貯蓄を税制で奨励している制度としては、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)や確定拠出年金などがある。ただ、これらは利用に年齢制限があり、また資金の引出しの際の目的や年齢に制限がある。
この点、既存の制度で注目したいのは、上場株式、公募株式投信、上場ETFなどの譲渡所得と配当所得が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)である。NISAは20歳以上であればだれでも活用でき(0~19歳を対象としたジュニアNISAもある)、資金の引出しに制限がないため、他の制度よりも使い勝手がよい。
さらに、2018年1月からは、非課税で運用できる期間を20年に延長する「積立NISA」が創設される。NISAを恒久的な制度としたうえで、もっと使い勝手のよいものとしていくことが、老後に備えた自助努力を促すうえで必要ではないだろうか。
神尾 篤史 大和総研パブリック・ポリシー・チーム研究員
2006年立教大学大学院経済学研究科博士前期課程修了、大和総研入社。財務省国際局出向(2010~12年)、金融・資本市場調査担当などを経て2015年より現職。2013年立教大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学、2013~15年立教大学兼任講師。
【編集部のオススメ記事】
・「信用経済」という新たな尺度 あなたの信用力はどれくらい?(PR)
・資産2億円超の億り人が明かす「伸びない投資家」の特徴とは?
・会社で「食事」を手間なく、おいしく出す方法(PR)
・年収で選ぶ「住まい」 気をつけたい5つのポイント
・元野村證券「伝説の営業マン」が明かす 「富裕層開拓」3つの極意(PR)