(本記事は、山田英夫氏、手嶋友希氏の著書『本業転換――既存事業に縛られた会社に未来はあるか』KADOKAWAの中から一部を抜粋・編集しています)

本業転換の難しさ―― 第一歩を遅らせる5つの理由
化粧品のDHCの前身が、大学翻訳センターという翻訳会社だったり、豪華な付録で有名な女性誌の出版元である宝島社の前身が、地方公共団体向けコンサルティング会社であったり、有名なスポーツ選手を広告に使った寝具のエアウィーヴの前身が、プラスチック射出成型機メーカーだったことを知る人は、多くはないだろう。
これらは、創業期の事業を規模が小さいうちに捨て、全く別の事業で成長してきた企業例と言えよう。
しかし、本業を拡大して大企業になった後に、その本業が衰退したために、本業を別の分野に転換させることは、新興企業の本業転換に比べて、桁違いに難しい。それには以下の5つの理由があるからである。
第1に、本業のライフサイクルが、いつ衰退期を迎えるかを予測することが難しい。本業が今、ライフサイクルのどの位置にあるかを正確に知ることはできない。製品・事業のライフサイクルは、導入期、成長期、成熟期、衰退期という段階を経るが、今行っている事業がどの時期に位置しているかは、正確にはわからない。正確に測ろうとすれば、その製品・事業が消滅した時に、後戻り的に、どの時期がどの段階であったかがわかるものである※1 。
例えば日本におけるウイスキーは、2008年頃までは毎年消費量が減り続けており、業界では成熟期だと思われていた。しかし、2009年に缶入りハイボールが発売されてからV字回復し、その結果、原酒が足りなくなる事態となった。ウイスキーは成熟期ではなかったのである。
第2に、衰退期を認識できないもう1つの理由として、「衰退は一気に生じるものではなく、波動をもって忍び寄る」※2 からである。そのため社内では、「まだ行けるはず」「ここさえ凌(しの)げば」という考えが強くなり、衰退の認識の遅れが生じる。
第3に、新興企業の場合には、創業期の事業に将来性がないと思えば、それを捨てて、新たな事業や新しいビジネスモデルに転換することが、比較的容易にできる。しかし、大企業で長年行ってきた事業の場合には、現実に大きな売上が立っており、固定客がついており、また従業員の雇用やステークホルダーに対する社会的責任もあり、簡単には撤退できない。事業規模が大きくなればなるほど、撤退することの社会的影響も考慮しなくてはならない。
例えばスイスのエレベーター会社シンドラーは、事故が多発したこともあり、日本から撤退を決めたが、彼らの保守事業は米国オーチスの日本法人に委ねることになった。外資といえども大企業になれば、簡単には撤退できないのである(エレベーターは、保守を法律で義務づけられているという理由もあるが)。
第4に衰退事業であっても、競合企業が先に撤退することによって、結果的に残存利益を得られる可能性もある。そのため、最後の1社を目指して頑張るというスタンスになりやすい。例えばレコード生産の川上から川下までの全工程を行える企業は、日本には東洋化成1社しかなくなったが、ハイレゾ音域が記録されているレコードが突如再ブームとなり、東洋化成は残存利益を享受している。
第5に大企業では、事業を評価する明示的・暗示的な尺度が形成され、その尺度に合う事業は温存され、資源が投入されやすい。逆にその尺度に合わない事業は、なかなか社内で正当な評価を受けにくい。本業で使われていた尺度が、企業全体を支配しているケースが少なくない。
例えば、かつて鉄鋼会社のほとんどが半導体事業に手を出したが、鉄鋼事業の評価尺度は「トン」であり、半導体は「グラム」である。「トン」の企業風土が根づいている鉄鋼会社内で、「グラム」の事業がいくら頑張っても、「トン」に近づくことは難しい。
また死亡保険金の大小で評価される大手生保が、死亡保険金が少ないガン保険になかなか力を入れられなかったのも、評価尺度が影響していたと言えよう。

そもそも「本業」とは何なのか
「本業」という言葉は、極めて日本人好みの言葉でもある。GEや3Mの社長に向かって、「貴社の本業は何ですか」と質問しても、質問されたほうが当惑してしまうだろう。
米国企業では事業の売買は日常的であり、事業単位も売買されやすいように自己完結しているケースが多い。親会社は持株会社の形態をとり、事業を組み換えながら成長していく企業も多く、新聞の証券欄を見ても、会社は業種別に分かれておらず、社名のアルファベット順に並んでいる。
翻(ひるがえ)って日本では、「本業」という言葉は今でもよく使われる。本書で取り上げた富士フイルムの〝本業喪失〞は、社会的にも大きなニュースとなった※3 。
また日本では、主たる事業の売上構成比が変わると、証券の業種カテゴリーを移動することになる。ちなみに東京証券取引所のルールとしては、
①現在の主要業務に係る売上高が、現に所属する業種に係る売上高の2倍以上 ②それが2年間連続している
場合に、所属業種の変更が行われる(M&Aなどで事業内容が大きく変わった場合は、2年未満でも変更がありうる)。
古くは、HOYAが「ガラス・土石」から「精密機械」に、旭化成やクラレが「繊維」から「化学」に、ダイワボウホールディングスはダイワボウ情報システムの完全子会社化に伴い、「繊維」から「卸売業」に変更した。またソフトバンクは2006年に、「卸売業」から「情報・通信業」に変更した。
本書で取り上げる日清紡ホールディングスは、2015年にエレクトロニクス事業の売上の拡大に伴い、「繊維」から「電気機器」に変更している。
以上のように「本業の転換」は注目されやすいが、本業という言葉は、学術的には定義されていない言葉である。
分野は異なるが、財務会計上、本業とは、「会社の定款に事業目的として記載されている事業」と定義されている。しかし定款に事業目的と記載されていない事業であっても、それを本業として行っているという意志に基づく限りは、会計学においては、本業と判断している。
また会計的には、企業が本業で稼いだ利益を営業利益と呼んでおり、本業以外の財務活動などによる収益・費用も反映させたものが経常利益である。
このように会計上の定義はあるが、本書では、定款にどのように記載されているかではなく、企業内での相対的な位置づけを重視し、「売上高の50%以上を占めるセグメント」を、本業と呼ぶことにする。
※1 山田英夫(2019)『ビジネス・フレームワークの落とし穴』を参照 ※2 加護野忠男(1989)「成熟企業の経営戦略」 ※3 例えば『週刊東洋経済』2014年4月19日号では、「本業消失」という特集で、富士フイルムの事例を取り上げている
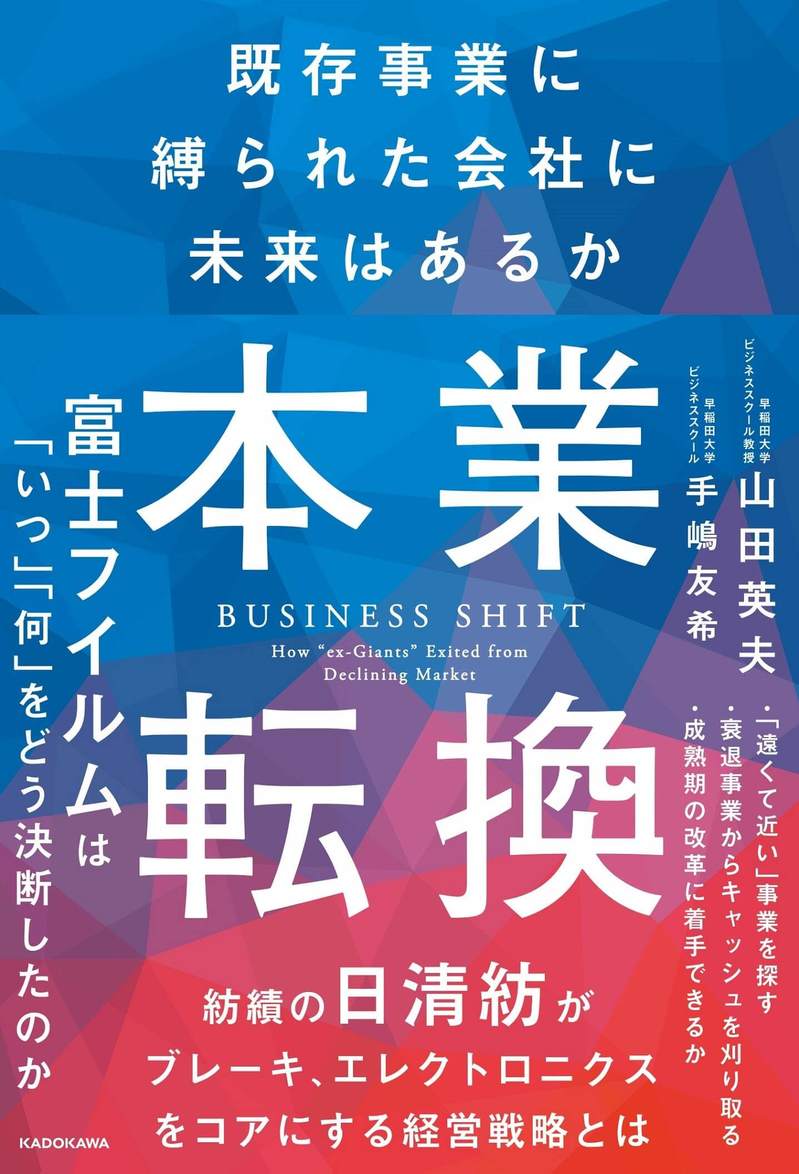
※画像をクリックするとAmazonに飛びます