(本記事は、山田英夫氏、手嶋友希氏の著書『本業転換――既存事業に縛られた会社に未来はあるか』KADOKAWAの中から一部を抜粋・編集しています)

「成熟・衰退→多角化→転換」の先行研究
中小企業の会社の平均寿命は、大企業に比べて短いが、逆に極めて長寿の企業もある。帝国データバンクの2019年の調査によると、創業100年以上の長寿企業は日本に約3万3000社あり、その4割は年商1億円未満の小企業である※1 。
一方大企業で上場企業の場合には、株主からの期待に応えるためにも、売上は横ばいではなく、持続的成長を果たさなくてはならない。
しかし事業にはライフサイクルがあり、いつかは成熟期から衰退期を迎える。そのため大企業が永続していくためには、事業構造を変えていく必要がある。
本業が成熟・衰退した場合、企業は2つの手を打たなくてはならない。それは、成熟・衰退した本業からキャッシュを刈り取る作業と、次世代の成長のための新事業の開発である。
そのために具体的には、
①成熟・衰退した事業から、新事業への投資のために、いかにキャッシュを刈り取るか ②どのような事業に転換していくべきか ③どのように新事業に転換していくべきか
の3つが必要である。
本業転換を考える上で、この3つの切り口から先行研究を確認しておこう。以下では、①②③の順に主な研究成果を、(1)代表的な理論研究、(2)日本企業の調査・研究の順に見ていく。
1. 成熟・衰退した本業をどうするか
(1)衰退業界の競争戦略
衰退した事業への対応に関しては、マイケル・ポーター(1980)が衰退事業における戦略定石を示している。それは、リーダーシップ戦略、拠点確保戦略、刈り取り戦略、即時撤退戦略の4つである。

リーダーシップ戦略は、自社を業界で唯一の生き残り企業、あるいは数少ない生き残り企業の1つにすることである。リーダーシップ戦略のためには、積極的なマーケティング投資により、他社を当該市場からおろす、競合を買収する、競合の設備を買い取る、競合へOEM供給するなどの戦術が有効である。
例えば、競合他社にOEM供給することによって、競合企業が当該製品の生産から撤退していくことは、成熟産業ではよく見られる方法である(日本では、軽自動車や銀塩フィルム時代のレンズシャッター・カメラにおいてよく見られた)。
拠点確保戦略は、衰退業界のセグメントの中で、需要が安定しており、衰退がゆるやかで、その上、高い利益率を生み出すセグメントを識別し、そのセグメントで地位を築くことである。拠点確保戦略のためには、高い利益率を生めるセグメントを見定めることが何より重要であり、その上で、そのセグメントに対してリーダーシップ戦略をとることである。
刈り取り戦略は、事業から回収する現金を最大にしようとするものであり、最後には、事業を売却するか、清算することになる。刈り取り戦略のためには、製品数(SKU)を減らす、取引する流通業者数を減らす、小口の顧客を切る、サービス水準を下げるなどの戦術がある。ただし顧客の反発を招かないことが重要である。
即時撤退戦略は、衰退期に入ったら早めに売却することである。一般に、早めに事業を売却すれば、遅く売却するより事業価値は高めに評価されるからである。衰退期に入る前の成熟期に売却できれば、売却価格を高くすることもできる(ただし早めの売却には、将来予測を誤るリスクもある)。
(2)日本企業の調査
日本企業の本業に着目した調査が、「会社の寿命」の調査であった。
1983年に、『日経ビジネス』による定量調査から「会社の寿命は30年」※2 が提示された。これは大企業といえども、企業には寿命があることを初めて示した調査である。
この調査は、明治29年(1896)、44年(1911)を総資産額で、大正12年(1923)、昭和8年(1933)、18年(1943)、25 年(1950)、35年(1960)、47年(1972)、57年(1982)を売上高で見た場合の、日本のトップ100社を抽出したものである。
この9期間、連続して上位100社に名前を連ねたのは王子製紙ただ1社であり、上位100社に名前を連ねられる期間は平均2.5回、すなわち1期10年とすると、「1つの会社はたかだか30年間しか繁栄のピークを極めることはできない」という事実を見出した(あくまで日本の上場企業を売上高の大きさ順に並べたものであり、赤字、黒字などの利益は考慮されていない)。これが「会社の寿命は30年」と呼ばれる調査の概要である。ちなみに総資産額だけで9期を見ると、本書で取り上げるカネボウに加えて小野田セメントも、王子製紙と並んで上位100位を維持していた。
同調査では、「一業にこだわる企業に明日はない」と提言し、何もしないと本業の衰退とともに企業も死を迎えてしまうため、本業の需要がある間に、変身の種を蒔(ま)くことの重要性を指摘した。
2. どのような事業に転換すべきか
(1)ルメルトの多角化研究
新しい事業への転換に関しては、ルメルト(1974)が行った『多角化戦略と経済成果』が代表的研究と言える。主力事業が成熟してきた場合、多くの企業は新しい成長分野へと進出して生き残りを模索する。その選択肢の1つが、多角化である。
研究は、1949年、1959年、1969年の3時点に関して行われた。1949年は総資産額、1959年と1969年は売上高による「フォーチュン500社」内の全米上位100社を対象とし、3期を通じて上位100社に入った246社をサンプルとした。
ちなみに調査時点における「フォーチュン500社」には、米国に拠点を置き、収益の50%以上を製造業か鉱業から挙げており、財務諸表を公開している企業が掲載されている(すなわち、製造業を対象としたランキングである)。
ルメルトの研究の結論は、以下のようなものである。
- 多角化の程度の高い企業のほうが、そうでない企業よりも成長性は高い
- 技術的に関連の薄い分野や関連のない分野に進出するよりも、本業に近い関連多角化のほうが業績が良い
- 最も業績が良かったのは「本業集約型」企業と「関連集約型」企業
- 最も業績が悪かったのは「非関連・受動型」企業
その後、本業と多角化事業との関連ではなく、本業に根差している「ドミナント・ロジック」(事業を概念化する方法や、重要な資源配分の意思決定を行う際の指針)の硬直性が、多角化の成否に関係しているという研究も提唱された(プラハラッド&ベティス 1986)。
彼らによれば、ドミナント・ロジックが新しい事業と整合しない時には、パフォーマンスは高くならない(彼らの考え方は、保有する経営資源が鍵となるリソース・ベースド・ビューの考え方に近いと言えよう)。
ルメルトは、進出した市場の関連性など、外部要因との関係を中心に多角化の成否をとらえてきたが、プラハラッドらは、組織内の資源要因から多角化の成否を説明した。
強(し)いて言えば、市場関連多角化を説明する時は前者の考え方が、技術関連多角化を説明する場合には、後者の考え方がわかりやすいと言えよう。
(2)日本企業の多角化研究
多角化に関して、ルメルトと同じ方法で日本企業を調査したものが、吉原英樹他(1981)の『日本企業の多角化戦略』である。
研究の対象としたのは日本の大企業(鉱工業/筆者注:一部上場の製造業とほぼ同じ)118社の、1958年から1973年までの15年間である。すなわち、第1次オイルショック以前の高度成長期が、調査対象期間であった。
118社の多角化とパフォーマンスを調査した結果、次のような結論が示された。
- 日本企業の多角化の程度は、海外企業と比べて低い
- 日本企業の多角化は、関連多角化が多い
- 成長性と収益性にはトレードオフがある
- 成長性に関しては、高度な多角化のほうが業績が良い
- 収益性については、中程度の多角化のほうが業績が優れている

この研究のユニークな点としては、成長性に関しては、高度な多角化のほうが良いが、収益性に関しては、中程度の多角化が良いという発見であった(図表参照)。
3. どのように新事業に転換していくべきか
(1)両利きの経営
ベンチャー企業の創業であれば、新規事業開発だけで十分であるが、大企業が本業転換をするためには、衰退期にある本業を維持しながら、新事業の模索を行わなくてはならない。
こうした観点からなされた研究として、オライリーとタッシュマン(2016)の『両利きの経営』が挙げられる。彼らは、本業に必要なのは「深化」(exploitation)の力、一方、新事業に必要なのは「探索」(exploration)の力であると述べ、両者は全く違う能力であると述べた。
一般に企業は成功すればするほど、「深化」に傾きやすい。成熟期〜衰退期に入った本業には、深掘りし、利益を確保していく「深化」が必要なのに対して、新事業は不確実性が高く、コストとリスクを伴う「探索」が必要である。
本業転換を果たすためには、「深化」と「探索」の両方を高いレベルで行う「両利きの経営」(ambidexterity)が必要であると提唱した※3 。
彼らの研究では、「両利きの経営」で成功した企業として、米国IBM、米国USAトゥデイ、英国ブリティッシュ・テレコム、中国ハイアール、日本では富士フイルムなどを例に挙げている。
(2)日本企業の効率と創造
「会社の寿命」の2年後に行われた「診断 会社の寿命」※4 の調査からは、「社員30歳、本業7割」という仮説が提示された。これは、本業比率が7割以上で、従業員の平均年齢が30歳を上回った場合、企業は成長率を鈍化させていくというものである。
具体的には、昭和30年(1955)以降、3年ごとの売上構成比、従業員の平均年齢などをもとに、売上高上位100位のランキングを作成し、その中でのランクの上がり下がりを調べた。その結果、ランク下降組の43社の98%が平均年齢が30歳以上であり、かつ多角化のウエイトの低い企業が60%近くになっていた。そして平均年齢が30歳を超えた頃から、急速に売上の伸びを鈍らせていた。
実は本業比率と平均年齢の2つの指標には、相関がある。多角化が上手くいった企業は、新事業部門に若い従業員を採用するため、平均年齢の上昇をとどめることができる。従って、企業がコントロールできるのは本業比率のほうであり、平均年齢はそれに伴って変化する変数と言えよう。
ある段階で成功すればするほど、次の段階への転換は難しくなる。「こうすれば成功するのだ」という信念や風土が組織の中に固定化され、次の段階に必要な考え方を取り込む姿勢が失われるからである※5 。
一般に組織は「成長」→「優位性」→「効率」の段階を経て、老化していく。そして、「『効率』から『創造』への再転換は困難であるのみならず、多くのリスクを伴う。効率を求める組織は、イノベーションを抑圧する傾向が強いからである」※6 と述べられている。
こうした考え方は、後のクリステンセン(1997)の『イノベーションのジレンマ』 でも述べられており、1世代前の技術のリーダー企業になればなるほど、漸進(ぜんしん)的な改良に目が行き、大きな技術革新は、1世代前にリーダーでなかった企業のほうが進めやすいと論じている。
本業だけに頼っている大企業は長期的な発展は難しく、本業の成熟とともに、本業自体を転換させていくことが求められていると言えよう。
※1 帝国データバンク『「老舗企業」の実態調査(2019年)』2019年1月8日 ※2 「企業は永遠か」『日経ビジネス』1983年9月19日号、および日経ビジネス編(1984)『会社の寿命』を参照 ※3 なお、このことは(2)で述べる『続 会社の寿命』(1985)において、「効率とイノベーションという一見相矛盾した目標を同時に達成しなくてはならない」と既に述べられている ※4 「診断 会社の寿命」『日経ビジネス』1985年1月7日号、および日経ビジネス編(1985)『続 会社の寿命』日本経済新聞社を参照 ※5 日経ビジネス編(1985)『続 会社の寿命』日本経済新聞社 ※6 前掲書
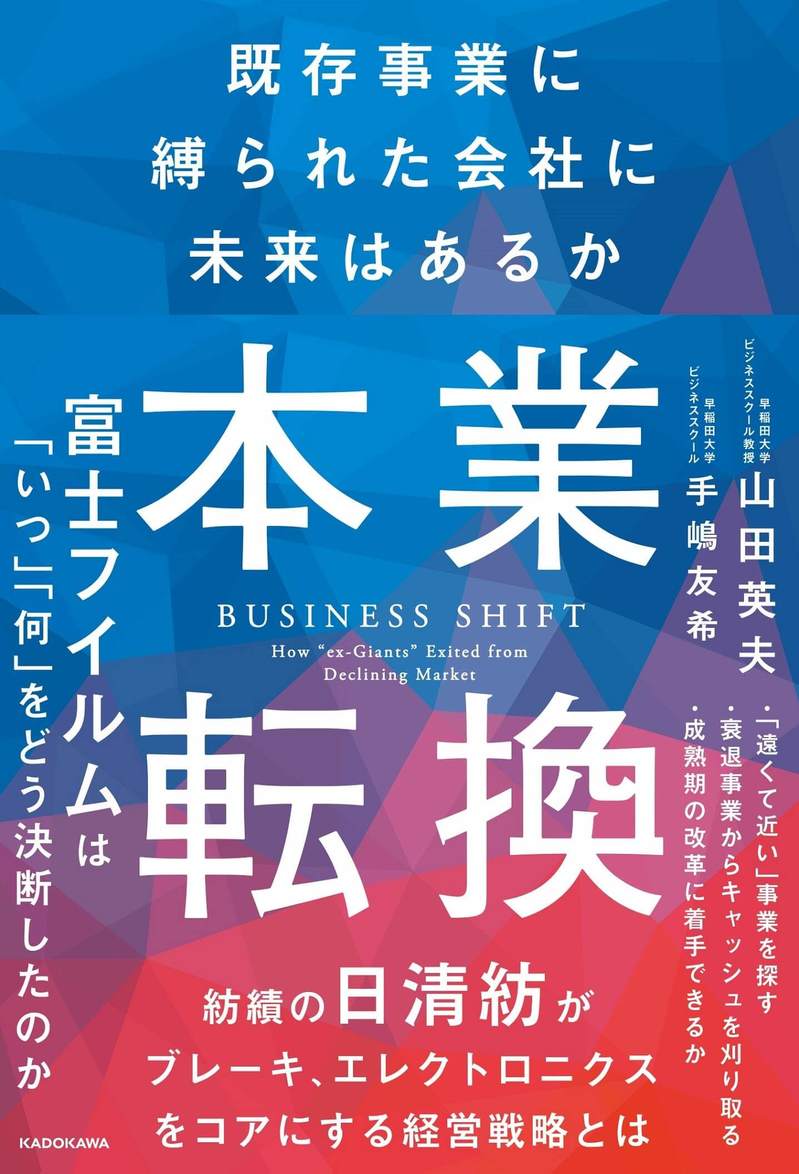
※画像をクリックするとAmazonに飛びます