(本記事は、山田英夫氏、手嶋友希氏の著書『本業転換――既存事業に縛られた会社に未来はあるか』KADOKAWAの中から一部を抜粋・編集しています)

日清紡【地道な多角化の歩み】
(1)日清紡の誕生
1907年、根津財閥(後の芙蓉グループ)によって高級綿糸の生産を行う紡績会社として、日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社。以下、日清紡)が設立された。海外からの高級綿糸に対抗する目的で、最新鋭の紡績機械が導入され、設立の翌年に紡績生産を、1918年に織布生産を開始した。
1942年には戦時下のため、13工場のうち紡績、紙布、繊維の3工場を残して、10工場を軍需品工場に転換した。また特需で儲けた利益で、味の素や三菱電機などの株を買いまくり、これが後の日清紡の含み益を生み出した。当時は新聞記者から、「日清紡は繊維会社なのか、証券会社なのか?」と揶揄(やゆ)されたこともあった※1 。しかし終戦後は軍需はなくなり、工作機械とアルミの技術を使い、弁当箱から、鍋、釜まで作った時代もある。
(2)ブレーキへの進出
日清紡のブレーキ事業は、第二次世界大戦中に、戦闘機用に石綿を使ったブレーキ材の発注を受けたのが始まりであった※2 。石綿からブレーキパッドを作る際に、紡績技術が転用できるというのが、受注の理由であった。
戦後、航空機ブレーキから自動車ブレーキに転じたが、自動車ブレーキは紡績の技術とは違う方向に向かい、日清紡としては相乗効果が期待できなくなった。
しかし日清紡は、自動車をこれからの成長産業と考え、ただ1社自動車メーカーの資本が入らないブレーキメーカーとして事業を続けた。どの会社の資本も入っていないという「弱み」は、逆に全メーカーと取引できる「強み」となり、結果的には国内すべての自動車メーカーと取引できるようになった※3 。
(3)進む多角化
1950年代に入り日清紡は、土地や株式の含み益が多く、資金的に余裕があったことから、経営難に陥った企業からの支援依頼が度々舞い込んだ。
大倉財閥を設立した大倉喜八郎が、日清紡の草創期に相談役を務めていた縁で、1955年に、2代目の大倉喜七郎が、日清紡社長の桜田武に日本無線の経営支援を要請し、日清紡から経営陣が派遣されるようになった。繊維と関係のない無線事業への多角化は、この経営支援がきっかけだったのである。日清紡は日本無線以外にも、東邦レーヨンの経営支援もした。
日本無線は、日露戦争時の無線電信をルーツとし、無線電信から船舶航行支援システム、気象レーダー、消防緊急指令通信システムなどを手がけた。官公需や大型船舶を中心に、漁船向けのレーダーや、超音波を使った医療機器などにも進出していた。
日清紡は1960年には、硬質ウレタンフォームの生産を開始、1963年にフライス盤の製造を開始した。1964年にはブレーキ部門が、世界的ブレーキライニングメーカーの英国スモール・アンド・パークス社と技術提携した。
1972年に、戦後初めての海外工場をブラジルに設立した。また1978年には、東海製紙工業株式会社を買収し、製紙品のトイレットペーパー「白樺」で国内シェア1位を獲得した。
1980年代に入り、国内のモータリゼーションの波に乗り、ブレーキ事業を急速に拡大させた。1983年には国際金属加工機械展に、レーザー加工機を出展した。
1985年以降の円高、バブル崩壊の影響を受け、繊維業界は輸出から輸入へ転換を余儀なくされ、日清紡も海外展開を進めた。1993年、上海とインドネシアに、95年には米国に工場を設立した。
2004年にはより川下のビジネスに近づくため、高級ワイシャツメーカーのCHOYAを買収した。シャツに関しては、生地段階での供給を含めると、日清紡は国内で3割ほどのシェアを持っており、世界に先駆けて、ノーアイロン・シャツ地を開発した。最近では、紳士服の青山商事と共同で、次世代ノーアイロン・シャツ「アポロコット」を展開し、ノーアイロン性を、綿100%でも実現している。
またエレクトロニクス事業拡大のため、2005年にはマイクロ波製品とアナログ半導体を主力とする新日本無線を連結子会社化し、さらに翌年には、日本無線、長野日本無線の株式を追加取得した(新日本無線には、村上ファンドが、より高い価格でTOBを仕掛けてきたが、買収後の価値向上を株主に訴え、日清紡が勝利し、村上ファンドは撤退した)。
日本無線は2000年代初頭までは、NTTドコモ向けに自動車電話や携帯電話端末を供給していたが、その後は船舶用無線機や防災行政無線機などを主力事業としてきた。しかし世界的な海運・造船市況の悪化の影響を受け、業績は低迷が続いていた。日清紡との連携によって、コスト構造改革などで業績を立て直すことになった。
(4)日本無線の沿革
繊維と無線の間には何ら関係がないと思われるが、前述のように、日清紡の資金が潤沢であった時期に、日本無線の経営再建に日清紡が役員を送ったことが契機となり、それが現在の関係につながっている。
日本無線は、1915年に日本無線電信機製造所として創業、無線電信機や真空管の製造を開始した。1920年に日本無線電信電話株式会社に改組し、気象放送用無線機を完成させた。1924年には、無線とテレビの会社であるドイツのテレフンケンと資本・技術提携し、ラジオ受信機の開発に着手した。1942年に日本無線株式会社に商号を変更。超音波測深機を完成させた。
1953年に東証に上場し、54年には日本初の気象レーダーを完成させた。
1977年にはアマチュア無線機を発売した。1990年には世界初のカーナビ向け車載用GPS受信機を開発。1993年には、国内の携帯電話機に参入した。2006年には2輪車用ETC車載器を発売している。
2010年に、日清紡ホールディングスの連結子会社となった。2012年には「新たな成長に向けた事業構造改革」を公表し、2017年に、日清紡ホールディングスの完全子会社となった。
現在日本無線は、放送(テレビ、ラジオ、衛星)、産業・施設、道路・鉄道、組込(モジュール、チップ)の4分野を擁する企業になっている。
一方新日本無線は、1959年に日本無線の全額出資により、埼玉日本無線として創立され、1961年に新日本無線に改称した。その後、日本無線と米国の軍需品会社レイセオンとの合弁会社になった。
1962年には、日本無線より半導体製造部門を、1963年にはマイクロ波管および半導体販売部門を譲渡された。2000年に東証二部、2002年には東証一部に指定替えした。そして2005年に親会社が日本無線から日清紡に変わり、2018年に日清紡ホールディングスの完全子会社になった。
現在では、マイクロ波製品(マグネトロン、衛星/地上通信用コンポーネント等)、電子デバイス製品(半導体集積回路、半導体デバイス、SAWフィルター)などを擁する企業になっている。
(5)ホールディングスの誕生
日清紡は2009年4月持株会社制に移行し、傘下に次の6つの事業会社を持つ日清紡ホールディングスが誕生した。
- 日清紡テキスタイル(繊維)
- 日本無線(エレクトロニクス)
- 日清紡ブレーキ(ブレーキ)
- 日清紡ペーパープロダクツ(紙製品)
- 日清紡ケミカル(化学品)
- 日清紡メカトロニクス(メカトロニクス)
2010年に入ると、エレクトロニクスおよびブレーキをコア事業化する動きが一層強まった。同年、日本無線、長野日本無線を連結子会社化した。さらに、2017年には、紙製品事業を大王製紙に売却し、一方で日本無線の全株式を取得した(日本無線は同時に上場を廃止した)。
また2018年には、リコー電子デバイスを連結子会社化した。リコー電子デバイスは、以前からアナログ半導体の製造で新日本無線と協力関係にあった。同社を連結子会社化することで、製造工程の相互補完を高め、コスト低減による価格競争力も高める狙いがあった。また自動車や産業機器向IoTどの分野で、製品の開発を加速させる狙いもあった。
(6)事業構造の数値的変化
1940年代〜1960年代の日清紡は、戦後の生活物資需要に応えて非繊維分野に多角化したが、売上の9割は繊維が占めていた。日清紡のセグメント別売上高を見ると、1970年には、繊維が売上の約82%を占めており、本業は繊維事業であったことがわかる。

1980年には、繊維:約68%、ブレーキ:約8%、化学品:約15%、紙製品:約6%と多角化事業の構成比は増えたが、本業は未だ繊維事業であった。
1990年でも、1980年とセグメントの構成に大きな変化はないが、ブレーキが約14%と伸びを示している。繊維事業が約67%であり、変わらず本業であったことがわかる。

ただしこの頃までの日清紡は、戦前から戦後にかけて綿紡で稼いだ利益を有価証券に換え、その売却益でも利益を稼いでいた(ちなみに1991年3月期の売上高よりも、有価証券の含み益のほうが大きかった)。
2000年には、繊維:約37%、ブレーキ:約22%、紙製品:約12%となり、本業であった繊維事業の割合が減った。逆に、ブレーキが2割を超えた事業に成長を遂げた。なお、ブレーキ事業の売上は2003年3月期で563億円(繊維は740億円)であったが、営業利益は50億円と7期連続で繊維を上回り、高い売上高営業利益率を誇っていた。
2010年には、繊維:約23%、ブレーキ:約17%、化学品:約6%、紙製品:約13%、精密機器:約10%、エレクトロニクス:約21%となり、かつての本業であった繊維は2割となり、非繊維事業が8割を占める構成に変化した。
以上のように、日清紡は長い時間をかけて、繊維の会社からブレーキ、エレクトロニクスの会社へと本業転換を遂げてきたのである。
現在日清紡には、エレクトロニクス(無線通信とマイクロデバイス)、ブレーキ、精密機器、化学品、繊維、不動産の7つのセグメントがあり、ちなみに2018年12月期の売上構成比は、エレクトロニクスが約35%、ブレーキが約32%、精密機器が約15%、繊維が約10%、化学品が約2%、不動産が約1%となっている(なおセグメント別営業利益では、不動産が最大になっており、営業利益率でも不動産が一番高い)。
幅広い事業を手がける日清紡ホールディングスの目指す姿は、「『環境・エネルギーカンパニー』グループとして地球環境問題解決に向けたソリューションを提供」と表されている。また、今後の戦略的事業領域として、「モビリティ」「インフラストラクチャー&セーフティ」「ライフ&ヘルスケア」の3分野が挙げられており、事業領域には祖業の「繊維」という文字はなくなっている。日清紡の事業転換は、社名から「写真」が消えた富士フイルムホールディングスと似ているのかもしれない。
※1 『会社の寿命』(1984) ※2 『日経ビジネス』2004年6月28日号 ※3 『日経ビジネス』2003年9月8日号
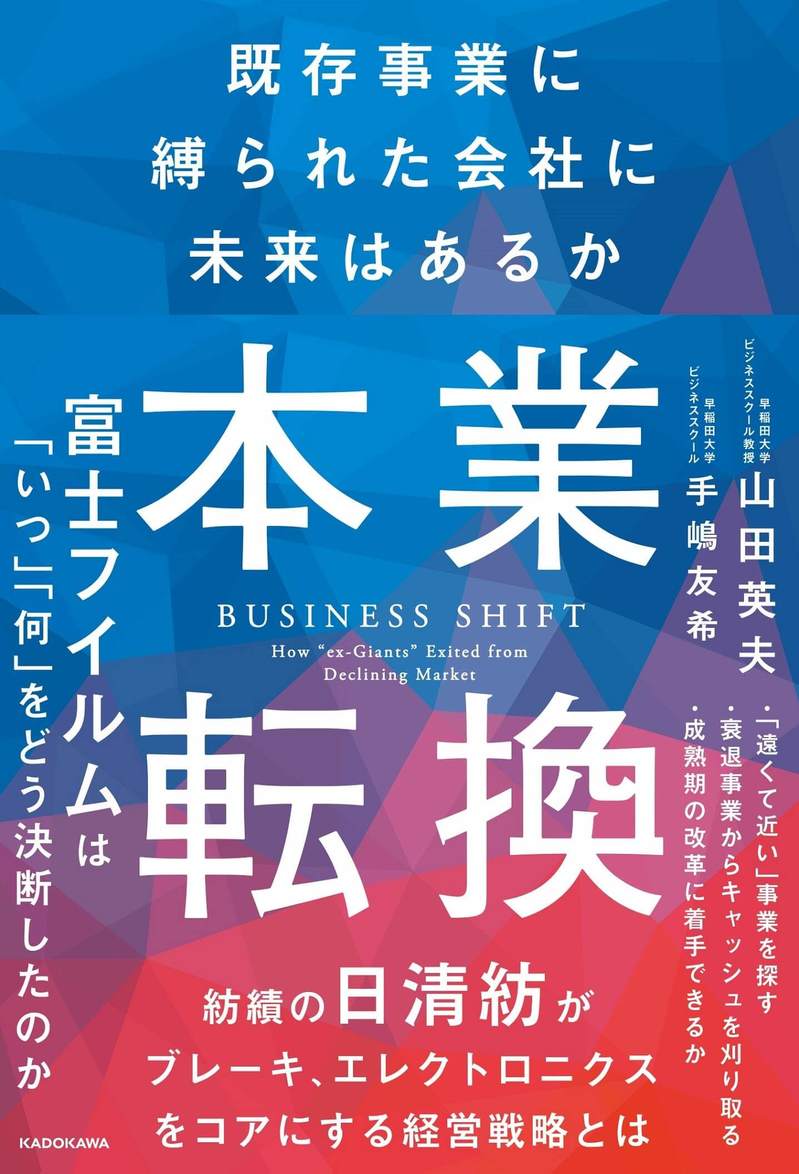
※画像をクリックするとAmazonに飛びます