(本記事は、山田英夫氏、手嶋友希氏の著書『本業転換――既存事業に縛られた会社に未来はあるか』KADOKAWAの中から一部を抜粋・編集しています)

両社の相違点① 新たな収益源
両社の相違点は、主に戦後の戦略の違いにある。具体的には、何を新たな収益源としたかという戦略の違いである。
戦中・戦後の復興期において日清紡は、1944年から摩擦材(自動車のブレーキパッド)の生産を開始した。繊維業とブレーキの摩擦材は、技術面で共通点があった。ブレーキの摩擦材は、そもそも石綿糸、つまり繊維状のアスベストであった。今は使われていないが、繊維状のアスベストをシートに加工して、自動車のブレーキの摩擦材を製造していた※1。また、戦時中に航空機用ブレーキを製造していた関係で、ブレーキ技術を持っていたことも関連性があった。
戦後に始めた製紙業は、戦時中、空襲を逃れるために、ブレーキの摩擦材を製造する工場を、東京から静岡へ移転することを検討したことがきっかけになった。ブレーキの摩擦材であるアスベストをシートに加工するには、抄紙(しょうし)機が必要であったため、抄紙機のある製紙工場を買収した。しかし工場移転の前に終戦を迎えたため、東京の工場でブレーキの摩擦材の生産を継続することになった。そのため買収した静岡の工場では、そのまま製紙業を継続することになった※2 。
繊維業と製紙業の関連性としては、紙の原料が綿と同じセルロースのため、技術的な共通点が多かった。製紙業は徐々に成長し、1978年に東海製紙工業株式会社を買収したことを機に、製紙品のトイレットペーパーで国内トップシェアを獲得した。
化学品事業として、1960年から生産を開始したウレタンフォームは、車のクッション、マットレスに主に使用され、ブレーキや本業の繊維品のシーツなどにも使用された。
また日清紡は1950年代後半に、合成繊維への進出はしないと決断した。紡績の一貫生産の中に取り込め、石油化学をもとにした合繊の加工効率が良いことは知られていた。しかしながら、メーカーとして安定供給および原材料コストを検討し、結果的に合成繊維への進出は見送った。
一方カネボウは、終戦後の1949年、繊維一本に戻り、繊維以外の全事業を譲渡した。
それ以降、1961年に化粧品へ進出するまでは、繊維一本であった。
1960年代に入り、1961年に化粧品に本格参入、1963年にナイロンの生産を開始し、天然繊維から合成繊維へ進出、1964年に食品事業、1966年に薬品事業へ進出した。多角化を始めた1961年からわずか5年間で、化粧品、食品、薬品と3つの事業に参入した。また、本業の繊維業においては、日清紡が見送った合成繊維へ進出し、3大天然繊維(綿・羊毛・絹)と3大合成繊維(アクリル・ナイロン・ポリエステル)のすべてを持っているのは、カネボウの特長となった。
繊維事業と非繊維事業である化粧品、食品、薬品とは、技術面での共通点はなかったが、カネボウは、異業種への多角化を積極的に展開した。
強いてシナジーを挙げるならば、ファッションカラーに羊毛の染色技術が使用されたことや、化粧品の販売ルートを利用して、女性用の下着等、カネボウの軽衣料の販売をしたことであった。カネボウの場合、技術面での共通点は薄かったと言える。
わずか5年間で3つの異業種へ進出を果たしたが、結果的に、多角化した非繊維事業のうち、利益を挙げられたのは化粧品事業だけであった。
また、カネボウが手がけた3大合成繊維は装置産業であり、設備には多額の資金を要した。カネボウが合成繊維へ進出した時点を、東レ、帝人、旭化成など先発企業と比較すると、かなり遅かった。合成繊維の市場において、販売力、品種、生産効率を比較すると、カネボウが勝てる市場ではなかった。また、カネボウが合成繊維への参入時点では予知できなかったことではあるが、合成繊維は石油化学がもとになるため、1970年代のオイルショックの影響は多大であった。
日清紡は、新事業への参入は極めて慎重で、「経営・人・モノ・カネ・技術」が絡み合っているかという視点が貫かれた。すなわち、日清紡は一貫して、培った技術が関連する事業への多角化しか行っていない。
一方、カネボウの異業種への多角化は、吸収合併や買収が契機であった。化粧品事業は、鐘淵化学工業の化粧品事業を買収し、食品事業は、ハリスや立花製菓を買収することで事業をスタートさせた。薬品は、山城製薬を買収して、事業を開始した。
カネボウは、M&Aによる異業種への多角化を積極的に推進し、組織統合・分社などを繰り返したため、事業を横断する有機的な繋がりは薄かったと言える。
両社の相違点② 新事業参入のタイミング
両社のもう1つの相違点として、1940年代〜1960年代の戦略の違いがある。具体的には、いつ新事業に参入したのかという違いである。
日清紡は、戦後の復興期で繊維をはじめ生活物資の需要が多かった1940年代後半以降、時間をかけて徐々に、ブレーキの摩擦材、製紙業、化学品事業へ参入し、それぞれの事業を確実に成長させてきた。1990年までは、主力の繊維事業が売上の約67%を構成していたが、2000年には、ブレーキ事業が繊維に続く中核事業に成長していることからも、急激な多角化による事業拡大は行ってこなかった。
また日清紡は、経営難に陥った企業の再建支援を目的として、1955年に日本無線に経営陣を派遣し、1960年代から再建に入った。
最終的に、2010年に日本無線、長野日本無線を連結子会社化し、エレクトロニクスをコア事業とする動きを一層強めた。日清紡が、日本無線に経営陣を派遣してから55年以上の年月を経て、エレクトロニクス事業は、日清紡の新たな主力事業へと成長を遂げたのである。
一方カネボウは、1961〜1966年の5年間で、化粧品、食品、薬品と、吸収合併・買収によって、3つの新事業を始めた。本業であった繊維業においても、1963年に合成繊維へ進出を果たした。
1950年代後半から1960年代前半はデフレ不況となり、繊維業界全体として厳しい環境であった。当時の繊維業界の置かれた環境を鑑みれば、繊維以外の新たな収益源を開拓する必要があった。
カネボウも例外ではなく、わずか5年間で、3つの異業種へ参入したことに加え、装置産業である合成繊維への参入も重なり、多額の投資が必要となった。
カネボウは繊維の需要が安泰である時期に、新たな収益源を模索しておらず、事業環境が悪化してから、急激にM&Aによる異業種への多角化を実施した。また急激なスピードで一挙に多角化したことで、経営資源が拡散し、当該業界が必要とする投資金額に届かず、事業ごとへの資源配分が手薄になった。
後手に回りながらもM&Aに頼った多角化を進めたカネボウであったが、結果的に、新たな収益源となったのは、化粧品事業だけであった。
※1 「繊維から事業転換、強いコア技術が成長の鍵 日清紡」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO21413870S7A920C1000000/ ※2 前掲URL
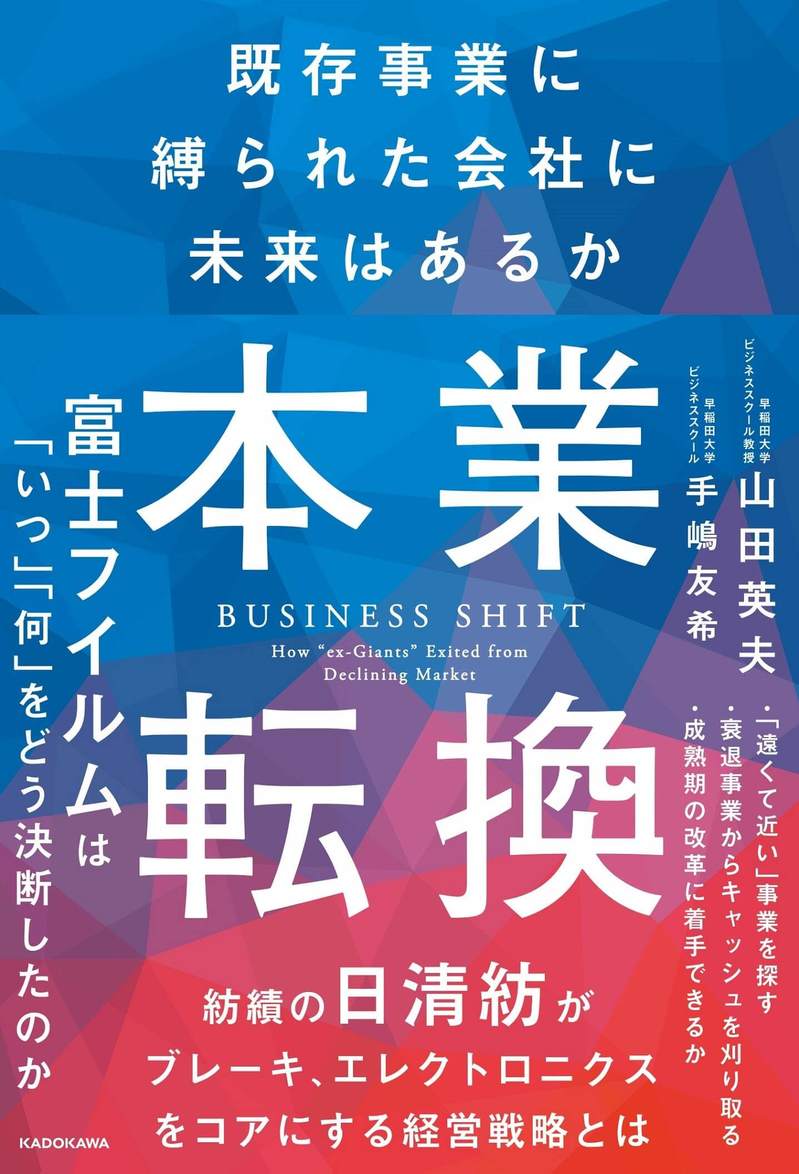
※画像をクリックするとAmazonに飛びます