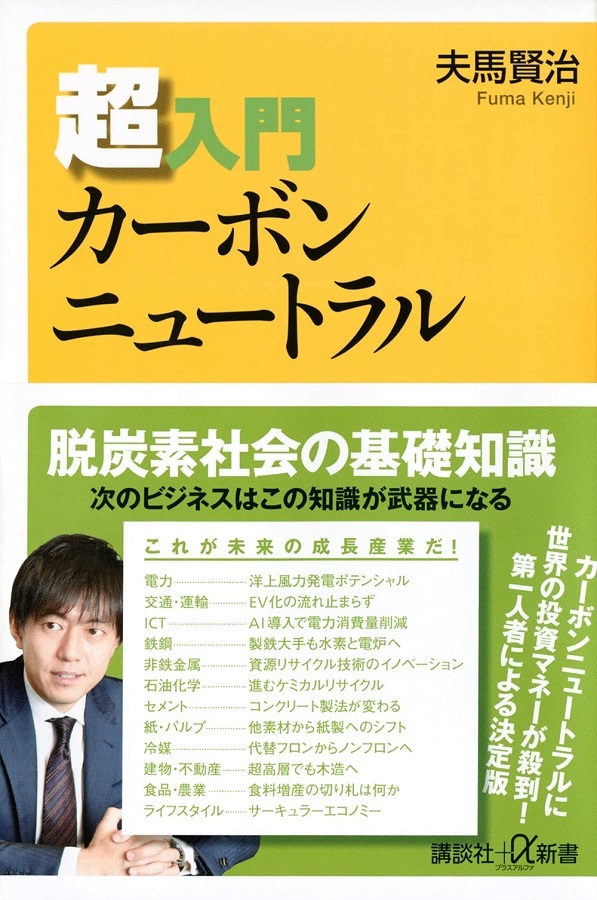本記事は、夫馬賢治氏の著書『超入門カーボンニュートラル』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

カーボンニュートラルの具体的な手法
カーボンニュートラルとは温室効果ガス排出量をプラス・マイナス・ゼロにすることだと、ここまで何度も説明してきた。現在の年間の温室効果ガス排出量は約50Gt。そして、気候変動を緩和するために、2050年までにこれをネットゼロにする。これを実現するためのオプションは、3つある。
1つ目は、現在排出している50Gtをゼロにする手法。これをカーボンニュートラルと区別して、「ゼロエミッション」や「カーボンゼロ」「ゼロカーボン」といったりもする。これが容易に実現できれば苦労はないが、残念なことに、完全にゼロにできる目処(めど)はまだ立っていない。これまでみてきたように、人間社会は至るところで温室効果ガスを出してしまうのだから、簡単であろうはずがない。
2つ目は、現状の50Gtの排出を続けたまま、大気中にある温室効果ガスをなんとかして同量の50Gt分吸収して、排出した分を全量相殺してしまう手法。強引にも思えるが、一応、計算上は、大気中の温室効果ガスを増やしてはいないので、科学的にはゼロエミッションと同じ効果が得られる。
3つ目は、1つ目と2つ目のオプションを組み合わせた手法。50Gtを減らせるだけ減らしたうえで、それでもどうしても減らせない分を、大気中から吸収して、プラス・マイナス・ゼロにする。現在、世界的に、この3つ目のオプションが最も現実的な解となっている。
どうしても削減できない温室効果ガスの排出分を、大気中からなんとかして吸収することを「二酸化炭素除去(CDR)」「ネガティブエミッション」という。具体的な方法はおおむね5つある。
①植林・森林管理―まだ日本の24倍の面積に植林できる
まずは植林。森林を農地に変えたり森林火災が発生したりすると、大気中に二酸化炭素が排出される。ならば、逆に地球上の森林を増やせば、大気中の二酸化炭素は減らせる。
地球には植林ができる場所はもうほとんど残されていないという人もいるが、科学者はそうは見ていない。世界にはまだ日本の面積の24倍にもなる9億ヘクタールの植林ポテンシャルがあるという。実現すれば、森林は今よりも25%以上も増え、大気中の二酸化炭素を最終的に200Gtも吸収できる。200Gtは、現在の地球大気中の二酸化炭素の25%に相当する。
そして、実際に企業からも積極的に植林に乗り出す動きが出てきている。「経済サミット」の異名を持つ「ダボス会議」を主宰する世界経済フォーラムは、2020年に国連環境計画(UNEP)と国連食糧農業機関(FAQ)が展開する「生態系回復の10年」という国際プログラムと連携し、「1t.org」という団体を発足している。1tは「1 Trillion」の略語で、日本語にすると「1兆」。この団体は、2021年から2030年までのあいだに世界全体で1兆本の植林をおこなうことを目指している。
1t.org の活動は、すでにアメリカでも具体的な動きとなって現れている。企業、自治体、NGOなど26機関が、1t.org のアメリカ支部を立ち上げ、合計で8億5500万本の植林計画をすでに発表済みだ。アメリカでは近年山火事が頻発し、森林が消失していることもあって、企業が積極的に動き出している。1t.org のアメリカ支部には、マイクロソフト、アマゾン、セールスフォース・ドットコム、リンクトイン、バンク・オブ・アメリカ、マスターカード、ペプシコ、ティンバーランド、HPなどが発足メンバーとして参加している。今では、54機関で49億本の植林計画にまで伸長した。
アフリカでも現在、アフリカ大陸を横断しているサハラ砂漠の南部で、全長8000㎞にも及ぶ土地に、2030年までに1億ヘクタールに植林する「グレート・グリーン・ウォール」プロジェクトが、国連とアフリカ連合、EUの主導で展開されている。実現すれば、2030年までに大気中の二酸化炭素を0.25Gt吸収でき、1000万人分の雇用も創出できるという。2007年のプログラム発足以降、すでにアフリカ大陸の21ヵ国がこのプロジェクトに参加しており、目標を超える1.56億ヘクタールの土地が植林対象地域に指定された。過去約10年でプロジェクトは全体の15%を完了しており、残り約10年で一気に動きを加速させようとしている。
植林ではなく、既存の森林を育てていくことも、十分、温室効果ガスの吸収量増加につながる。森林は適切に管理すれば、数百年、数千年、数万年と育っていくからだ。
②ブルーカーボン―二酸化炭素の55%は海洋植物が吸収
植林や森林管理で得られるのと同じ効果を、海洋植物でも実現できるのではないかということで注目されているのが「ブルーカーボン」だ。海で生きている海藻、海草、植物プランクトンは、大気中の二酸化炭素を吸収して植物の成分にしている。実際に、地球上で生物が吸収している二酸化炭素のうち、55%はブルーカーボンで、海洋植物は大量の二酸化炭素を吸収してくれている。
ブルーカーボンの中で特に注目を集めているのが、マングローブ林だ。マングローブは浅瀬の海底に根を張り、海上に葉をつけて生息している。通常の植物は、塩水につけると枯れてしまうが、マングローブは海中で生息できる特殊な植物だ。そのためマングローブ林は多様な生物の住処(すみか)となり、豊富な生態系を作り出してくれている。
マングローブ林を増やせば大気中の二酸化炭素の吸収量も増やすことができる。だが近年、マングローブ林は、沿岸部の観光開発や埋め立て、またエビの養殖などでむしろ消失してきている。そのため、実際にはマングローブ林が消失した分だけ、大気中に二酸化炭素が放出されてしまっている。
マングローブ林以外のブルーカーボンでは、藻類が豊富な海藻藻場(もば)と、海草類が豊富な海草藻場も有名だ。海藻ではワカメや昆布、海草ではアマモなどがよく知られている。最近では海草や海藻に栄養素が豊富なものも見つかっており、食物や飼料としても注目され始めている。藻場を増やしていけば、植林と同じように大気中の二酸化炭素を減らすことができる。
③バイオ炭(たん)―田畑に撒くと土壌の養分を豊富に
バイオ炭は、ネガティブエミッション技術の中でも最も新しく認知された技術だ。バイオ炭は、バイオマスを無酸素または低酸素の環境下で350℃以上の熱で分解すると得られる炭のことをいう。もちろん、このバイオ炭を燃焼させれば二酸化炭素が出てしまうのだが、燃焼させるのではなく、田畑に撒まくという使用法がある。バイオ炭は自然分解されにくいので、放置しておいても大気中に二酸化炭素をあまり排出しない。農地に撒くとむしろ土壌中に炭素を蓄積する効果がある。それにより、土壌の養分を豊富にし、作物の成育を促進する。
バイオ炭は、農林業から出た廃棄物や食品廃棄物を原料にできるため、原料の調達コストも安く、廃棄物のリサイクル効果もある。すでにアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスでは、積極的にバイオ炭の活用が始まっている。(※日本バイオ炭普及会〝各国政府の取組〞)
バイオ炭の活用は、日本でも農林水産省が普及に向けて動き出している。バイオ炭は、大気中から吸収した二酸化炭素を固定したままにできる上に、農地の土壌の透水性、保水性、通気性の改善などの効果もあり、いいこと尽くめだ。唯一の課題は回収と輸送のコストを下げることで、今の日本では、回収が容易な殻(もみがら)などに原料が限られている。今後、さまざまな農林業廃棄物や食品廃棄物を効率よく集められるようになれば、バイオ炭によって農業振興も可能になってくる。
④直接空気回収(DAC)―大型換気扇で二酸化炭素を吸引
4つ目は直接空気回収と呼ばれる技術で、人工的に大気中の二酸化炭素を化学反応により吸収してしまおうというものだ。
この手法は、①の植林・森林管理や②のブルーカーボンとは、かなり毛色が違う。植林やブルーカーボンは「自然に基づく解決策(Nbs)」と呼ばれているのに対し、DACは自然ではなく、完全に人工的な技術を駆使する。
DACの一般的な方法は、大型換気扇のようなもので大気を吸引し、大気中に含まれる二酸化炭素だけを化学反応で吸着して除去してしまうというものだ。吸着させる化学物質ではアミンが最も有名だ。
だが、大気を吸引し、アミンを使って化学反応をさせるには、当然、電気や熱エネルギーが必要になる。せっかくDACで二酸化炭素を大気中から吸収できても、DAC設備を動かすための電気や熱エネルギーで大気中に二酸化炭素を排出してしまっては、意味がない。そのため、DACでは、設備を動かす電気を再生可能エネルギーにしたり、熱エネルギーの燃料をバイオ燃料等に切り替えたりすることが欠かせない。
現在、世界には稼働しているDAC設備が15ヵ所以上あり、欧米や中国に集中している。しかし現状はコストが高すぎて商業利用は難しいので、実験機的な扱いにとどまっている。全設備での年間の二酸化炭素吸収量の合計は9000tと非常に小さい。アメリカで建設中のものも加えると、全体で年間100万tぐらいにはなるという。ただ、本当に商業利用が可能になるかに関しては、産業界や金融機関の間でも否定的な見方がかなりある。現段階では、画期的なイノベーションが起き、非常に効率的に吸収できるDAC技術が開発されることが夢想されている状況と言ってもいいかもしれない。
⑤バイオエコノミー―植物を資源にして化石燃料に代替
最後はバイオエコノミー。こちらも植林と同様に、植物の力で大気中の二酸化炭素を吸収しつつも、栽培した植物を資源として積極的に活用していく手法だ。
温室効果ガスは化石燃料が主要な発生源であるならば、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料を極力使わない経済システムを構築していくことがきわめて重要となる。たとえば、同じ火力発電でも、化石燃料を使うのでなく、植物由来のバイオマスを燃料とする発電が注目されている。自動車でもガソリンやディーゼル燃料の代わりに、バイオ燃料やバイオディーゼルを使おうという動きもある。ガス燃料についても、食品廃棄物などを発酵させたバイオガスがすでに活用されている。
だが、化石燃料は、燃料以外の目的でもかなり多く使われている。たとえば、ポリエステルやアクリルなどの化学繊維は、石油が原料だ。プラスチックも合成ゴムも同じく石油が原料だ。最近では、植物由来の油脂を使ったバイオ繊維やバイオプラスチックの研究も、盛んにおこなわれている。紙繊維もバイオ素材のため、プラスチック容器を紙容器に切り替えることもバイオ素材化ということができる。
ただ、植林・森林管理とは異なり、バイオエコノミーでは植物を資源として活用するために植えるため、せっかく二酸化炭素を吸収しても、最終的に廃棄や焼却をすれば二酸化炭素は再び大気中に戻っていってしまう。したがって、栽培する量よりも使用する量が多くなれば、大気中の二酸化炭素量は増えてしまう。バイオエコノミーでは、使用量よりも栽培量を増やして二酸化炭素の吸収量を確保することが絶対条件として必要となる。
また、バイオ燃料は、燃焼時に排出される二酸化炭素を直接空気回収(DAC)技術を用いて工場内で回収してしまうこともできる。燃料となる植物生産で大気中の二酸化炭素を吸収したまま、燃料を消費しても大気中に二酸化炭素が出ていかないようにできれば、全体として大気中の二酸化炭素を減らすことができる。
工場などで排出される二酸化炭素を回収し、地中などに埋蔵してしまう一連の技術のことを「炭素回収・貯留(CCS)」技術と呼ぶ。また貯留する代わりに、何か別の用途で用いる場合は「炭素回収・利用(CCU)」技術という。この2つをあわせて「炭素回収・利用・貯留(CCUS)」技術と呼ぶ。バイオ燃料にCCS技術を組み合わせ、燃料を活用しながら大気中の二酸化炭素を減らしていくことを、「バイオエネルギーCCS(BECCS)」という。