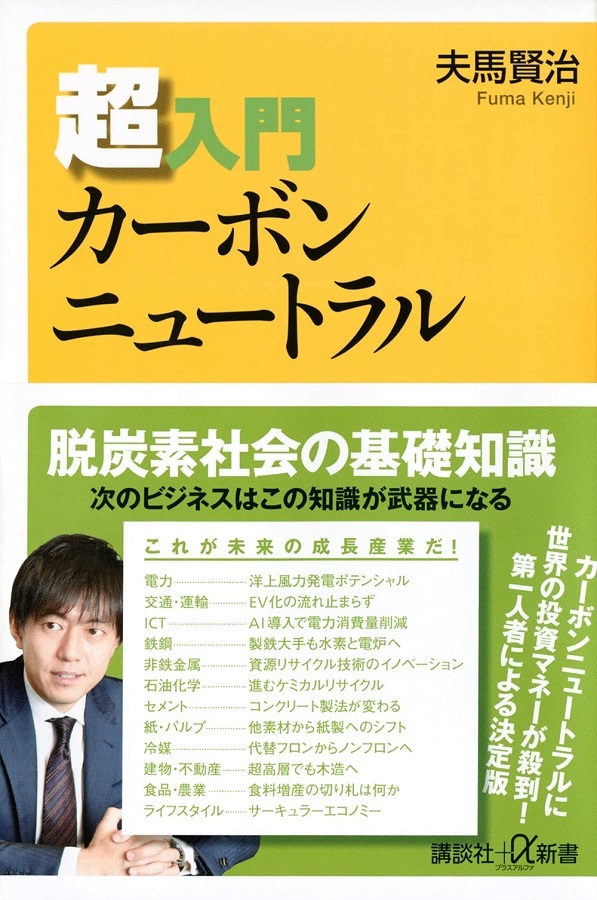本記事は、夫馬賢治氏の著書『超入門カーボンニュートラル』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

【資本主義の未来と日本】
日本はこれからどうなっていくのか。もっといえば、日本政府、日本の各自治体、日本企業、日本国民、日本の市民社会は、この激流の時代をどう乗り越えていけるのか。
わたしは前著『ESG思考』の中で、経済認識の4分類モデルというものを提示した(図17)。この4分類それぞれへのメッセージをもって、本書を締めくくってみよう。

ニュー資本主義
ニュー資本主義は、自然環境や社会情勢が悪化している昨今の状況を見つめつつ、それでも人類に健康、安全、幸福をもたらすため、環境・社会へのインパクトと持続可能な経済成長を両立させようという考え方だ。ポイントは持続可能な経済成長で、この点が短期的成長や短期的利益のみを追求し、社会や自然環境を荒廃させてきた従来型の資本主義観とは大きく異なっている。
カーボンニュートラルの文脈では、ニュー資本主義は、まさに「デカップリング」を志向する考え方となる。気候変動を抑制するためにカーボンニュートラルを掲げながら、同時に経済成長も追求するというものだ。本書でも伝えてきたが、国連、国際環境NGO、各国の金融当局、機関投資家、産業界も、2010年頃からニュー資本主義の立場を鮮明にしてきている。
日本でも、菅首相の2020年10月の所信表明演説、そして経団連の2020年12月の提言「2050年カーボンニュートラル実現に向けて」は、「経済と環境の好循環」という表現を用いており、2020年後半から日本の政府と産業界はようやく本格的にデカップリングに舵かじを切った。
ニュー資本主義の時代には、ほぼすべての業種で、カーボンニュートラルを実現するための大幅な技術イノベーションやビジネスモデルの転換が必要となってくる。しかし、この変化の速度について、エネルギー問題を所管する国際エネルギー機関(IEA)は2021年に、日本のエネルギー政策の転換の遅さに苦言を呈する報告書を発表した。低炭素技術の導入、規制障壁の撤廃、エネルギー市場の競争環境の向上がなければ、カーボンニュートラルは実現できないとの見方を示している。
技術イノベーションやカーボンニュートラルに必要なものとして、ここでは3つの要点を提示しよう。まずは、先を見据えたイノベーション分野の設定。日本の官民では、ハイブリッド車の扱い、プラスチック・リサイクルの方向性、電源構成目標、水素の生産方法について、いまだに確たる統一見解を定めることができていない。これでは他国以上の速度で産業転換を図ることはできないだろう。
2つ目の要点は、大胆なグローバル市場展開構想。中国は大量生産によるコスト競争力に大きな強みを持つ。さらに欧米のグローバル企業は、そもそも国内市場だけではなく、グローバル市場を視野に入れているため、やはりコスト競争力に優れている。それに対し日本企業が、市場が縮小していく日本国内のみを見据えた戦略を描いていては、必ずコスト競争力で負けてしまう。日本は中国のコスト競争力に関しては地政学的な防衛戦を国際協調で敷いていくことで、中国の海外市場進出に歯止めをかけようとしている。しかし仮に中国製品や中国の技術が日本を席巻することを防げたとしても、そのスキに欧米もしくは他の新興国からのイノベーション攻勢により、日本企業が敗北するおそれもある。
3つ目の要点は、金融機関と投資家との連携。急速な産業転換には必ず資金が必要となるが、経団連も伝えているように、財政難の日本政府にはもはや産業転換を支えるだけの資金力がない。頼みの綱は融資銀行であり、株主であり、社債債権者だ。今、気候変動による金融危機リスクへの懸念を感じながらESG投資やサステナブルファイナンスに傾斜している金融機関や投資家は、企業にとって重要な資金の出し手となる。しかし、企業が「先を見据えたイノベーション分野の設定」と「グローバル市場展開構想」を示してくれなければ、金融機関や投資家は安心して積極的に投資することができなくなってしまう。そのため、これらの3つの要点は相互に関係している。
また、ニュー資本主義の状況で、大企業が長期的にカーボンニュートラルを追求するようになると、大企業が不当に市場を独占しようとし、経済構造が歪んでいく可能性も出てくる。そこには具体的には3つのリスクがある。まず市場寡占や下請いじめなど競争法上の不当行為。これらを日本の独占禁止法では「優越的地位の濫用」と呼ぶ。2つ目は、政治献金などを通じて不当に政治に影響力を行使し、大企業に有利な市場環境を創り出していくこと。3つ目は、グローバルな企業体制を悪用し、租税回避を追求することで、国内で努力している中小企業が不利になっていくこと。
これら3つのリスクはすでに投資家も認識している。そのため、これらの状況に陥らないように、投資家は企業に対し、競争法上の対応方針や行政処分結果、政治献金の献金先と金額、納税方針と各国での納税額の3つについて、時価総額の大きい上場企業から段階的に情報開示を要求するようになってきている。(※情報開示を企業に求める役割は、MSCIやサステイナリティクスなどのESG評価機関が担っている。また近年では機関投資家自身も結束し、株主総会で情報開示を義務化する決議をおこなう事例も出てきている。)
陰謀論
陰謀論は、カーボンニュートラルの動きを「誰かの陰謀」とみる見方だ。なかには、気候変動そのものを否定する勢力までもがいる。陰謀論では、カーボンニュートラルの動きは、欧米や中国が仕掛けた「まやかしの誘い文句」であり、決して海外の流れに追随してはならないと主張したりもしている。最近では「国連は中国に乗っ取られている」説の論者も増えてきたことで、国連が気候変動危機を主張するのであれば、それは信じてはいけないという声まである。
だが、気候変動を否定したり、気候変動による経済影響を過小評価したりする科学者は、国際的に見てもかなりの少数派だ。もちろん科学は多数決で決まるものではないが、陰謀論の人たちは、自分たちが拠って立つ科学的根拠は決して盤石ではないことを認識しておくべきだろう。
陰謀論者の中には、国際的な陰謀から日本を守るためには、日本政府が巨額の資金を日本企業に投じ、日本の技術開発を全面的に支援することで、国内生産を保護し、海外輸出を支援すべきだと主張する人もいる。しかし、日本も加盟しているWTO(世界貿易機関)の協定では、特定の業種や特定の企業を対象とした輸出補助金および国内産品優先使用補助金は、明確に禁止補助金として指定されている。以前は、研究開発補助金と環境補助金に関しては、規制の対象外として明確に容認されていたが、この規定は1999年に失効し、同様に輸出や国内産品優先使用を目的とするならば禁止されることとなった。この禁止規定に違反した場合、海外政府からWTO訴訟を起こされ、敗訴すれば規定を撤回するよう迫られたり、対抗措置を打たれたりする可能性もある。
これらの禁止規定は開発途上国には適用されないが、先進国においては、WTO協定を考慮した補助金を実施しなければならなくなっている。たとえば、国内消費のための国内生産に対する補助金は容認されているが、日系企業の国内生産と外資系企業の国内生産は区別してはならない。また、たとえば電気自動車購入補助金を出す場合、トヨタ自動車などの日本企業が製造した自動車と、中国企業が日本で製造する自動車を区別することが禁止されている。さらに、日本企業の研究開発や製造に補助金を出したことで、輸入品にデメリットがある場合も、WTOで違法性補助金と判断される可能性もある。
このように各国の補助金は、「自国企業」(実際には定義は難しいが)だけを保護することが難しくなっており、たとえばEUの補助金は日本企業が申請しても通常認められるようになっている。一方、日本では「日本企業のための補助金」「日本の技術のための補助金」という言論が非常に多いが、その色を強めれば強めるほどWTO協定違反のおそれが出てくることを知っておく必要がある。
それでも、カーボンニュートラルという国際潮流やWTOという国際ルールに背を向け、日本独自の考え方や理想を貫く方法がないわけではない。パリ協定やWTOから離脱をすれば、日本は国際的な潮流からもルールからも解放されることになる。実際に日本は昭和の時代に、国際的な動きに反発し、独自路線を貫いて開戦し、最終的に失敗して国際的なルールに復帰したという苦い歴史もある。
もし日本が、欧米主導の国際協調に背を向けたとき、グローバリゼーションに反発し、欧米諸国と敵対している国々はおそらく味方になってくれるだろう。しかし、現在、アメリカとEUの双方から通商関係を断絶されたり、制裁を課されたりしている国は、北朝鮮、イラン、シリア、ベネズエラなどだ。この路線ではたして日本は本当に救われるだろうか。
陰謀論者はわたしたちをどこに導こうとしているのか、いまいち釈然としない。感情論で反発しても、明確なゴールが描けない限り、その道がいいと判断することは、本来は難しいはずだ。
脱資本主義
脱資本主義は、デカップリングを否定する考えだ。カーボンニュートラルをしながら経済成長を実現することなどは不可能で、利益のみを追求するという行動原理が宿命の企業や投資家が本気で気候変動対策を進めることなどありえないと考える。
しかし、本書の中でも示したように、デカップリングが可能だと最初に強く提示したのは、企業や投資家ではなく、国連と環境NGOだった。企業と投資家はむしろ、デカップリングが可能だと国連と環境NGOによって説得されたのだ。企業と投資家は、今や強くそれを確信するに至り、現在はニュー資本主義に移行している。
脱資本主義によると、資本主義を形成しているのは大企業と、謎の「グローバル金融資本」という勢力のようで、彼らを葬り去り牧歌的な社会システムに回帰すれば、気候変動は止まることになっている。だがその根拠は明白ではない。脱資本主義を実現すれば温室効果ガス排出量が削減できるとする論者には、デカップリングは不可能ということの実証とともに、資本主義的な金融の流れが止まれば温室効果ガス排出量が削減できることについての論理的説明と実証が求められる。さらに、第3章で示したように、脱資本主義が引き起こす傾向にある自由権の抑圧についても十分に考慮する必要がある。
実際問題として、国連や各国政府がカーボンニュートラルを実現するにあたって懸念しているのは、大企業ではなく中小企業のほうだ。大企業は資金調達力が高いため、カーボンニュートラルを達成するための技術イノベーションやビジネスモデル転換について、自力で敢行できる。だが、中小企業の場合は、経営資源に限りがあるため、長期的な展望を見据えた大胆な事業転換を起こしづらい。
このことは日本でも顕著に表れている。たとえば、日本政府はカーボンニュートラルを積極的に進める企業を政策的に支援するため、カーボンプライシング制度の導入を検討している。カーボンプライシングには、特定資源税(特定の化石燃料由来の製品に課税する)、炭素税 (排出量に応じて課税する)、二酸化炭素排出量取引制度(各社に排出量上限を設定し、下限を下回った場合には余剰分の排出量販売権を、上限を上回った場合には超過分の排出量購入義務を課す)などの複数の選択肢がある。
これに対し、カーボンプライシングの議論が始まった2021年1月のタイミングで、大企業中心の経団連の中西宏明会長は「カーボンプライシングを拒否するところから出発すべきではない」と前向きな姿勢を表明する。一方で、中堅企業中心の経済同友会の櫻田謙悟代表幹事は「カーボンプライシングを社会が受容するか、大きなハードルがある」、同じく中小企業中心の日本商工会議所の三村明夫会頭からは「国際的にみても割高なエネルギーコストを負担し、高止まりする電力料金が経営に影響を及ぼす」と明確に反対姿勢を示した(※サンケイビズ(2021)〝カーボンプライシング、経済界に賛否 経団連会長「拒否せず」に波紋〞https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210117/mca2101171947003-n1.htm )。やはり中小企業のほうがカーボンニュートラルのハードルは高いのだ。
脱資本主義では、大企業がカーボンニュートラルを阻む諸悪の根源とみている人が多いが、実際には中小企業のほうが抵抗感は強いということを認識しておく必要があるだろう。
オールド資本主義
オールド資本主義は、昔ながらの経済認識で、「カーボンニュートラルは経済を悪化させるからやらないほうがいい」というものだ。ニュー資本主義と脱資本主義の双方は現状からの転換を推奨するのに対し、オールド資本主義と陰謀論は、日本企業はカーボンニュートラルを進めることなく、現状維持でいいと説く。
そして、オールド資本主義と陰謀論の違いは、陰謀論は「欧米や中国の口車に乗せられるな」と考えるのに対し、オールド資本主義は「カーボンニュートラルは経済成長を止めてしまうから、最終的に世界中のどの企業も政府も本気にはならないだろう」と考える。
だが、オールド資本主義の主張は、往々にして、気候変動がもたらす外部的な経済ダメージを考慮していないことが多い。自然災害の増加、海面上昇、食料価格の高騰、感染症リスクの増大、金融危機リスクなどを考慮しても、それでもなお「カーボンニュートラルを実現しないほうが経済成長できる」というのであれば、気候変動がもたらす経済ダメージの各々についての反論が必要になってくる。
そして、オールド資本主義が考えるように、「どの企業も政府も本気になどならない」とはいかず、他の多くの国が宣言どおりにカーボンニュートラルを進めてしまったときのリスクも考えなければならない。
たとえば、諸外国で石炭、石油、天然ガスの採掘量が減少した場合に、日本は今のようなエネルギー資源依存型の経済をどのようにして将来維持できるのか。諸外国が国境炭素税を導入した場合に、日本は海外輸出を諦めていくのか。日本は国内市場縮小の中で海外進出に不利な状況を自らつくり出していっていいのか。他の先進国と歩調を合わせず反発姿勢を強めた場合に、日本の安全保障は担保されるのか。国際的なブランディングを放棄しても日本は大丈夫なのか。日本に賛同してくれる国はどこなのか。海外の機関投資家から株式を売却され、日本が世界の金融市場から孤立していったときに、日本の金融システムは回るのか。
現状維持は、未知の世界に飛び出さなくてもいいので、心地よく、安心感もある。だが、変化の激しい時代に、現状にしがみついていて、本当にいいのだろうか。日本では幕末に革命を起こし、維新を選択し、江戸時代から明治時代へと時代が移っていった。わたしたちは、あのとき変化を諦め、士農工商、男性の丁髷(ちょんまげ)、女性のお歯黒、幕藩体制、鎖国令の維持を選択していたほうがよかったのだろうか。
急激な変革を避ける現状維持思想は、短期的には既存の産業の延命策にはなりうる。ただし、短期的な効用を優先しすぎれば、大局観を誤り、長期的には企業体そのものを滅ぼしてしまう。そしてそれが地域の雇用にも破壊的な大きなダメージを与える。
わたしたちは、いやがおうでも、カーボンニュートラルという新しい時代の中で生きていくことになる。この状況にどのような経済認識でいくのか。本書が、いま一度皆さんが考えるきっかけになれば幸いだ。