
はじめに
英国がBREXITを巡り揺れ続けている。日産が英工場におけるスポーツ用多目的車(SUV)の生産計画を白紙撤回するなど決して無縁ではない。それ以外にもBREXIT前後における外国為替マーケットの動向にショックを受けた読者も少なくないのではないか。
(図表1 BREXIT前後における英ポンド実効為替レートの推移)

そうした中で実は今、BREXITが新たな火種をもたらしつつある。それは米英関係の悪化である。それも単なる外交関係のみではない。来年(2020年)実施予定の米大統領選挙にさえ、影響を与えかねない事態なのである。本稿は、BREXITを始めとして米欧に混乱を巻き起こしている英国がもたらしつつある新たな米英関係を模索する。そこでは、カギとなるのが実は「アイルランド」であることを考えていきたい。
混迷するBREXIT ~停滞から抜けるための「アイルランド・テロ」~
英国内はBREXITの議決を巡り混迷の最中にある。先週13日(GMT)には英下院が欧州連合(EU)からの「合意なき離脱」を回避する案を賛成多数で可決した。それでもBREXITを目指すメイ首相に対し、バーコウ下院議長は同首相による欧州連合(EU)離脱案を3度目の議会採決にかけることを事実上禁止した。他方で来週29日に離脱期日を迎える中でメイ首相は、EU側に対しその離脱期日の延期を求めた。しかしEU側はこれを却下したという。こうした直近のBREXIT動向を見る限り、英国がBREXITを実現できるかは不透明、むしろ懐疑的であると言わざるを得ない。
ここで考えたいのが、メイ首相が離脱期日の延期を求めた理由として国内で調整が付かない点を挙げていることである。つまり、BREXIT議論を先に進めるには何としても国内での調整を付ける必要があるということである。
そうした中で筆者が注目しているのが、ロンドン市内で5日(GMT)、爆発物が3つ発見されたという事件である。ヒースロー空港にシティー空港、そしてウォータールー駅で爆発物の入った封筒が発見され、それらにはすべてアイルランドの切手が貼られていたのだという。英警察当局はかつて英国でテロ活動を働いてきたアイルランド共和軍(IRA)によるものである可能性も視野に入れて捜査を始めていた。そうしたところ、12日(GMT)に新アイルランド共和軍(New IRA)を名乗る集団が犯行声明を出したのである。
いわゆる9.11以来、世界はテロの時代に入ったというのが安全保障を巡る議論で度々なされる。9.11自体がそうだったように、テロをきっかけとして国内世論が変わり、時の政権がそれまで外交政策を大きく変更することは良くあることだ。英国でも2000年以降、何度もテロ活動が生じてきた。たとえば2005年7月7日(BST)に生じたロンドン同時爆破事件がそれである。こうした事件を通じて、アラブ系テロリストと米英欧の対立という基軸が創られてきた。しかし、英国の年配層にとっては、テロ活動と言えばむしろアイルランドを想起する者も少なくない。英国とアイルランドは北アイルランドを巡り永年係争を繰り返してきた。たとえば1972年には「血の金曜日事件)」と呼ばれる爆破テロ事件が生じている。
そもそもBREXITを巡る論点の1つが、アイルランドの扱いであった。BREXITが実効となった場合、(英領)北アイルランドとアイルランド共和国の国境をどのように管理するのかという問題である。単にBREXITが実際に効力を持つようにするというのみならず、英国によるアイルランド植民地支配の歴史と関係するために非常に複雑になっているというわけである。
先々月(1月)にもロンドンベリーで自動車爆発事故が生じておりこれも新アイルランド共和軍によるものであるという可能性が指摘されてきたのである。無論、こうしたテロ活動がBREXITと直接的に関係しているという証拠があるわけではない。しかし、タイミングがあまりにも出来過ぎていると言わざるを得ないのだ。今後、新アイルランド共和軍によるテロ活動が続くこととなれば、いよいよ英国においてアイルランドとの訣別が“演出”される可能性があることを忘れてはならない。
英国の頭痛の種である「アイルランド=米国コネクション」とは?
BREXITを巡り、テロ事件を通じてアイルランドが新たな争点となりつつあることを指摘してきた。既に述べたように、このテロ事件がBREXITと明らかな連関をもつという直接的な証拠は無い。にもかかわらず筆者がこのような可能性を考えている理由が、英国の高級紙であるガーディアン紙がこのような報道を行ったからである:
“(註:米民主党のベテラン外交アドバイザーで)北アイルランドの平和化プロセスでワシントンにおける裏方役であったトリーナ・ヴァルゴが批判するところによれば、(ビル・ヒラリー)クリントン夫妻が娘のボーイ・フレンドによるアイルランド留学に当たり奨学金を得られるように斡旋する一方で、2008年の民主党内での大統領候補競争の中でオバマ大統領候補(当時)を支持したヴァルゴを処罰すべくその奨学金プログラムへのファンディングを停止したのだ”
なぜ筆者がこれに注目したのかというと、まずこの記事がガーディアン紙の独占報道(Exclusive)であるという点である。ガーディアン紙といえば、単なる高級紙というだけでなく、たとえばWikileaksによる一連のリークにも深く関わってきたという経緯があり、リークを通じた世論への波及力を相当有しているのだ。
次にタイミングである。この記事が発出されたのが今月5日(GMT)なのだが、この日は上述したロンドン市内における3つの爆発物発見事件に対する新アイルランド共和軍の関与可能性を英警察当局が発表したタイミングと一致するのである。
アイルランドと米国の関係は非常に深い。18世紀から19世紀にプロテスタント系アイルランドから米国への移民があった。それ以上にアイルランドと米国の関係において重要なのが、1845年から1849年にジャガイモ飢饉が生じた際の移民である。同飢饉は最終的に当時の全人口のうち少なくとも20パーセントが餓死するほどの苛烈な状況にあったにもかかわらず、当時の宗主国である英国が食糧輸入を禁止した中で、カトリック系アイルランド人の米国への移民が殺到した。同時期、米国への移民のうち約半分がアイルランド人だったという。
アイルランドでは毎年3月17日、聖パトリックの休日のイベントが催されるが、米国でもニューヨークやボストンでそれが催される。また前述したビル・クリントン元大統領や、ジョン・F・ケネディ元大統領、レーガン元大統領、さらにはオバマ前大統領などがアイルランド移民の子孫なのである。このように米国社会においてアイルランド移民はかなりの影響力を有しているのである。この史実があるため、英国がアイルランドとの関係でさざ波を立てようとすると、米国という巨大な壁が現れる可能性があるという訳だ。
こうした関係を踏まえると、前述した新たなアイルランド問題がBREXITとたまたまタイミングを一緒にしたというよりは、意図的なものを感じるということなのである。すなわち、英国としてはBREXITを進めるに当たってアイルランド問題を持ち出した。他方で歴史的関係を踏まえて、アイルランドを持ち出す以上、米国に対しても先制パンチを喰らわせた、という訳である。
おわりに ~「新アイルランド問題」が米大統領選に与える影響~
しかし、単なる英愛関係に、ここまでの議論を収束させてはならないのではないかという疑問も実は筆者にあるということを吐露しておきたい。では何を付け加えるべきか。それは、米大統領選との関係である。
来年2020年には米国で大統領選が行われる予定である。この選挙では注目すべき点が2つある。1つ目はオバマ前政権で副大統領職を務めたジョー・バイデンが大統領候補に立候補しているという点である。2つ目は先週14日(米東部時間)にベト・オルーク上院議員が突如として大統領候補への立候補を発表したという点だ。彼らに共通するのが、両議員が共にアイルランド系米国人であるという事実である。
(図表2 3月14日(米東部時間)に大統領選立候補を公表したベト・オルーク上院議員)
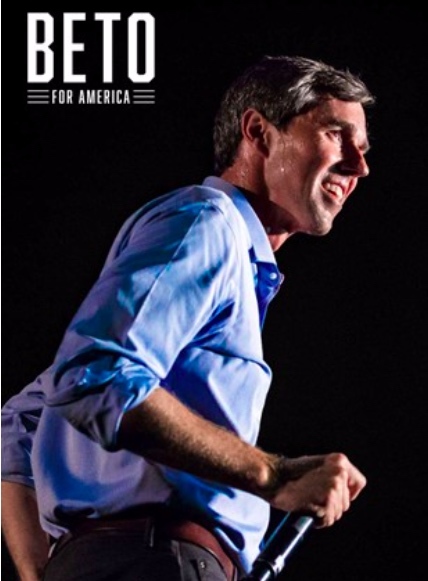
これとは対照的に、トランプ大統領とアイルランドの関係は良好とはいえない。昨年11月にトランプ大統領が訪愛の可能性を示唆してきたものの、最終的にキャンセルするという事態があった。これに対し、アイルランド当局側が同大統領の訪問がキャンセルされたと確報であるかのように公表する一方で、トランプ政権側はまだ最終決定したわけではないという齟齬があったことが知られている。
他方で、弊研究所がかつて調査分析レポートの中で分析したことがあるのだが、去る2016年の米大統領選当時、トランプ大統領候補(当時)が共和党の有力候補であった中で、選挙の4か月前に、ロンドン・シティ(City of London)との関係性が深い公的通貨金融機関フォーラム(The Official Monetary and Financial Institutions Forum)が「ドナルド・トランプの政治経済(The Political Economy of Donald Trump)」と題する報告書を公表しているのだ。これを読む限り、ロンドン・シティが就任以前からトランプ大統領候補に大きく注目していたと言えるのであり、逆に言えば、ロンドン・シティの対米見解を観察すれば、米大統領選の行く末について手がかりを得られる可能性があるというわけだ。
そうした中でここ最近、OMFIFがトランプ大統領による貿易摩擦問題について注文を付けているとでも言うべき見解を表明しているのだ。前回、トランプ大統領候補(当時)を持ち上げてきたものの、今回は徐々に彼を見限る方向性へとスライドしている訳である。そうした中で、アイルランド系移民の子孫たちが俄かに次回大統領選に向けて勢力を広げているのだ。
以上を踏まえると、このような考えが出来るというわけだ:
●当初トランプ大統領候補(当時)に対してロンドン・シティが支持する姿勢を見せてきたものの、いざトランプ大統領による米中貿易摩擦問題など各種政策の動向を振り返る限り、ロンドン・シティとしては姿勢の転換をしない限り同大統領を見限る可能性を検討している
●他方で、ロンドン・シティをも包含する英国としては、トランプ大統領に対する強力なライバルとなり得るバイデン元副大統領やベト・オルーク上院議員らアイルランド系移民へと牽制を行っており、トランプ大統領再選の可能性が完全についえたわけではない
●しかし、このままの姿勢を堅持する、特に財政政策と貿易政策を混在させる限り、逆にトランプ大統領の再選は無くなる可能性が在り、むしろバイデン元副大統領やベト・オルーク上院議員らが躍進する可能性がある
実はこれ以外にもOMFIFが「次の金融危機が2008年危機を凌ぐ可能性が在る(Next financial crisis may eclipse 2008)」というコメントを公表しているが、その中でトランプ大統領の政策スタンスがその危機を更に悪化させる可能性があるという見解を表明しているのである。BREXITに「次なる金融危機」、そして米大統領選。それらの行く末を見る上で、「アイルランド」に注目すべきであることを是非忘れないで欲しいというのが筆者の本稿での結論である。
株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA)
元キャリア外交官である原田武夫が2007年に設立登記(本社:東京・丸の内)。グローバル・マクロ(国際的な資金循環)と地政学リスクの分析をベースとした予測分析シナリオを定量分析と定性分析による独自の手法で作成・公表している。それに基づく調査分析レポートはトムソン・ロイターで配信され、国内外の有力機関投資家等から定評を得ている。「パックス・ジャポニカ」の実現を掲げた独立系シンクタンクとしての活動の他、国内外有力企業に対する経営コンサルティングや社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。
大和田克 (おおわだ・すぐる)
株式会社原田武夫国際戦略情報研究所グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー。2014年早稲田大学基幹理工学研究科数学応用数理専攻修士課程修了。同年4月に2017年3月まで株式会社みずほフィナンシャルグループにて勤務。同期間中、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーに出向。2017年より現職。




