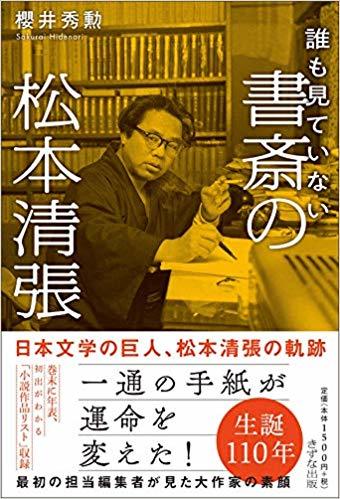(本記事は、櫻井秀勲氏の著書『誰も見ていない書斎の松本清張』きずな出版の中から一部を抜粋・編集しています)
作家、太宰治との四日間

清張さんとの出会いを語るには、まず私のことを書かないわけにはいかない。
私は清張さんが『或る「小倉日記」伝』で芥川賞を受賞した一九五三年(昭和二十八年)一月には、東京外国語大学のロシア語専攻の学生だった。すでに四年生で就職を決めなければならない最後の時期だった。
いまなら大学三年のうちに就職の内定を受けなければならないが、この頃は四年生の秋から入社試験が始まるという、そんな時代だった。私が一九四九年(昭和二十四年)に大学に入ったときは、たしか高校卒業生の五パーセントくらいの大学進学率だったので、就職の時期は中・高校生優先で、大卒はあと回しになっていたのかもしれない。
そして私は、あまり就職に熱心ではなかった。それというのもまだ戦後経済はどん底で、自分の進みたい出版社は想像外の競争率で、到底合格するとは思えなかったからだ。また、無謀にも、できればロシア文学の翻訳と小説を書いて、生計の道を立てたいと思っていた。実際、「作家群」という同人雑誌の創刊メンバーだったし、歴史小説を主として書いていた。
実はそうなったについては、一つの物語があった。私は旧制中学四年の冬、十五歳のときに、太宰治と思われる作家と四日間、一緒に過ごした経験をもつ。
この異常な経験は、その後つき合っていく作家とのあいだを、驚くほど深くしていったが、私の人生を決定づける強烈な印象を残したものだった。
第二次世界大戦末期、米軍の空襲で東京は焼け野原になったが、私は当時、母の実家のある千葉の大網という小さな町に疎開していた。
戦争が終わって、そこでの二回目の冬を迎えようという年の瀬のことである。私は両手の指のあいだに皮膚病が広がり、痒くて勉強もできないほどだった。医師は敗戦の日本には薬品がないので、硫黄泉に行くしか方法はない、と冷たかった。そこで硫黄泉を探したのだが、千葉県内には温泉そのものがなく、箱根の芦ノ湖の近くに、さびれた芦之湯温泉という硫黄泉があるので、そこで十日ほど入湯することになった。
インターネットを使えば一瞬に探し出せるのだが、当時は日本国内の情報は、すべて戦争遂行のため秘密扱いにされているという、いまでは信じられないような時代だった。
そしてこの温泉で、作家の太宰治と覚しき女性連れの男と出会ったのだ。それも数人入れば一杯という、小さな温泉風呂の中で。
「きみは毎日一人で、ここで何をしているのですか?」
痩せた中年の男は、毎日何回も温泉に浸かっている私を不審な目で見ていたようだ。
このとき私は訳を話したのだが、その男は納得しただけでなく、親切にも、「だったらヒマだろうから、私の部屋に遊びに来なさい」と誘ってくれたのだ。
敗戦後、一年半もたっていなかった頃なので、部屋には古ぼけたラジオが一台あるだけで、それもよく聴けない。かといって勉強も数時間すれば、飽きてしまっていた。
中学生にとっては冒険だが、大人になるチャンスと思ったのだろう。私は思いきって、二階の、その彼の部屋を訪ねたのだった。
出てきたのは思いがけなく、中年の和服の女性であった。
「櫻井さんね、どうぞお待ちしていました」
と、和服の女性は笑顔で、私を部屋に招き入れてくれた。私が男性に告げた名前を、ちゃんと知っている。
その男性は部屋に座っていた。私はまだこの男性に「何をしているのですか?」と聞いてはいなかった。というのもその頃の屈強な男たちは、ほとんど除隊してきた兵士ばかりだったので、仕事を聞くことは失礼に当たったのだ。
ところが部屋を見回してみると、大きなテーブルの上に原稿用紙が置かれている。もしかすると作家ではないか?というのが、私の最初の直観だった。
残念ながら私は名前を聞いたのか、仕事を尋ねたのか、それも遠い昔のことなので、忘れてしまっている。
ただ覚えているのは、小説家でありながら、名前を名乗らなかったこと。またあとで係の女性に、この男性のことを聞いたとき、
「ああ、○○さんですね」
と答えたのだが、太宰という名前ではなかったことだけは覚えている。
それだけではない。部屋を訪ねたのは四日間だったのだが、一体そんな長い時間、何を話していたのか、それも忘れてしまった。
ただ、「話していた」というより、「質問攻めに遭っていた」というほうが正しいかもしれない。それほど私の話を面白がってくれたのだ。
では私がなぜこの男を「太宰治」と思ったのか?
一つだけこれははっきり覚えているのだが、戦後に出てきた「あごに手をやる写真」そっくりのポーズをしていたことだ。
また私に「出版社という会社があるから、小説が好きなら、そういう道もある」と、将来の道のヒントをくれたことも覚えている。
この一言によって、私は詩と小説を書き始め、詩では、当時人気の詩人、白鳥省吾に少し認められて、興奮した覚えがある。小説は高校の文芸誌に初めての作品を書いて、文芸部を立ち上げたのだった。
私がこの男を太宰治と思ったのは、二年後の一九四八年(昭和二十三年)六月十三日の情死によって、初めて写真が小さく新聞に出たことによる。
この当時の新聞は紙の事情が悪く、タブロイド版に悪質の印刷という、そんな新聞しか出ていない時代だった。教科書も数枚の薄っぺらい紙でできたものだった。
その中で太宰治と山崎富栄の情死事件は、報道されたのだ。このときのボケた写真を見て「もしかしたら」と思うようになっていった。
のちに私は編集者になってから、太宰治と親友だったラジオドラマ作家の伊馬春部と会って、この温泉での数日間の話をしたことがある。
伊馬氏は私の義兄の仲人でもあったので、私の話を真剣に聴き入り、最後にこういった。
「櫻井君、それはきみにとって、間違いなく太宰だよ。もうこれ以上、本物かどうかなど、調べてはいけない。彼には年譜があるので、ほとんど足跡はわかっている。しかし、実はその数日間のことはわかっていない。だから、これ以後は絶対に調べてはいけない。きみは太宰治と間違いなく、数日間を過ごしたのだよ」
私はこの伊馬春部先生の言葉通り、それ以後、太宰治の足跡を調べてはいない。
そして、いつしか私は、あの日、笑顔で迎えてくれた和服の女性は太田静子だった、と信じるようになっていた。太田静子は太宰に、華族の日常を教えた愛人である。それが名作『斜陽』(岩波文庫)を生んでいる。
この太田静子は太宰治の子を生んでいる。作家の太田治子がその人だが、不思議な縁はつづくもので、私が六十代の頃、彼女とちょくちょく一緒に、講演して歩くようになった。
そのときに、この温泉での話をしたのだが、彼女は実にユーモラスで、私に向かい、「ちょうど櫻井さんが二人に会った晩に、私ができたのよ」と、まじめな顔で冗談をいうような女性だった。
松本清張を推した作家たち
私は学生時代、若い年齢にしては意外に古臭く、芥川龍之介や、劇作家の真山青果に夢中になっていた。真山の名前は、いまでは知る人もいないかもしれないが、歌舞伎で有名な『元禄忠臣蔵』の作者である。
木々高太郎の探偵小説も好きだった。木々はもともとは慶應義塾大学医学部の名誉教授で、本名を林髞といった。この林を二つに分けて「木々」とし、「髞」を高太郎としてペンネームとして使っていた。「髞」ではむずかしすぎて、ペンネームには合わなかったからだった。
この木々はすでにこの頃、探偵小説は古い、推理小説と呼ぶべきだと主張していて、松本清張のこの小説こそ“推理小説だ”として、高く評価していた。
“この小説”とは、他でもない。『或る「小倉日記」伝』である。
木々は親切にも、新人の松本清張を「三田文学」の同人として、いつでもこの雑誌に作品が書けるように、配慮してくれたのだった。
作家にとって発表の場をもてることほど幸せなことはない。
「三田文学」は、慶應義塾大学の文学部を中心に、一九一〇年(明治四十三年)に創刊された文芸雑誌である。初代主幹は、慶應出身の永井荷風であり、森鷗外、芥川龍之介ら既成の作家に発表の場を提供するとともに、久保田万太郎、佐藤春夫など、慶應義塾塾生の弟子たちを多く育てた。
その「三田文学」の同人にしたというのは、それだけ木々が松本清張の作品に期待していたということだろう。しかし、尋常小学校高等科しか出ていない清張さんにとって、日本の上流階級の牙城である慶應大学系の「三田文学」は、腰の座りのいい雑誌ではなかった。木々が同人を退めると同時に、清張さんも同人ではなくなった。
とはいえ、木々高太郎はこの時期の松本清張にとって、非常にありがたい存在だったと思う。
実はこの時期に、もう一人、新人の彼を押し出した作家がいた。永井龍男という作家だ。いまはもう、この名前を知る人は少なくなってしまったが、作家として文化勲章も取っている。また、文藝春秋の専務取締役まで務め、芥川賞、直木賞を裏方として支えた人でもあった。
私より二十七歳も上だったので、編集者としても雲の上の存在だった。
それほどの人でありながら、永井さんは松本清張と同じように、小学校高等科しか卒業していない。それだけの勉強しかしていないのだが、文学賞の名を並べたら書き切れないほどの受賞歴をもつ。
松本清張の受賞回のときは、直木賞の選考委員をしていたのだが、永井は「この作品は直木賞というより芥川賞向きではないか?」と述べて、賛成多数で芥川賞に回るという、珍しい経過を辿たどっていた。
これは現在の二賞の同日選考と違い、当時は直木賞と芥川賞の選考日が離れていたので、できた技でもあった。そして永井の慧眼通り、芥川賞を五味康祐と同時受賞という形になっていったのだ。まさに清張さんにとって、最高の選考委員といっていいだろう。
「時の氏神」という言葉がある。「喧嘩の最中に、最高の仲裁人が現れる」という意味だが、こちらは喧嘩どころか「芥川賞」という、作家にとって最高最大の文学賞の選考に際して、それまでまったく知らなかった二人の援助者が現れたのだ。
これは一種の奇跡というべきで、私は月刊「文藝春秋」の選考経過などで多少この裏話を知っていたが、これらの幸運が、その後、私の身にも振りかかってくるとは、まったく思ってもいなかった。
ところで、五味康祐の正しい表記は「五味康祐」である。しかし、当時は出版社によって「五味康祐」として出版されることもあった。五味は純文学作品では「五味康祐」を使い、それ以外では「五味康祐」で通していた。本書では、友人としての親しみをこめて「康祐」と表記させていただくことにした。