本記事は、田村秀男氏の著書『「経済成長」とは何か - 日本人の給料が25年上がらない理由』(ワニブックス)の中から一部を抜粋・編集しています
金融経済で若い人が実利を得るのは?―アメリカと日本
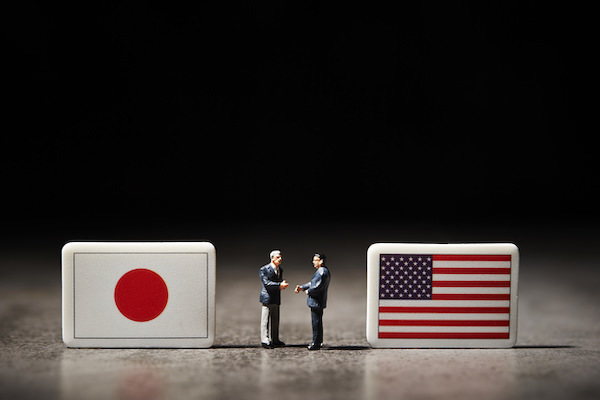
元手、つまりおカネがないと金融経済で実利を得ることは実際には難しいものです。いまから「頑張っていこう」という若い人は、家がお金持ちであればいいですが、それは一般的な話ではありません。先立つものがない若者が金融経済から恩恵を受けることはあるのでしょうか。
じつはアメリカと日本とでは、大きな違いがあります。
アメリカの場合、新技術や高度な専門性をもち、未知の要因が多くても創造、革新的な事業を展開するベンチャービジネスが推奨されていますが、ベンチャーキャピタルというベンチャービジネスに対する投資を主業務にする企業があります。一種の投資ファンドです。彼らは「あのベンチャーはいけそうだ」と思ったら、先物買いをやる。資本金出資をしますが、どのように投資回収をするかというと、株式市場に新規株式公開 ── IPO(新規公開株)といいます ── をやります。それがうまくいくと、一挙に株価が上がるのです。その差額でボロ儲けするというわけです。
ただし、ベンチャーですから、千三つという譬えがある ── 1,000品目出しても当たるのは3品目くらいの意 ── ように、0.3%くらいの確率でしか成功しません。ただ成功した場合の利益(キャピタルゲイン)が莫大ですから、それでうまくいくわけです。これがまさにアメリカ型の資本主義です。
何か可能性のあることをやろうとしている人たちに対して、特段支えてあげようという意志があるわけではなく、ここは儲かる可能性があると見込んだら、投資ファンドが融資するということです。そういうシステムが出来上がっているのです。
勿論投資ファンドも状況をウォッチし、積極的に情報入手しています。そして「あ、これはいける」と判断したら、すぐに投資です。
さらにテレビにも、一般の若者が「自分はこういう発明をしたから、こういう事業を起こしたい」とプレゼンする番組があります。目利きの投資のプロがそれを見ていて「よし、それ、買う」という内容です。
そういうふうにカルチャーとして、ベンチャービジネスに対する投資が根付いているのです。どこの馬の骨ともわからないような人の話でも、きちんと話を聞いて、「おっ、いいじゃないか。出資する」といって出資が成立してしまう。アメリカにはそういうカタチでチャンスがあるというわけです。
はっきり言って日本にはこういうカタチでのチャンスはありません。
誰かの紹介が必要とか、誰かが保証してくれなきゃダメとか、最初から機会が平等ではない。そんな日本には本来的に紹介や保証ができる立場の人がいました。それは銀行の支店長でした。高度成長期までの話です。バブル期になると土地さえあれば担保になりました。「アンタには土地があるから融資してあげよう」と。ところがバブルが崩壊して経済が縮小する ── デフレになる ── と、それもできなくなった。
都市銀行の支店長がやる気を失ったというか、審査のプロ、目利きがいなくなった。かつては支店長がまず有望な投資先を見立てて、それから本店の審査部がチェックして、「あっ、ここはいけますよ」と融資を決定していました。かつての日本はそれでいろいろな企業 ── ホンダやソニー、パナソニックなど ── が世界的な規模に成長していきました。彼らには土地の担保があったわけではありません。〝可能性〟しかなかった。こういう人たちに「やってみなはれ」「貸しましょう」……こういう信頼関係が日本の高度成長や新しい企業を支えたわけです。しかしいまのようなデフレ経済でゼロ成長だと、貸す側も慎重にならざるを得ません。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます
