本記事は、御手洗昭治氏の著書『ビジネスエリートが身につけたい 教養としてのダンディズム』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています
紳士が陥りがちなアイ・コンタクトの失敗

アイ・コンタクトの意外性~眼と視線~
日本語には、「目(眼)は口ほどに物を言う」、「目をかける」、「目をつける」、「目じりを下げる」、「目を三角にする」その他、目に関する表現が豊富にある。日本人は、フェイス・トゥー・フェイスでのコミュニケーションの際には、目を避けるように話しているが、その実、「上目づかい」にしっかり相手の顔色を伺っているようだ。
しかし、「目は心の窓」というように、対人コミュニケーションの際に、自分の目をわざわざ閉じて謙遜のシグナル・メッセージにするのが、日本文化の美徳でもある「伏し目」である。しかし、対人コミュニケーションや人前でのプレゼンテーションでは、相手(聴き手)の目を観る「アイ・コンタクト」が重要な要素である。
ただし、相手の目をのぞきこむのは、プライベート侵害となる。
暗黒街の帝王のアル・カポネを扱った『アンタッチャブル』という映画を鑑賞して気づくことは、親分のカポネは下っ端の子分たちには目もくれない。反対に子分たちは、常に親分格のカポネの一挙手一投足の挙動には注意を払ってはいるが、親分の目を直視していない。それが帝王学、または仁義だからだそうだ。
なお、多くの調査では、女性は男性よりも数倍見つめる仕草が多い。相手を、頻繁に見るし、また目を合わせる時間も長い。
「まなざし」のコミュニケーション
日本文化は、細やかでかつ微妙な「まなざしのコミュケーション」を日常化させていたという。日本文化で育った人は、日常の対人コミュニケーションで人と向かい合った状態では、お互いに目を見すえてはならないと教え込まれている。その理由は、相手と互いに目を結ぶことは、不作法な行為とみなされているからだ。したがって、われわれは、むやみに人と視線が合わないよう、互いに気を付けているのである。
小笠原流の作法の中には「目付の事」という項目が存在する。小笠原清信『日本を知る事典』(社会思想社、1971年)によれば、相手を見る際、「どこに目を置くのか?」については二つの種ケースがある。一つめが、真剣に人の話を聞く時であり、二つめは、気楽に相手の話を聞く時である。
井上忠司によれば、日本には古来から三つの目線に関する言葉があるという。「目通り・乳通り・肩通り」の三つである。相手の話を一言も聴きもらすまいとする場合には、相手の目の高さ、乳の高さ、肩の高さで、それぞれ囲んだ四角形の中を見ていれば良いという。
他方、気楽に相手の話を聞く場合には、「額のあたり・おへそのあたり・肩幅から一寸(約3.3センチ)の幅」を、それぞれ四角形に結んだ範囲内となっている。これをはずれると、相手から目をそらしているように映るという。
日本の人たちは、目の置きどころを、日常生活の中で知らず知らずのうちに、「無意識」に作法として実践しているのだ(『まなざしの人間関係』(講談社現代新書、1982年)。
文化とは、人びとが「無意識」のうちに身につけてしまった、行動・思考パターン(コミュニケーション)と定義されている。日本語の「みる」には、見・観・察・覧・診・視など多くの漢字が存在する。これらの漢字は、目を通して行う行為を分類すると同時に区別するために用いられている。
日本人は相手の目を見て話すのが苦手
目線は対人コミュニケーションの際、重要な位置を占めている。しかし、重要度は文化によって異なる。
ただし、日本の人びとは、伝統的に相手の目を見ないで話すようだ。面接の際にも相手のネクタイの結び目かノドぼとけ付近を見るよう指導されている。近年では、欧米の人と話す場合には、相手の目を見て話すようにと教えるようになったが、基本的には伝統的なまなざしの使い方は残っている。
しかし、欧米の人たちが、日本人と話していて最も気になるのは、相手の目を見ずに話す人が多いことだそうだ。アメリカ人の知人なども日本人の行動パターンで一番気になることだと述べている。対話の際、日本の人びとは相手のまなこをジーッと見て話すことは苦手のようだ。人を射すくめるように直視するのは失礼な行為だという気持ちがある。
欧米では、逆であり相手の目をしっかり見て話さない人物は、ずるい人、何か隠して信頼できない人という発想がある。アメリカの子供たちは、親に叱られる際、ジッーと親の目を見ながら話を聞いている。日本の子供たちはその逆であるため、文化の温度差を感じる。
また、同じアジア人でも日本人と韓国人とでは、まなざしの仕方に相違がある。韓国人同士の対人コミュニケーションのスタイルは、日本人同士のやりとりより、激しいものがある。そのため、彼ら同士で目を見て話す態度は日本人よりも強い印象を受ける。
「アイ・コンタクト」つまり、目線や視線は、人間関係を結ぶ上で、日常の対人コミュニケーションの基本的な行動パターンの一つであり、話し言葉以上に重要な位置を占めている。「仕草」や「まなざし」は各文化において異なる場合が多い。「仕草」や「まなざし」の背後には、各文化の人びとの深層心理が隠されている。異文化の人たちと円滑なコミュニケーションを行うためには、人間の心理や行動パターンへの洞察と文化と社会の関係の認識が必要である。
なぜ欧米文化ではアイ・コンタクトが必要なのか
では、なぜアイ・コンタクトが必要なのであろうか? 理由は以下のとおりである。
(1)相手への関与を示すバロメーターであるため (2)自信を伝達するため (3)自分の土俵に引き込むため (4)相手の気持ちや感情の情報収集をするため
ところで、ある調査では、人が見知らぬ他人から見つめられると「不審に思う」が第1位であり、「恐怖心」が第2位であった。また、親しい人から見つめられた場合には、男女の性別を問わず「うれしい」が第1位であった。
また、1対1の発表を行い、全体のうちの任意の3分間を切り取って調査された結果によると、平均で108秒(60%)以上の時間見つめられた場合、相手が「関心」や「リーダーシップ」を感じ取ったと報告されている。
イギリスの「鉄の女」と称されたマーガレット・サッチャー元首相やヒラリー・クリントン元大統領夫人のアイ・コンタクトを映像で測定してみると、興味深いことに、両者とも対談時間の8割以上もの間、相手の目を見つめていたことが分かった。
これは、別にサッチャー元首相やヒラリー・クリントンに限ったことではなく、欧米の政治家や起業家たちは、アイ・コンタクトのメリットと重要さを知っており、対人コミュニケ―ションの際など、実生活で活用している人物が多いからである。
ただ、アイ・コンタクトの量に関して言えば、男女差が少しあるようだ。欧米でも日本でも、同性同士では、女性の方が、相手の目をよく見つめている。ちなにみ、お互いしっかり見つめ合う文化は、欧米、アラブ諸国と南アメリカの文化圏である。
アイ・コンタクトにはルールがある
人の視線は、トライアングルを描きながら相手の顔の上を動く。
左右の目を行き来し、それから口元に下がるようだ。ある研究調査によれば、相手の顔を見ている時間の約75%は、左右の目と口を結ぶトライアングルの行き来に費やされている。そして、10%が額と髪、5%がアゴ、そして残りの10%がその他の部分を観ているという。
そこで、アイ・コンタクトのルールで大切なことは、「どこを、どのくらい、いつ見るのか」を知る必要がある。むろん、このルールもTPO(時と人と場所)による。例えば、欧・英・米文化社会において、くつろいだ社交の雰囲気の場では、視線はトライアングルの下の部分を伸ばし、トライアングルが鼻、口、アゴまで含むようにする。
ビジネスの商談の場合などは、視線は両方の目の端と鼻を結ぶトライアングルにフォーカスをあてる。そうすることで、商談の相手に対し、関心度、意欲、目的などを伝えることができる。
では、どのくらいのアイ・コンタクトをすればよいのか?
例えば、社交の場での出会いでは、相手に対して求める内容によって視線の使い方が異なってくる。親しみをキープしながら、親密な関係にまでなるつもりがないのなら、ビジネス・モデルの視線が望ましい。もっと相手に対して親密な関係を築きたいならば、アイ・コンタクト時間を長くすると良い。
次に、こちらが男性で相手も男性ならば、見つめ合うアイ・コンタクトの長さは、出会っている全体の時間60~70%である。それ以下の場合、相手はこちらを落ち着きがなく、自信に欠ける人物という印象を持ってしまう。また、こちらが男性で相手が女性の場合、アイ・コンタクトの長さは50%が望ましいという統計がある。
こちらが女性で相手が男性の場合、また、自分の考えなどを伝えたい時には、70%は必要であろう。また、相手を立て、自分の率直な意見を述べYESの回答を得たい場合などには、50%に下げた方がよい。なぜならば、アイ・コンタクトが増えると、相手に自分の主義主張を通そうとする、威圧的な自信家という印象を与えてしまう。
重要なことは、相手を受け入れるのか、歓迎するのか、それとも避けたいのか、また、あまり関わらないようにしたいかなどの目的によってアイ・コンタクトを調整することである。
いつアイ・コンタクトをするのか?
相手と信頼関係を築きたいなら、相手が話しはじめたら、即、アイ・コンタクトをすることが必要だ。そうすれば、相手は、自分の話を熱心に聞いてもらっていると思い安心する。
例えば、相手が話している時と、自分が相手に質問などをする時には、相手の目を見る必要がある。そして、自分が相手に対して話している時には、視線が宙に舞わないように注意しながら、時には相手から目をそらすことも必要だ。
なぜならば、相手は話し続けられると、戸惑いを覚え落ち着かなくなる。映画などを観ても、欧米の人は一般に自分が話している時には、相手から少し目をそらしながら話していることが分かる。
自分が話す時も、ナチュラルな話の途切れ目に、少し視線をそらしつつ、相手の視線を受け入れることが必要だ。自分の話が終わったら、視線を少し下げると、「次はあなたが話す番ですよ」というノン・バーバルなメッセージが伝わる。
見知らぬ者同士のアイ・コンタクトのルール
心理学者のアッシュクラフトとシェフレンの調査によれば、欧米において、見知らぬ者同士が通りですれちがい、3~4メートルぐらいの距離にアプローチした際、流儀として、お互いが相手の顔をながめ、すぐ視線をはずすという。
それ以上に長く見る行為は流儀違反である。万が一、見つめられた場合には、目礼をさりげなくするのがルールである。アメリカなどでは、偶然に両者が見続け、目が合った場合、「ハーイ」と言って軽く会釈するのがエチケットである。
では、相手がこちらに対してアイ・コンタクトを向けてこない場合はどうしたらよいのであろうか?
その場合、相手が内気なのか、不安を感じているのか、または、無関心なのかのいずれかである。そのいずれかの場合、まずはこちらから、アイ・コンタクトの数を減らすことである。
その代わり、こちらがアイ・コンタクトを向けた時、相手もアイ・コンタクトを返すように待つことである。こちらがアイ・コンタクトを減らすと、内向性で神経質な人は安心する。または、少し後ろに下がるのも良い。
あるグループの中の人物が、アイ・コンタクトの仕方を学び、グループリーダーになった事例もある。要は、意識してアイ・コンタクトに取り組む姿勢と意欲が評価されたのだそうだ。例えば、人と会って話す時、自らが先に相手に対して挨拶をし、話し始めると、相手は話し始めた人に対してアイ・コンタクトを通し視線を当てるようになる。
フランスの皇帝ナポレオンが残した格言、「一人の人間を仲間に引き込むには、その人の目に話しかけねばならない」は、洋の東西を問わず同じかもしれない。
人の視線は左から
人の視線は、左から見る癖があり、それから右へ移動する。
劇場の幕が左から開く瞬間、観客の視線は中央より左の下手の方に向けられる。歌舞伎の世界でも花道は中央ではなく、左の下手にある。観客が、自分のごひいきの役者に花束を贈るのにベストの場所という意味で、花道と呼ばれるようになった。目立つ場所の多くが中央から左手に始まる。ただ、劇場でオペラやバレエなどを見る場合、その席は中央より右手、つまり上手寄りの方が見やすいようだ。演劇を見上げたり見下ろしたりする視線も、左下から見上げ、左上から見下ろす癖がある。
ちなみに、ほとんどの画家が人の横顔を描く際、人が向きあっている絵を描くと左向きの方が、右向きのものより上手に描ける。日本の貨幣のお札に描かれている人物のほとんどが、左向きになっている。
異文化の目線とアイ・コンタクトのマナー
欧米文化では、相手の話を聞く際、また握手をする際には、相手の目を見つめ、自分が話す際には目線を少し下げるというのがマナーとなっている。
ハリウッド映画など欧米の映画を見ていてもそのことが分かる。アメリカ文化では、子供たちは人の話を聞く時に相手の目を見つめるように教えられる。したがって、学校で先生方が教壇に立つと、学生たちは先生に注目し、話を聞くという慣習になっている。日本の学生たちは、先生の話を聞く時には、視線を落としながら、静かに話を聞く。日本に来たばかりの欧米の先生や学生たちの不満は、日本の学生たちが目を見ながら聞いてくれないことだ。
自分が意見を述べる時には、少し視線をはずす。目線の動きを繰り返すことによって、押しつけがましい圧迫感を与えないようにすることが重要である。
「横目づかい」も避けた方が良い。目は顔ごと動かす習慣をつけることだ。「上目づかい」で相手の目を見ると、卑劣なズルイ人という印象を相手に与えてしまう。相手をジロジロ見るのも良くない。
なお、注意しておくべきことは、神経質な人、分裂症気味な人、憂うつな人は長く人の目を見ることができない。アメリカなどでは、1対1で対人コミュニケーションを行っている際、会話の時間の25~100%が相手の目を見つめることに費やされているという。
欧米のビジネスの商談は、まず相手に会ってアプローチすることが必要条件である。目と目のフェイス・トゥー・フェイスの対人コミュニケーションを通して、感情のつながりをつくってゆく。
日本文化において、人に紹介されても、ほとんど目線を合わせない人がいる。これは、社交マナーの点から言えば、失礼な行為であり、また相手方に不信感や不快感を与える。したがって、人に挨拶された場合には、相手の顔をちゃんと見て目線を合わせ挨拶を返す訓練が必要である。
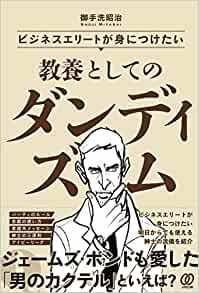
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
