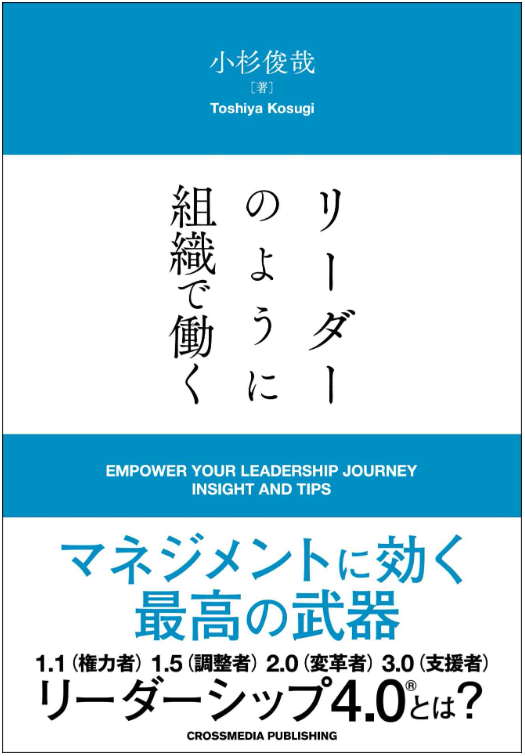本記事は、小杉俊哉氏の著書『リーダーのように組織で働く』(クロスメディア・パブリッシング(インプレス))の中から一部を抜粋・編集しています。

両利きの経営とは
両利きの経営の重要性の認識が広がっている。これは、ひとことで言えば「二兎を追う」ということだ。二兎とは次の通りだ。
- 知の深化:自身・自社の持つ一定分野の知を継続して深掘りし、磨き込んでいく行為
- 知の探索:自身・自社のの既存の認知の範囲を超えて、遠くに認知を広げていこうとする行為
両利きの経営が行えている企業ほど、イノベーションが起き、パーフォーマンスが高くなる傾向は、多くの経営学の実証研究で示されている。(『両利きの経営』チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン著/東洋経済新報社)
言うまでもなく、知の深化は日本企業が得意とするところで、新卒一括採用、社内育成、単一な価値観を持った日本の綺語の風土に合っている。一方、「知の探索」は、多様なバックボーン、社内外の知の組み合わせが必要であり、これがまさにダイバーシティが組織内において必要だという根拠ともなっている。
さて、では日本企業は昔から知の探索が苦手だったのだろうか。確かに社内においては知の深化をひたすら進めてきたからこそ、第二次大戦後世界的な多くの企業を生み出してきた。しかし、それだけでは十分に説明できない。なぜ、多くのイノベーションを生み出してきたかというと、社外を探索し、しかも同業ではなく他業界にも広くその視野を広げヒントを得て、社内に取り込むということをやってきたのだ。
たとえば、次のようなことだ。
- トヨタ自動車を世界的企業に押し上げた、トヨタ生産方式の中軸とも言えるカンバン方式。これは、米ウォルマートの「売れ行きに応じて必要な分だけ調達する」というやり方からヒントを得て、もの作りに応用したもの
- ヤマト運輸は巨人である日本通運になかなか太刀打ちできなかったが、個人宅配に特化し、業界No.1の地位を占めるようになったのは、吉野屋の「牛丼一本で勝負する」ということからヒントを得たもの
- TSUTAYAを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブは、会社が軌道に乗らず苦しみ、ついには十一といわれる高利貸しにまで手を出してしまったが、この消費者金融のやり方にヒントを得てCDレンタルに応用し、大成功を収めたもの
視野を広げたことによってイノベーションが起こり、大躍進を遂げた日本企業は数多い。「イノベーションは遠方よりやってくる」「イノベーションをマネージすることはできない」「次のイノベーションは誰にもわからない」などイノベーション(新結合)を説明する言葉はたくさんある。
このイノベーションは、オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーターが唱えた理論が有名だが、特に『経済発展の理論』(1934年)で、新結合(ニュー・コンビネーション)という言葉で説明し、世界中に大きな影響を与えた。
また、その後『イノベーションのジレンマ』(1997年)で実業家、経営学者のクレイトン・クリステンセンは、創造的破壊(クリエイティブ・ディスラプション)という概念を唱え、既存事業の延長線上では画期的なイノベーションは起きないことを明示し、現在に至るまで世界中の企業に大きな影響を与えている。
さて、お気づきだと思うがここで両利きの経営の話を持ってきたのは、デュアル・システムなくして成功した大企業にイノベーションは起こらないということを補強したかったからだ。さらには、この二兎を追うためには、マネジメントとリーダーシップの二刀流が必要だということでもある。
金太郞飴のようにどこを切っても同じ同質性の高い純粋培養集団の文化の中ではイノベーションは起こらない、だからダイバーシティが必要だということでもあり、1人ひとりに自律主体的に働いてもらう必要があるということだ。そして社内外のネットワークを広げていくこと、アライアンスを組むことが、企業が新しいものを生み出し、生き残っていくためには必須であるということをお伝えしたいのだ。
企業が女性の活躍推進を進める理由は外圧から、中途(経験者)採用を行うのは人手が足りないから、とだけ考えているような企業の未来は危うい。同様に、副業解禁するのは社員を辞めさせないためだけではない。留職やレンタル移籍を行うことにより社員を修行へ出すこと、OBOGのアルムナイネットワークを整備し、出戻りを歓迎すること、すべてそれは経営・人事戦略上の必要性からだ。