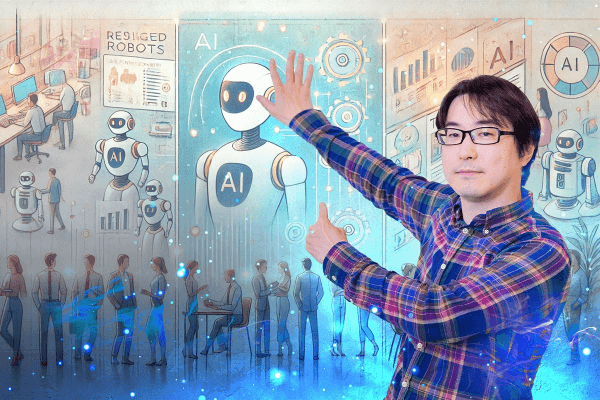
研究開発を担うR&D部門のエンジニアの素顔を映す企画「エンジニアのヨコガオ」。今回は、2014年入社の中堅エンジニア・斎藤敬太が登場します。彼を表すキーワードは、「社会貢献」と「根気」と「魔法」。その人物像を紐解きます。
工学部化学工学科を卒業後、IT未経験で2014年に株式会社シーエーシーに新卒入社。OJTを通じてスキルを磨きながら、IT関連の国家資格を複数取得。入社2年目からローコード開発プラットフォーム『AZAREA』の改善・保守や関連プロジェクトに携わり、現在はAI-OCRなどの開発に取り組む。
もっと世の中のために役立ちたい

――なぜIT業界、そしてCACを選んだのですか?
大学では化学工学を学び、研究にも熱中していました。ただ、それを仕事にすることには迷いがあったんです。「もっと世の中の役に立ちたい」という思いが常にありました。では何を仕事にすべきかと考えた時、化学、医療、金融、物流などあらゆる分野で活用されているITに関わることが、世の中の役に立つ近道だと思いました。
ITはほぼ未経験でした。でも、仮説を立て検証し、また新しい仮説を立てて実証していく、そんなトライ&エラーのプロセスに、化学の楽しさを感じていたんです。それはITの分野でも生かせるはずと思っていたので不安はありませんでした。
最終的に、独立系SIerとして元請けの仕事が多く、大規模なプロジェクトに携わることができ、個人の裁量が大きいこと。そんな環境に魅力を感じ、CACを選びました。
――入社後、どのようにしてスキルを身につけていったのですか?
入社前から『ITパスポート』の資格試験の勉強をしていましたが、入社後の研修では、与えられたお題に対し、プログラミング経験がある同期は驚くほどの早さでコードを書き上げます。一方、自分はまともにコードを書けず、置いてけぼり。でも、だからこそ火が着いたのだと思います。「負けてられるか!」って(笑)。
スキルの差を埋めるため、まずは『ITパスポート』で基礎を固め、実務で知識を磨きながら、上位資格に挑戦する。この繰り返しでステップアップを図り、最終的には基本情報技術者、応用情報技術者はもちろん、データベーススペシャリストなど計6つの資格を取得しました。
その過程で大きかったのは、入社1年目から現場経験を積めたこと。研修後は食品会社の既存システムの保守に関わりましたが、単なる保守にとどまらず、お客様のもとへ足を運び、直接困りごとを伺う機会が多くありました。持ち帰った課題をもとに設計し、対応を進めるという形で、小規模ながらも開発プロセス全体を経験できました。実際の課題を自分の技術で解決する。その実感を早い段階で持てたことは、自分の成長につながったと感じています。
入社後、最大の試練に不屈の精神で立ち向かう

――入社2年目の2015年には、『AZAREA』をメインに扱う部署に異動されていますね。
『AZAREA』は、システム開発を支援する当社独自の開発プラットフォームです。Webシステムのローコード開発プラットフォームであるWebapp Platformと、ETLのローコード開発プラットフォームであるETL Platformが存在します。その部署で約4年間、Webapp Platform部分の改善・保守を担当し、『AZAREA』を活用したプロジェクトの支援にも関わりました。
CACがSIerとして蓄積してきたノウハウを『AZAREA』としてプラットフォーム化することで、当社が、ひいてはお客様自身がより品質の高いシステム開発をよりスピーディーに行うことができるようになる。そこに、やりがいを感じていました。
とはいえ、配属当初は入社2年目でしたから、目の前の仕事についていくのに必死で…。『AZAREA』本体の知識を頭に入れ、ベテランの方が実装されたソースコードを見られるだけ見て、それを参考に自分でコードを書いては先輩にレビューしてもらう、という繰り返しでした。
――『AZAREA』担当として最も苦労したことは?
のちにR&D本部に異動してからも『AZAREA』に関わっており、そこでの作業ではありますが、『AZAREA』が生成するWebシステムのクライアントサイドを“Flutter化”する作業でしょうか。お客様がこれまでHTMLやJavaScriptといった従来型のコードで開発していた部分を、「Flutter」という新しいソースコードに置き換える作業です。Flutterを使うことで、従来はWebアプリ、iPhoneアプリ、Androidアプリ、Windowsアプリと、それぞれ別々に書かなければならなかったコードを、ひとつのソースコードで管理できるようになります。
※Flutterとは、Googleが提供するスマートフォンアプリを開発するためのフレームワーク
ですが、当時は膨大なコードを一つひとつFlutterに置き換えなければならず、作業量は多く、難易度も高かったんです。しかも、約2年という短期間で完了させる必要もありました。大げさかもしれませんが、当時は何としても喰らいつく気持ちでやっていたと思います(笑)。
――厳しい環境のなかで、何が支えになっていましたか?
『AZAREA』は、システム開発に携わる多くの人たちの助けになるという意味で、“絶対に価値がある”と感じていました。また、入社当時はコーディングがほとんどできない状況でしたが、世の中に役立つシステムを作るためには、エンジニアである以上、コーディングができないと何も始まりません。『AZAREA』に対する信頼感と、自分に対する危機感が、一番のモチベーションになっていたと思います。
開発現場で見えた、AIのリアルとポテンシャル

――現在、所属されているR&D本部ではどのような業務を担当していますか?
『AZAREA』関連の業務を引き続き担当しつつ、主にOCRなどドキュメント認識の分野で、AIそのものの開発やAIを利用したアプリケーションの開発に携わっています。
私がR&D本部に異動したのは2019年です。当時、AIは今ほど一般的ではなかったと思いますが、その頃、当社では外観検査の省力化をめざすAI開発に着手していました。構造物の破損や製品のキズをAIで自動検知するという話を社内で聞き、「そんなことまでできるのか⁉」と驚き、同時に「やってみたい!」という気持ちが湧きました。その希望が叶い、AI開発を担当するR&D本部への異動につながりました。
――念願のAI開発に携わったご感想は?
最初に担当したのは、AI-OCRを使って任意の環境で撮影された身分証を読み取るシステムの開発でした。ただ、AIは一度作れば終わりではなく、試行錯誤の連続です。例えば、20年ほど前のケータイで撮ったかのような解像度が低い身分証の画像、布団の上で撮影された画像、背景と身分証の色が似すぎて境界が曖昧なものなどのケースでは認識精度が大きく落ちます。課題が見つかれば、そのたびに学習データを追加し、AIにひたすら学習させ、少しずつ精度を高めていく。AI開発の現場は、実際はすごく地道で泥くさい。それが最初に感じたことでした。
ただ、精度が着実に上がっていくことを実感できるのは楽しいですし、システムを完成させ、納品したあと、お客様から「読み取り精度がすごい」「おかげで作業工数がかなり減った」と言われると、報われた気持ちになります。
私が携わるAI-OCRの技術は、紙の管理と紙の電子化という煩わしい作業をAIが肩代わりすることで、人がより創造的な業務に集中できる環境を提供します。それは、“人を察し、人を活かし、人を健やかにする”技術として当社が掲げる「HCTech®︎」のコンセプトにも合致するものです。
――斎藤さんにとって、AIとはどういう存在ですか?
ひと言でいうと、「魔法のような存在」です。AIがなかった時代、システム開発では人が何度も検証を重ね、ロジックや数式を一から組み立て、少しでも対象が変わるとまた作り直し、という作業が繰り返されていました。しかし今では一定量のデータがあれば、AIが学習し、最適なロジックや数式を自動で導き出してくれる可能性が十分にあります。
今後はますます、人が個性を発揮できる活動に注力できるようになると思います。もっといえば、やりたい仕事や遊びも、膨大なデータから最適なものを見つけ出し、提案してくれるAIが登場するはずです。言葉の壁がなくなり、異なる国籍の人たちが協力し合い、楽しそうに活動する社会も実現するのではないでしょうか。そんな未来が、すでに始まりつつあることを感じています。

――そんな未来の構築にエンジニアとして関わる斎藤さんですが、プライベートもなかなかアクティブと聞きました。最近、2泊3日のドライブで2000kmを走破したとか?
ええ、いろんな車に乗るのが好きで、カーシェアを使って旅行するのが趣味なんです。2025年1月には、千葉県を出発し、奥多摩のハンバーグ屋さんに寄ってから、山梨→淡路島→四国→広島へ、2泊3日で往復2000kmを走りました。本当は北九州まで行くつもりだったんですが、淡路島で渋滞にハマってしまい、やむなくルートを短縮しました。
――助手席には誰が…?
誰もいませんよ(笑)。キャンプは友達と行きますが、ドライブは自由気ままにしたいので、基本、ひとりです。
*
ユーモアを交えながら、ときにアツく、ときに先端技術に素直に感動を示しながら話す斎藤さん。負けん気の強さを力に変えて、これからも新しい分野の開拓を目指していくことでしょう。

技術者が気になる技術
最近、ハッとさせられたのが、「空気から電気を作る」という技術です。2年ほど前に、オーストラリアのモナシュ大学の研究チームが発表し、『Nature』誌にも掲載されました。この研究は、空気中の微量の水素を電気に変換する酵素を発見したというものです。
その酵素は「Huc」と呼ばれ、大気中の水素濃度よりもはるかに低い濃度でも発電ができるという特徴を持っているそうです。さらに、「Huc」は土壌に生息する細菌から抽出でき、細菌は大量に増殖させることができるとあって、持続可能な電力源としての可能性も秘めています。
ITやAIは生活をさらに便利にする力を持っているのは間違いありませんが、それも電気があってこそ。「空気から電気をつくる」技術の今後の動向には、期待を込めて注目しています。

(提供:CAC Innovation Hub)
