本サイトにはプロモーション広告を含みます。なお、掲載されている広告の概要や評価等は事実に反して優遇されることはありません。
株式や投資信託など、証券投資をする際に利用するのが証券会社だ。しかし、証券会社によってサービスやコストが大きく違うことを把握しているだろうか。これから投資をはじめる場合は、自分に合った証券会社を選ぶことが重要だ。
この記事ではネット証券として人気の高いSBI証券と楽天証券をサービスや取引ツール、手数料コストなどの面から比較していく。証券会社選びの参考にしてほしい。
IPO投資ならSBI証券がおすすめ
SBI証券と楽天証券の比較表を以下にまとめた。国内株式手数料手数料等では大きな違いはない。しかし、新規上場株式の取り扱い数であるIPO実績と、取り扱っている外国株の国数ではSBI証券が勝っている。

|

|
||
|---|---|---|---|
|
国内株式 取引 手数料 |
10万円 | 99円 | 99円 |
| 50万円 | 275円 | 275円 | |
| 100万円 | 535円 | 535円 | |
|
米国株式 取引手数料 |
約定代金の 0.45% |
約定代金の 0.45% |
|
| 投資信託本数 | 2650本 | 2613本 | |
| IPO実績 | 2019年 | 82社 | 26社 |
| 2020年 | 85社 | 38社 | |
| 単元未満株 | ○ | △(※) | |
| 取扱外国株 | 9ヶ国 | 6ヶ国 | |
2023年8月29日時点
上の表で示されている通り、SBI証券の強みとして、IPO実績が勝っている。楽天証券以外のネット証券と比較しても、トップクラスである。IPOで成果を目指したい方は、SBI証券での口座開設がおすすめだろう。
SBI証券と楽天証券はどんな証券会社
SBI証券と楽天証券はそれぞれどんな特徴を持った証券会社なのか、確認してみよう。
SBI証券
SBI証券は国内株式個人取引シェアNo.1のネット証券。さらに「みんなの株式 2021年ネット証券年間ランキング第1位」を獲得しており、ユーザーから絶大な評価を受けている。
また、Tポイントを貯めて・使えることもできるので、お得に投資を開始することが可能である。
使いやすかったです 有名な会社なので安心して始める事ができました。
引用元:価格.com
新卒時代から使っていますが、iDeCoや米国株の取引しやすくメインに使っています! 投資初心者向けとあって取引画面、ポートフォリオの画面が年々見えやすくて便利です。
引用元:価格.com
PC持ってなくてスマホでの利用ですが、スマホ対応画面と言うのが有りますがとにかく画面遷移複雑、字が小さくなったり戻るボタン不明なページあったり、とにかく使用するのが苦痛です。スマホでしか利用しない方は辞めた方が良いです。
引用元:価格.com
過去の履歴を見るのが、わかりづらい。個人の好みもあるのでしょうが、画面の色使いでピンクが多すぎる。資産全体が一画面でわかるところは、良い。
引用元:価格.com
楽天証券

楽天証券は楽天グループの証券会社であり、2019年口座開設数No.1のネット証券である。楽天証券は多彩なキャンペーンを実施していることでも有名であり、口座開設をするだけでお得なキャンペーンも存在する。
また、楽天証券と楽天銀行を連携させることによって、銀行普通金利預金金利が最大5倍にアップするなど、他サービスの連携が魅力的である。
もちろん楽天ポイントを投資で貯めて・使えるので、楽天ユーザーは口座開設しておきたいネット証券である。
投資信託で定期利用しています。ファンドも安定して自分としては安心度の高い証券会社だと思います。長期スパンで投資を続けるなら楽天証券一押しです。
引用元:価格.com
クレカ投資のポイント還元率とSPU条件が改悪されましたが、iSpeedやMarketSpeed2の使いやすさが最高に良いです!また、日経テレコンや各種マネー本が無料で読めるのも最高ですね!これからも引き続き使い続けていきたいと思います。
引用元:価格.com
投資信託 楽天カードを持っていて、楽天銀行の口座を持っていればポイントが使えるなどのメリットはある。肝心なのは一番リスキーなコースにしているが、とにかく増えない、ということ。現在220万の運用でー8万円。どうなの?LINE証券に移そうか考え中。
引用元:価格.com
楽天カードや楽天銀行との連携によるポイント付与や利率補助等、様々な特典があったのですが、相次ぐ改悪により、付与されるポイントは大きく削減され、また楽天銀行の利率補助も、他証券会社の行う補助と比べても見劣りするようになりました。これらの発表の年の始まりの頃に発表し、NISAの切り替えをさせないという魂胆が見え見えであるところも、嫌気がします。また提供される情報サービスは特にプアであると感じます。
引用元:価格.com
| 初心者におすすめの 証券会社ランキング |
証券会社の特徴 | 手数料(税込) | 外国株 | IPO銘柄数 (2021年実績) |
口座開設に 要する期間 |
つみたてNISA 取扱銘柄数 |
積立できるクレジットカードの特徴 | カード年会費 | クレカ積立の 還元率 |
カード発行日数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | ~20万円 | ~50万円 | ~100万円 | 取扱い有り | 米国株取扱数 | 米国ETF取扱数 | |||||||||||
|
1 |
 口座開設をする
口座開設をする
|
楽天サービスとの連携に強み | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 6カ国 | 4,759銘柄 | 324銘柄 | 74社 | 最短 翌営業日 |
◎ 181 |
 申し込む
申し込む
|
楽天市場でお得!クレカ人気No.1 ※保有者が日本一 |
◎ 無料 |
◎ 1.0% ※22/9買付分より一部変更 |
約1週間 |
|
2 |
 口座開設をする
口座開設をする
|
口座数が国内No.1 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 9カ国 | 5,130銘柄 | 339銘柄 | 122社 | 最短 翌営業日 |
◎ 183 |
 申し込む
申し込む
|
コンビニ大手3社・マックで5%還元 | ◎ 無料 |
◯ 0.5% |
最短5分 |
|
3 |
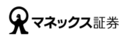 口座開設をする
口座開設をする
|
クレカ積立のポイント還元率1.1% | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 2カ国 | 4,561銘柄 | 345銘柄 | 64社 | 最短 翌営業日 |
◎ 152 |
 申し込む
申し込む
|
お買い物でも1.0%還元 | ◯ 550円 ※条件付きで無料 |
◎ 1.1% |
約10日程度 |
| 4 |
 口座開設をする
口座開設をする
|
初心者でも簡単!LINEから投資を始められる | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | - | 122社 | 最短 翌営業日 |
◯ 33 |
- | - | - | - | - | ||
| 5 |
 口座開設をする
口座開設をする
|
auユーザー 必見 |
99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 1カ国 | 1,522銘柄 | 206銘柄 | 42社 | 最短 5営業日 |
◎ 171 |
 申し込む
申し込む
|
Pontaポイントが貯まる | ◎ 無料 |
◎ 1.0% ※条件付きで最大5%に |
最短4日程度 |
SBI証券と楽天証券の対応とサービス
SBI証券は、約512万口座 (2020年3月末時点)、楽天証券は約500万口座 (2020年12月時点)を持つ、日本でも有数の非対面型ネット証券会社だ。はじめにSBI証券と楽天証券の対応やサービスを表で確認してみよう。
| SBI証券 | 楽天証券 | |
| 現物株取引手数料 (100万円まで) ※1日の取引合計額にかかる手数料 |
0円 ※アクティブプラン |
0円 ※いちにち定額コース |
| 現物株取引手数料 (200万円まで) ※1日の取引合計額にかかる手数料 |
1,238円(税込み) ※アクティブプラン |
2,200円(税込み) ※いちにち定額コース |
| 外国株取り扱い | 米・中・韓・ロシア・ベトナム・インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア | 米・中・インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア |
| 取り扱い投資信託数 | 2,680本 ※2020年10月現在 |
2,700本 ※2020年12月現在 |
| ポイント制度 | ・取引に応じてTポイントを付与 ・投信買付にTポイント利用可 |
・取引に応じて楽天ポイントを付与 ・投信買付に楽天ポイント利用可 |
上の表で示されている通り、楽天証券はポイントのサービスが充実しているのが特徴である。 ポイントを貯めて、おトクなサービスを利用したい方は楽天証券での口座開設がおすすめである。
SBI証券と楽天証券の取扱商品の違い
国内株式や外国株式、投資信託などを扱っているのは同じだ。具体的な違いについて確認していこう。
外国株式の取り扱い国数
SBI証券は「米・中・韓・ロシア・ベトナム・インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア」の9ヵ国。 楽天証券は「米・中・インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア」の6ヵ国だ。
「様々な国の株式を取引したい」と考えている場合は、SBI証券がおすすめといえる。
投資信託の取扱数
投資信託の取り扱い数は、SBI証券が2,680本(2020年10月時点)、楽天証券は2,700本(2020年12月時点)とほとんど差がない。 選べる投信信託の多さから考えると、SBI証券、楽天証券どちらを選んでもよいだろう。
SBI証券と楽天証券の初心者向けサービス
次に、SBI証券と楽天証券の初心者向けサービスについて解説する。
初心者向けセミナーや動画
投資初心者は、まず投資の仕方や証券会社サイトの使い方を学ぶことが必要だ。SBI証券と楽天証券では、初心者の学習用にどのようなツールを提供しているのだろうか。SBI証券では以下のような初心者向け学習ツールを用意している。
・初心者向けセミナー (オンライン・対面)
・動画による操作ガイド)
・YouTube内で市況や投資についての紹介動画配信)
・公式サイト内で初心者向け投資基礎講座ページを公開)
SBI証券の初心者学習ツールは、まったく投資をしたことがない人でも分かりやすいようにさまざまなものが取りそろえられている。その中でも特筆すべきは、公式サイト内での初心者向け講座だ 。
「日経平均株価とは?」 というところから外国株、チャートなど基礎から学ぶことが可能となっている。
また、YouTubeでは市況の解説も行っており、投資上級者でも満足できる内容といえる。
初心者の中には、「実際に専門家に会って話を聞きたい」という人もいるのではないだろうか。2021年現在、コロナ禍などで厳しい情勢だが、SBI証券では少人数制の初心者向けセミナー も開催している。
続いて、楽天証券の初心者学習ツールについても確認してみよう。
・初心者向けセミナー (オンライン)
・公式サイト内に初心者向け「投資の仕方」ページ
・公式サイト内で初心者向け動画 を公開
・楽天証券運営サイト「トウシル」内で市況・投資についての情報を公開
楽天証券は、動画が非常に充実しているのが特徴だ。さまざまなテーマを数回のシリーズとして紹介しているため、時間が空いたときに少しずつ視聴することができる。
また、楽天証券が運営するサイト「トウシル」 内では、経済や投資の専門家が市況や投資情報を動画で解説するコーナーもある。
投資について、さらに理解を深めたい人はこちらも確認すると良いだろう。ちなみに、楽天証券でも初心者向けセミナーをオンラインで開催している。自宅でゆっくりと話を聞きたい人におすすめだろう。
株式投資関連ニュースの提供
株式関連のニュースや情報について「どの程度提供しているか」も確認したいところだ。SBI証券では、YouTubeで毎月の相場見通しをチェックすることができる。また、公式サイトのトップページからは、投資レポートや各金融商品の動向についてのニュースも確認可能だ。
公式サイトのトップページに行くだけでどのようなニュースが出ているのか、タイトルだけでも確認できるのは非常に便利だろう。
楽天証券では、初心者学習ツールとしても先述した「トウシル」で銘柄の選び方などの情報を発信している。毎朝8時更新の専門家による市況解説記事もあるため、活用すると良いだろう。
ただ、使いやすさからいえば、公式サイトのトップページから情報の見出しだけでもチェックできるSBI証券のほうが優れているといえるかもしれない。
SBI証券と楽天証券のポイントサービス
SBI証券では「Tポイント」、楽天証券では「楽天ポイント」が取引に応じて付与される。違いを見ていこう。
ポイントの付与条件
【SBI証券】
SBI証券のTポイントは、以下の条件で付与される。
・新規口座開設時:100ポイント
・株式現物取引:月間合計手数料1.1%相当のポイント
・投信保有残高(月間平均保有額):残高1,000万円未満で年率0.1%相当のポイント、残高1,000万円以上で年率0.2%のポイント
【楽天証券】
楽天証券の楽天ポイントは、以下の条件で付与される。
・新規口座開設時:なし※ ただし、「ご家族・お友達紹介プログラム」経 由で総合取引口座を開設、1,000円以上入金した場合200ポイントを付与
・株式現物取引 :月間合計手数料1%相当のポイント※ 超割コース選択時
・投信保有残高 :月末時点の残高がはじめて10万円に到達した場合は10ポイント、はじめて30万円に到達した場合は30ポイントなど
株式投資を頻繁に行う人は、SBI証券のほうが貯まりやすいといえるだろう。しかし、「楽天市場でよく買い物をする」という人は、楽天証券を選んでもよいだろう。
なお、楽天証券には「ご家族・お友達紹介プログラム」というものがあり、紹介された人が口座開設と入金を行うと200ポイントが紹介者・被紹介者双方にプレゼントされる。知り合いや家族がすでに楽天証券口座を持っている場合は、このプログラムを利用してポイントをもらうのもおすすめだ。
ちなみに、SBI証券、楽天証券ともに貯めたポイントは買い物だけではなく、投資に利用することもできる。
出典元:SBI証券|株・FX・投資信託・確定拠出年金・NISA
出典元:株ポイントプログラム | サービス案内 | 楽天証券
キャンペーンについて
2社とも、多くのキャンペーンを行っているが、株式関連に限ると次のようなものがある。 ※2020年12月現在
【SBI証券】
「米国株式NISA買付手数料キャッシュバックキャンペーン」
キャンペーン期間中の米国株式個別銘柄の買付手数料全額キャッシュバック
「12月優待銘柄デビューキャンペーン」
国内株式を初めて取引した人を対象に12月株主優待銘柄の現物取引手数料をキャッシュバック
(1人当たり上限5,000円)
【楽天証券】
「現物取引デビューで200万ポイント山分けキャンペーン」
キャンペーン期間中にエントリーし初めて国内株式の現物取引を行った人に200万ポイントを山分けでプレゼント
「米国株式冬のボーナス250万ポイント山分けキャンペーン」
キャンペーン期間中にエントリーし、米国株式(ETF・ETN含む)を買付した人に250万ポイントを山分けでプレゼント
キャンペーンは期間限定が多い傾向だ。
また、自動的にプレゼントがもらえるわけではなく、事前エントリーが必要なものもある。 これらの情報を見逃がさないためにも、日ごろから公式サイトやメールマガジンをチェックして、参加できそうなキャンペーンを探すようにするとよいだろう。
SBI証券と楽天証券の手数料コストと分析ツールを比較
SBI証券と楽天証券の手数料は、どのような違いがあるのだろうか。投資する際に利用する分析ツールについても確認してみよう。
株式投資の売買手数料の違い
株式投資の売買手数料は、以下のようになっている。(※手数料は税込み)
【SBI証券】
・スタンダートプラン:1回の約定ごとに手数料がかかるプラン
| 1注文の約定代金 | 手数料 |
| 5万円まで | 55円 |
| 10万円まで | 99円 |
| 20万円まで | 115円 |
| 50万円まで | 275円 |
・アクティブプラン:1日の約定代金合計額に手数料がかかるプラン
| 1注文の約定代金 | 手数料 |
| 100万円まで | 0円 |
| 200万円まで | 1,238円 |
| 以降100万円増加ごとに | 295円ずつ増加 |
1日何回も取引を繰り返したり100万円までの取引しかしなかったりする人は、アクティブプランがお得だろう。ただし、約定代金が100万円を超えると手数料がかかるため、注意が必要だ。
次に、楽天証券の手数料だ。
【楽天証券】
・超割コース:1回の約定ごとに手数料がかかるプラン
| 1注文の約定代金 | 手数料 |
| 5万円まで | 55円 |
| 10万円まで | 99円 |
| 20万円まで | 115円 |
| 50万円まで | 275円 |
いちにち定額コース:1日の約定代金合計額に手数料がかかるプラン
| 1注文の約定代金 | 手数料 |
| 100万円まで | 0円 |
| 200万円まで | 2,200円 |
| 300万円まで | (以降、100万円増えるごとに1,100円追加) 3,300円 |
約定ごとに手数料がかかるコースであれば、それほど金額に違いはない。定額コースの場合は、
SBI証券(アクティブプラン)、楽天証券(いちにち定額コース)ともに100万円までの取引は手数料無料となっている。
しかし、約定金額が100万円を超えてしまう場合は、SBI証券の手数料のほうが低い。
1日に100万円を超える取引をするかしないかで、会社を選ぶとよいだろう。
株価分析ツールの使いやすさの違い
株式投資をする際に、重要なのが情報の分析だ。分析ツールの使いやすさもチェックするべきだろう。
SBI証券の分析ツール「HYPER SBI」 が有名である。
「HYPER SBI」 は、パソコン上の一つの画面で登録した20銘柄のリアルタイムの値動きが確認できる。40種類にもおよぶチャートの確認、マーケットニュースや四季報の閲覧もできる便利なツールだ。
また、注文もツール上から行えるため、タイミングを逃がすこともない。積極的に投資をしたい人におすすめといえるだろう。
楽天証券の分析ツール「マーケットスピードⅡ」は、2018年秋にリリースされた分析ツール。
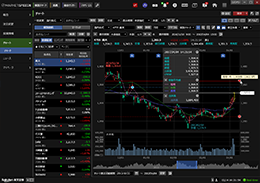
出典元:マーケットスピード II | 楽天証券のトレーディングツール
「マーケットスピードⅡ」は、チャートも今までの27種類から57種類に増えている。 また、チェックしたい個別銘柄の情報は一つの画面ですべて確認できる。
このツール上から、さまざまな方法の注文も可能だ。「より積極的に投資をしたい」「投資の知識が十分にある」といった人におすすめのツールといえるだろう。
SBI証券と楽天証券の取引ツールの使いやすさを比較
分析ツールについて分かったところで、取引ツールも見ておこう。それぞれどのような方法で取引できるのだろうか。
取引ツールについて
SBI証券と楽天証券の取引ツールを確認し、どのようにして注文を入れるのかを見ていく。
【SBI証券の注文方法】
SBI証券の注文は、以下の方法で受け付けています。
- パソコン
- スマホアプリ
- 電話
パソコン、スマホアプリ については自身で「売り・買い」「銘柄」「株数」「指値・成行・逆指値」を入力し、取引が成立したら連絡が来る仕組みだ。なお、SBI証券では電話での注文 もできるが、手数料が以下の通り、かなり割高となりますので注意が必要だ。
※手数料は税込み
| 1注文の約定代金 | 手数料(1回あたり) |
| 50万円まで | 2,200円 |
| 50万円超100万円まで | 3,960円 |
| 100万円超150万円まで | 4,840円 |
ネット証券会社というだけあり、ネットでの取引のほうがお得といえるだろう。
【楽天証券の注文方法】
楽天証券の注文は、以下の方法で受け付けています。
- パソコン
- スマホアプリ
- 電話(自動音声電話、カスタマーサービス
楽天証券でもパソコンやスマホからだけでなく、電話でも注文を受け付けている。しかし、SBI証券と異なるのは、自動音声電話の受付がある点だ。プッシュボタンで注文を入れる。この場合は、インターネットで注文を入れたときと手数料は変わらない。
ただし、SBI証券と同様に、カスタマーサービスのオペレーターを通じて注文 を入れた場合は、以下の通り手数料が割高となる。(※手数料は税込み)
| 1注文の約定代金 | 手数料(1回あたり) |
| 30万円まで | 3,795円 |
| 50万円まで | 3,795円 |
| 100万円まで | 4,180円 |
SBI証券、楽天証券どちらもインターネットから注文を入れるのが基本だ。しかし、「どうしても電話を使わないといけない」といった場合は、楽天証券の自動音声電話を利用するといいだろう。
取引ツールにはどのような特徴がある?
両社ともインターネット経由で取引するのが基本だが、どのように注文するのだろうか。取引ツールを紹介する
- 公式サイトから
- スマホアプリから
- 分析・トレーディングツール「HYPER SBI」から
- 公式サイトから
- スマホアプリ「iSPEED」から
- iPad版「iSPEED」から
- 分析・トレーディングツール「マーケットスピード Ⅱ」から
どちらも同じような方法で注文を入れることが可能だ。また、両社とも公式サイトや分析・トレーディングツールだけでなくスマホアプリからでも、個別の銘柄の情報や、マーケット情報などが確認できる。ちなみに、「スマホの画面からでは情報が見にくい」という人は、タブレットの大きな画面で閲覧できる楽天証券のiPad版「iSPEED」を利用するのもよいだろう。
「これから投資をはじめたい」という初心者の人の場合、分析・トレーディングツールは使い方が少々難しいため、まずは公式サイトやスマホアプリからスタートしてみてはいかがだろうか。
SBI証券で口座開設する証券会社のサービスを比較するポイント
各証券会社のサービスを比較するうえでのポイントをいくつか紹介する。
取扱商品の豊富さ
証券会社では株式(国内・海外)、投資信託、債券(国内・海外)、先物(国内・海外)FX、CFDなどさまざまな商品を扱っているが、商品数は証券会社によって異なる。まずは取扱商品の多いSBI証券や楽天証券といった大手のネット証券会社の口座を開設して自分に合う商品を探してみるのが良いだろう。
初心者向けサポート
一部の証券会社では、無料セミナーやお問い合わせ窓口などの投資初心者向けのサービスを提供している。サポートサービスに加えて、アプリを始めとする各種ツールが使いやすいかどうか確認すると安心だ。
ポイントサービス
最近では多くの証券会社が独自のポイントプログラムを導入しており、取引に応じてポイントを貯めることができる。ポイントの付与条件や使い道は証券会社によって様々であり、貯まったポイントで投資ができたり日常の買い物に利用できたりする。自分にとって「ポイントが貯めやすく、使いやすいか」という点を踏まえ、証券会社を選ぶと良いだろう。
売買手数料
売買手数料には、1回の約定ごとに手数料がかかる場合と、1日の約定代金合計金額に手数料がかかる場合の2パターンがある。SBI証券、楽天証券いずれも2パターンのプランの用意があるので、まずは口座開設を行い、自分が取引する頻度や金額をイメージしながら比較すると良いだろう。
両社ともメリットの多い証券会社!自分に合ったほうを選ぼう
SBI証券と楽天証券を手数料コストやサービスの面から比較した。どちらも口座開設数が非常に多い証券会社のため、サービス面では非常に充実している。
ただし、取引手数料を「1日定額」とした場合は、1日100万円までの約定ならば手数料0円、100万円を超える場合はSBI証券のほうがお得といえる。
外国株式の取引を考えている人も、SBI証券が向いている。日本ではあまり知られていない外国のマーケットにチャレンジしたい人は、9ヵ国もの株式を扱っているSBI証券を選ぶとよいだろう。
また、両社ともインターネット注文が主流ですが、パソコン・スマホの故障などで、どうしても電話で注文を入れないといけない場合もあるかもしれない。その際は、自動音声電話ならばインターネットでの取引時と手数料が変わらない楽天証券を利用するとよいだろう。
どちらの証券会社にも、メリット・デメリットがある。いろいろ見比べて、自分にあったところを選ぶのがおすすめだ。場合によっては、2つの口座を作成して取引ごとに使い分けるようにすることも選択肢の一つといえるだろう。
【関連記事】
・楽天証券とSBI証券はどう使い分ける?比較して上手に活用!
・楽天証券で少額投資! ミニ株投資はできるの?
・証券口座は複数持つべき?メリットやデメリットを知って運用しよう!
・SBI証券の2つの手数料「スタンダード」と「アクティブ」はどっちがお得?
・証券口座開設にマイナンバーが必要?“投資はじめて”さんのよくあるマイナンバーの疑問5選