本記事は、内藤誼人氏の著書『不安や悩みがすぐに軽くなるアドラー心理学』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

訓練すれば、人前でも堂々と話せるようになる
人前でスピーチができず、舞台恐怖の傾向がある人は、聴衆を敵だと見なしているからである。
『The best of Alfred Adler』
私たちにとって、「死ぬこと以上に怖い」ものがあります。それはスピーチ。米ネブラスカ大学のカレン・ドワイヤーは、さまざまな恐怖のリストを815名に見せて、何が一番怖いのかを調べてみたことがあります。
すると1位は、「人前でのスピーチ」。これを怖いと答えた人は61.7%でした。2位は「お金の問題」。お金がなくなることに恐怖を感じるのは54.8%です。そして3位が、「死」。死を恐れるのは43.2%でした。
「スピーチをするくらいなら死んだほうがマシ」と冗談交じりに言う人もおりますが、本人にとっては冗談でも何でもないのかもしれません。
けれども、スピーチはそんなに怖れる必要もありません。
なぜなら、ちょっと訓練すれば、だれでもそれなりにスピーチができるようになるからです。
アメリカン大学のルース・エイデルマンは、社会恐怖(昔の対人恐怖症)と診断された52名(男性23名、女性29名)に、1回2時間の訓練を10回受けてもらいました。訓練では、誤った認知を修正するための講義(聴衆がみんな敵かというとそんなこともなく、好意的に反応してくれる人のほうが圧倒的に多いという事実を教えるなど)に加え、4人から6人のグループでの発表のワークショップが行われました。また週ごとの宿題も出されました。「今週は、人の多いところに出向いてみよう」などです。
それから6か月後に調べてみると、社会恐怖と診断された参加者たちもそれほど不安を感じなくなることがわかりました。
人前で緊張したりするのは、訓練で相当に改善できるのです。
人前でドキドキしたり、顔が赤くなってしまったりすることにコンプレックスを感じる人も少なくないでしょうが、そういう問題は解決不可能かというと、そんなこともありません。
カウンセリングやセラピーに通ってもよいのですが、自分なりにいろいろな人と会うように心がければ、そのうち自然と不安や緊張も消えてくれるものです。
人間関係のスキルは練習でいくらでも伸びる
(甘やかされた)子どもには、今後の人生に欠かせないトレーニングをしておく機会がありません。つまり、他者と正しい方法でつながる努力をし、実行する練習をしていないのです。
『人間の本性』
昔の日本には、兄弟姉妹がたくさんいました。5人も6人も兄弟がいるのは、ありふれた光景でした。そのため、ごく普通に生活しているだけでも、人間関係の練習ができました。どうするとケンカが始まるのか、もしケンカをしたらどうすれば仲直りできるのかを、自宅にいながら練習できたのです。
また、田舎でも都市部でも学校が終われば、子どもたちは学校のグラウンドや空き地で遊びました。遊びを通して友だちの作り方なども自然に学習するのが一般的でした。
ところが時代は変わり、一人っ子が多くなりました。自分1人しかいないので、当然ながら人間関係のスキル、たとえば会話のスキルなどの練習もできなくなりました。また、塾に通う子どもも増えて、放課後に遊ぶ子どもが減りました。そのため、クラスメートとどうすれば仲良くできるのかの機会が奪われてしまうようになりました。
このような時代においては、どうしても自分なりに人付き合いの練習をしなければなりません。
では、人間関係のスキルというものは練習できるものなのでしょうか。
結論を先に言うと、できます。
実際に、私が大学で受け持っている講座名は、「対人スキルトレーニング」です。魅力的に見える笑顔を作る技術、自分の意見を間違いなく相手に伝える技術、表情から相手の気持ちを見抜く技術などは、練習で伸ばせるのです。
ドイツにあるボン大学のタッシロ・モンは、さまざまな職業の123名の成人に、相手の声を聞いて、4つの感情(幸福、悲しみ、怒り、恐怖)のどれに当てはまるのかのトレーニングを受けてもらいましたが、訓練の後には、相手の声を聞いて感情を見抜けるようになったという研究報告をしています。
同じような研究はいくらでもあります。
もし自分の人間関係の技術に不安があるのなら、セミナーや講演会に出向いて、その技術を教えてもらうとよいでしょう。できれば単なる座学ではなくて、ワークショップ形式のものを選びましょう。
「対人スキル」というキーワードでセミナーの検索ができないのなら、「コミュニケーション・スキル」というキーワードで探してみてください。どちらも同じような意味ですが、「コミュニケーション・スキル」のほうがよく使われる用語のような印象があります。
セミナーや講演会に参加するには、多少のお金はかかってしまうかもしれませんが、それによって人間関係の技術を学べるのであれば、決してソンにはならないと思います。
ちょっとした隙間時間には、イメージトレーニングをする
白昼夢には将来を予測しようとする意識がともないます。人間が未来へ続く道を開き、確実に進もうとしているときに、白昼夢は現れます。
『人間の本性』
通勤・通学でバスや電車を待っているときには、頭の中で他の人としゃべっている姿をイメージしてみるとよいですよ。相手がこんなことを言ってきたら、自分はこんなふうに返事をしよう、というイメージをしていると、実際の会話力もアップしますから。
「空想と現実は違うのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなこともありません。読者のみなさんも「イメージトレーニング」(略してイメトレ)という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、頭の中でイメージするのは、実際の訓練と同じような効果があるのです。
プロのアスリートは、試合の流れを頭の中でイメージトレーニングするものですが、そういう訓練は非常に重要です。イメージトレーニングをするかしないかで、実際の試合の運びもまったく違ってくるのです。
イメージトレーニングは、さまざまなプロが実践している非常に効果的なテクニックなのですから、どんどんやりましょう。
米ウィスコンシン大学のリチャード・マクフォールは、頭の中でいろいろとイメージトレーニングしておくと、たとえば、断りづらいことを相手に求められたときにも、スムーズに断ることができることを実験的に確認しています。
マクフォールは、他の人の頼みをなかなか断れない人だけを集めて、さまざまな状況でのイメージトレーニングをしてもらいました。
「あなたの家は図書館のそばなんだから、私の本を返却しておいてくれない?」といった具体的な場面をイメージしてもらい、どのように断れば角が立たないのかをいろいろとイメージしてもらったのです。
このようなイメージトレーニングを受けてもらうと、現実に似たような状況になったときにスムーズに断ることができるようになりました。イメージトレーニングはとても効果的だったのです。
たとえ独学であっても、勉強していればそれなりに知識がついてくるのと一緒で、自分勝手なイメージトレーニングでもやらないよりは、やったほうがずっと効果的です。
異性と話すときに緊張してしまう人は、いろいろな異性とおしゃべりする場面を空想してみてください。空想するだけなので、特別な道具などもいりませんし、どこでも行うことができます。入浴中でも、食事を食べるときでも、好きなときにイメージトレーニングをしてみましょう。
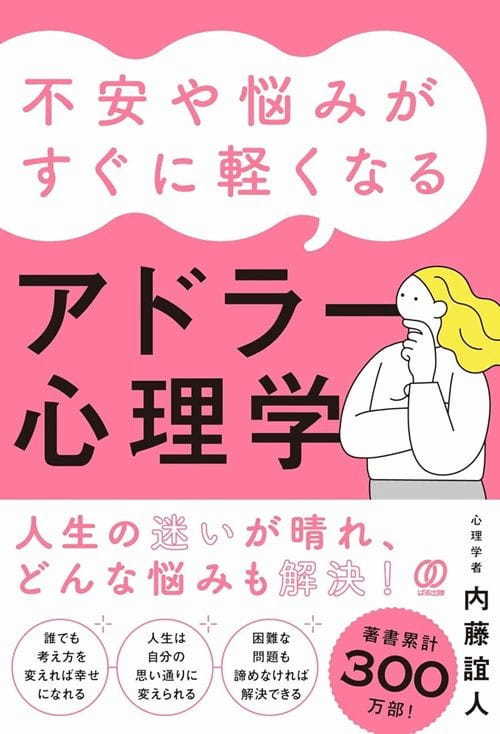
慶應義塾大学社会学研究科博士課程修了。社会心理学の知見をベースに、ビジネスを中心とした実践的分野への応用に力を注ぐ心理学系アクティビスト。趣味は釣りとガーデニング。著書に『人間関係に悩まなくなるすごい心理術69』(ぱる出版)、『いちいち気にしない心が手に入る本:何があっても「受け流せる」心理学』(三笠書房)、『「人たらし」のブラック心理術』(大和書房)、『世界最先端の研究が教える新事実 心理学BEST100』(総合法令出版)、『気にしない習慣 よけいな気疲れが消えていく61のヒント』(明日香出版社)など多数。その数は250冊を超える。※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
