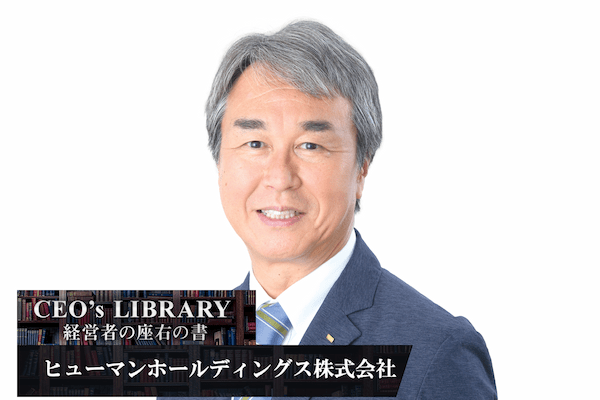
社長のこれまでの変遷について
—— まずは社長のこれまでについてお伺いしますが、事業を継承されているということで、最初は管理部門からスタートされたと伺っています。
ヒューマンホールディングス株式会社 代表取締役社長・佐藤 朋也氏(以下、社名・氏名略) 日興証券(現:SMBC日興証券)、本郷会計士事務所(現:辻・本郷税理士法人)を経て、当社(前身である「ザ・ヒューマン株式会社」)への入社は1991年です。最初のミッションは、東京に経理、財務、人事、総務の機能を作るべく、東京管理部を立ち上げました。
—— それから、大阪本社の経理に異動されています。どのような状況だったのでしょうか。
佐藤 当時、会社は急成長中で本社の経理は非常に混乱しており、会計処理が追いつかず、また適切でなかったことが原因で、資金繰りすら全く掴めないような状態でした。そこで、それらを解決すべく、会計基準に合った会計処理の適正化に取り組み、その結果、時間は掛かりましたが、なんとか経理機能の正常化に成功しました。その後は、財務や情報システム、国際部門なども兼任し、様々な管理・スタッフ部門を経験しました。
—— その後、創業者である社長(現・取締役ファウンダー)から上場の話が出たと伺いました。
佐藤 当初、上場については、私は積極的ではありませんでした。当時、知名度や投資資金に特段問題はなく、却って上場することにより経営の自由度が制限され、制約が増えると考えていたからです。結果的には創業者の意向により、2002年にヒューマンホールディングス株式会社を設立して、私が社長に就任し、2004年にJASDAQ証券取引所(現:東証スタンダード市場)に上場しました。その結果、経営に求められるものに変化があり、それまでの経営方法や価値観が変わりました。また、副産物として会社の雰囲気が活気づきました。
—— 上場後の経営について教えてください。
佐藤 教育から人材・介護と事業を拡大してきましたが、上場後には、さらに、スポーツ事業(B.LEAGUE B1に所属するプロバスケットボールクラブ「大阪エヴェッサ」の運営)、美容事業、保育事業、IT事業と、教育とのシナジーのもと事業領域を拡げてまいりました。一方で、減損会計基準の適用の開始や職業訓練給付金の縮小により、社会人教育事業で約30億円の赤字に陥ったり、政権交代による人材派遣の規制緩和の方針が変わったことにより、誠に遺憾ながら人材派遣事業において行政処分を受け、売上が約半分に落ち込んだりと、様々な外的要因によるリスクも経験してきましたが、2021年度には上場後の最高売上高を記録し、現在に至るまで更新し続けています。
社長の一番感銘を受けた書籍とその理由
—— 社長の最近感銘を受けた書籍について教えていただけますか?
佐藤 最近読んだ中で特に印象に残っているのは『入門・マーケティング戦略』という本です。これは慶應義塾大学ビジネス・スクールの元校長で慶應義塾大学の名誉教授である池尾恭一先生が書かれたもので、池尾先生は私が大学のゼミでお世話になった先生でもあります。現在はヒューマンアカデミーが運営するMBAスクールの顧問や講師も務めていただいています。
—— この本が特に印象に残った理由は何でしょうか?
佐藤 ヒューマングループは、ブルーオーシャンにおける戦略を駆使して成長してきた会社です。元々、営業活動のない教育事業において営業に取り組み、一気にシェアを拡大しました。そして、他の事業においてもブルーオーシャンのマーケットを、営業力を駆使して市場シェアを拡大してきました。具体的には営業マンの数を増やし、営業量を徹底的に追及することで成功を収めてきたのです。
しかし、現在、各事業においては競争が激化してレッドオーシャン化し、従来の手法では勝てなくなってきました。その時に必要となったのが、マーケティングの差別化戦略で、この本は、私がその基礎を再確認するために最適な一冊で、今でもバイブルとして活用しています。
—— まさに仕事の中心にある書籍ですね。
佐藤 マーケティング戦略は、マーケット環境を把握し、他社の動向を分析することが重要です。また、プロモーションを通じて得られる反応を分析し、必要に応じて戦略をリアルタイムで調整することが求められます。
—— 特にマーケティングの重要性を感じられた出来事はありますか。
佐藤 例えばリーマンショックの時、景気の悪化により教育事業のネイリスト養成講座の受講生数が急激に落ち込む状況の中、改めて受講生の分析をしてみると、新たな顧客層が見えてきました。ホステスなどナイトワークの方々が景気悪化の影響を受けて“手に職”を意識し、ネイリストを目指されている状況が浮かび上がってきたのです。状況を分析して変化を迅速に察知し、適切なターゲットへアプローチを行うことの有用性を改めて感じた印象的な出来事でした。
このように常に市場の動向を把握し、ターゲットのニーズに応じた戦略を練ることが重要です。教育の分野ではマーケティングは日常的なものとして捉えています。また、人材派遣や介護の分野では、長期的な視点での戦略が求められます。付加価値の高いビジネスへシフトし、専門性を高めることで差別化を図っています。
—— コロナ禍では、教育事業にどのような変化がありましたか。
佐藤 コロナ禍では、リアルな教室でのサービス提供が難しくなりましたが、インターネットを活用するオンライン講座という新たな需要が急拡大しました。その理由は、場所・時間・形態にとらわれることなく、例えば、受講生が、東京にしかいない優秀な講師の授業を地方や海外からでも受講できるようになったからです。
—— 人材派遣事業にも変化が及んでいるようですが、どのような影響がありますか。
佐藤 コロナ終息後は景気の回復が顕著になってきました。それに併せて、国内労働人口の減少に対応するために海外人材を活用する取り組みも進めています。
—— 具体的にはどのような取り組みをされていますか。
佐藤 海外からIT技術者を招き、日本語教育を提供した上で、国内企業へ派遣しています
—— 海外人材も、給与水準の高い欧米などではなくて日本に来てくれるのですね。
佐藤 日本の文化や生活スタイルに憧れる外国人は多く、これが日本で働く動機となることもあります。文化的なバックボーンが強みとなり、日本を選ぶ理由になっています。
また、教育事業において専門教育やリスキリング、介護・保育事業により労働市場に人材を送り出す支援、そしてITを活用した業務効率化、特にRPAを導入して生産性を高めるサービス支援といった事業に注力して、日本の抱える労働人口減という問題にトータルで対応するソリューションを提供しています。
社長が経営において重要としている考え方
—— 社長が経営において重要視している考え方についてお聞かせください。経営で判断に迷われた時に思い出されるフレーズや、重要な考え方について教えていただければと思います。
佐藤 我々の経営理念である「為世為人(いせいいじん)」が一番の起点です。世のため、人のためになるのかどうかが判断基準の根底にあります。世の中に貢献しないものはビジネスにはなり得ないと考えます。
思い描いている未来構想や従業員への期待について
—— 最後にお聞きしたいのですが、佐藤さんが思い描いている未来構想、今後の御社の展望、そして従業員への期待についてお話しいただけますか?
佐藤 まず、今後の展望についてですが、先ほどお話しした通り、日本の人口減少、特に労働人口の減少に対して、教育・人材・介護・保育・ITなど我々のリソースを活用して具体的に解決していこうと考えています。これが当面のビジョンです。
—— それでは、社員の方々にはどのように成長してほしいと考えているのでしょうか?**
佐藤 我々は、すべてのステークホルダーへの提供価値(バリュープロミス)として「SELFing」を掲げております。これは「self-management」に現在進行形の「ing」をつけた造語で、なりたい自分を発見し、それに至るプロセスを設計し、サポートするという意味です。社員に対しては最優先でSELFingを提供し、顧客に対して説得力のあるサービスを提供したいと考えています。
—— 具体的にはどのような方法でサポートされているのでしょうか?
佐藤 マンダラチャートをもとに開発した「SELFingシート」というツールを使用しています。マンダラチャートは大谷翔平選手の目標設定シートとしても知られていますが、正方形の中に9つのマスを作り、真ん中に「なりたい自分」の姿や目標を書きます。その真ん中の目標を達成するために何をすべきかを周囲の8マスに順に書き込んでいきます。そしてそれを更に8マスに展開することもできます。このフレームワークに取り組むことで、目標が明確になり、やるべきことが見えてきます。また、その中で仕事の位置づけもはっきりしてくるはずです。なりたい自分が見つかると自走し始め、自立していきます。自走すると人は強い。自立した職業人を目指してもらいたいと考えています。
ある若い社員は現在マネージャーをしておりますが、「かっこいい男になる」と真ん中に書いていました。彼はそのためには仕事ができなくてはならないと、生き生きと仕事に取り組んでいます。どんなささいなことでもいいのですが、なりたい自分を見つけ、自発的に動けるようになることが、人生を豊かにする重要なポイントだと思います。
—— 目標を持つことで、行動が明確になりますね。本日は貴重なお話をありがとうございました。
- 氏名
- 佐藤 朋也(さとう ともなり)
- 社名
- ヒューマンホールディングス株式会社
- 役職
- 代表取締役社長

