(本記事は、マーク・ハイマン氏の著書『アメリカの名医が教える 内臓脂肪が落ちる究極の食事』= SBクリエイティブ、2020年6月20日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
どのような食べ物から摂取したものであっても、すべてのカロリーが体重と代謝に与える影響は同じだというのは、今日の医学界に根強く残っている神話である。実際には食品が違えば、遺伝子の発現、ホルモン、脳内の化学作用、免疫系、代謝、さらには腸内細菌叢に異なる影響を与えるのである。
食べ物はただのエネルギー源、カロリー源ではなく、情報である。食べ物には体のあらゆる生理機能に影響を与える指示が含まれている。すべてを制御するのだ。食べ物は遺伝子の発現に影響し(どの遺伝子が病気を引き起こすか、あるいは予防するかを決め)、ホルモン、脳内の化学作用、免疫系、腸内細菌叢、さまざまなレベルの代謝に影響を与える。それは一口食べるごとにリアルタイムですばやく作用する。これはニュートリゲノミクス(遺伝子中のタンパク質・代謝物などを解析して、食品が体に与える影響を研究する手法)の画期的な科学によって解明されている。
脂質から摂るカロリーのほうが減量と代謝の改善に有効であることを確認する科学者がますます増えている。米国国立衛生研究所のケヴィン・ホールは、すべての食事量・運動量・カロリー消費量を注意深く測定する代謝病棟において、脂質によるカロリー摂取量を増やした人は(同量のカロリーを炭水化物から摂った場合に比べて)、1日に100カロリー以上余分に燃焼させたことを見いだした。1年の間にそれは4・5キロの減量をもたらす。ホールはまた、脳画像と脳機能の研究で、脂質の摂取量を増やすと空腹中枢が抑制されると報告している1。食物摂取・味の好み・代謝を制御する上では、脳が最も重要だと思われる。そして食事中の脂質は、カロリーの燃焼プロセス全体にプラスの影響を与えるのだ。
お腹いっぱい食べても太らない

たいていの人は食べすぎるから太ると思い込んでいる。もっともな推論に思えるだろうが、ハーバード大学教授、デイヴィッド・ルードヴィヒは『ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・メディカル・アソシエーション』誌に掲載された才気あふれる論文で、肥満と代謝に関するまったく異なる考えを主張した。
彼はさりげなく、私たちが逆の考え方をしていると言う。あなたが太るのは、食べる量が増えて運動不足になるからではなく、太っているために食べる量が増えて運動不足になるからである。要するに脂肪細胞が「空腹感をもたらし」、過食することになる。ルードヴィヒは著書『Always Hungry?(いつもお腹が空いてるって?)』の中で、このプロセスを詳しく説明している。太り過ぎると、ホルモンと脳内化学物質によって空腹感と疲労感が生じるのだ2。
これは、体重増加の原因についての考え方を根底から覆し、減量のために推奨されていることを何もかも否定している。ルードヴィヒ博士は、カロリーと量のことばかり考えず、体が本来の能力を発揮して空腹感・活動・代謝・体重を調節できるように、食事の質と構成(タンパク質、脂質、炭水化物の量と種類)を重視することを勧めている。意志の力に頼るのではなく、科学を用いて空腹感をなくし、エネルギーを高め、代謝をスピードアップさせよう!
さて、あなたの体内ではどんなことが起こるのだろうか。
まず、カロリーを制限して運動を増やすと、体は飢餓状態にあると認識するように作られている。そうなると疲れを感じ(それによって動きを減らしてエネルギーを節約し)、お腹が空き(そのために食べる量が増え)、代謝が遅くなる(だから死ぬことはない!)。この「食べる量を減らしてもっと運動する」方式はたいていうまくいかない。もちろん、短期間ならうまくいくことがあるが、減量してその体重を1年間維持できる人は10パーセント未満だ3。十中八九リバウンドして、元の体重に戻ってしまう。
第2に、炭水化物と糖質を摂ると、インスリンが急増して血糖値が下がる。インスリンは、血流内で利用できる燃料の大半を脂肪細胞、特にお腹の辺りの脂肪細胞すなわち、おなか周りの内臓脂肪に変える。すると、体は燃料不足に陥り、脳を刺激して4 食欲を起こさせる5 。脂肪組織に1年分のエネルギーをため込むことができても、飢えているような気がするのだ。
この悪循環を断ち切る唯一の方法は、脂質をたくさん摂って、精製炭水化物と糖質の摂取をやめることである。高脂質・低炭水化物の食事をとれば新陳代謝が良くなり、減量した体重を維持できる。
体重が上下するのはなぜか
脂肪細胞はなぜ脂質を蓄えるのだろうか?
なぜそれは脂質を放出して燃焼させるのだろうか?
私たちは体が体重を調節する仕組みを今なお学んでいる。機能性医学(1990年にアメリカのジェフリー・ブランド博士によって提唱された「最先端科学と医学を融合した、生活習慣病や慢性病の治療法」)の核となるのは、生化学的・遺伝的個性の概念である。この概念は特に体重に関連している。体重増加の原因は1つではない。多種多様な食べ物―脂質や炭水化物やタンパク質―に対する反応の仕方は人さまざまである。いまだにすべての疑問に対する答えが出ているわけではないが、全体像を描くための「点」は十分あるので、私たちは大半の人の役に立つ基本的な提言を行うことができる。
脂肪細胞はアディポサイトとして知られる。脂肪細胞は、体重に関係するほぼすべてを制御するあらゆる分子を活発に生成し、心臓病、がん、認知症を促進するように働く。
意外なことに脂肪細胞は、実のところ、甲状腺や卵巣や精巣と同じように多くのホルモンを造る内分泌細胞である。脂肪組織は白血球(マクロファージ)を含むので、免疫系の一部でもあり、アディポサイトカインという炎症性化学伝達物質を産生する。内臓脂肪などの体脂肪は、神経伝達物質―脳の化学伝達物質―の影響を受けるとともに制御する。脂肪細胞は貯蔵器官で、(飢餓状態や低血糖により)供給が減った場合に蓄積したエネルギーを提供する。脂肪細胞は、食事中の炭水化物から脂質を生成することもできる。活動的な脂肪の小球は、常に全身―胃、膵臓、脳、ホルモン、肝臓など―とメッセージを伝え合うが、この複雑に絡み合った相互作用とフィードバックは混乱に陥りやすい。
しかし、一番重要だと断言できること、つまりいくつかの事実から全体像を導き出すというストーリーの最後の事実は、脂肪細胞の生理作用のほとんどが食べる物の質と種類によって制御されるということだ。そしてこのために、「内臓脂肪を落とす食事」実践編のような高脂質・低炭水化物(低GI)・高繊維質の自然食が、多くの人に有効なのである。
体を「炭水化物燃焼」から「脂肪燃焼」に変える
炭水化物の摂取を控えると、インスリン値が低下する。インスリンは塩分(と水分)を保持するように働くため、その低下によって腎臓から塩分が排出される24。これが筋肉のけいれんを引き起こすことがある。最善の策は、毎日、食事にティースプーン1〜2杯の塩を加えることだ。さらに、カリウムの摂取も増やす必要がある(1日当たり約2グラム)―これは第●章(●ページ)で紹介する野菜と骨のスープから摂ることができる。
炭水化物の摂取を減らすと運動能力に影響を与えるのでは、と心配する人がいるかもしれない。多くのアスリートが、レース前にグリコーゲン(筋肉に蓄えられるブドウ糖)を補給するために、炭水化物を多く摂取する。しかし多数の研究によれば、いったん低炭水化物食に順応すると、持久性運動はまったく影響されない。短距離走やウェイトリフティングなどの無酸素性運動はグリコーゲンの貯蔵不足に影響される可能性があるが、●ページからの「内臓脂肪を落とす食事」実践編では、決められた量の炭水化物を摂ると、この問題を予防するのに十分なグリコーゲンの貯蔵を維持できる。低炭水化物・高脂質食に慣れ、炭水化物燃焼から脂肪燃焼に体を切り替えるには数週間かかるが、本書のプログラムに従えば、それを実現できる。ただし、必ず十分な量のタンパク質―毎日、体重1キロ当たり1・5グラム、つまり標準的な人なら約100〜120グラム―を摂る必要がある。毎食タンパク質を摂ることで、筋肉が付くのだ。だが活動量や運動量が少ない場合は、摂りすぎたタンパク質が血流内で糖に変わることがあるため、あまり活動しないのならタンパク質を減らす必要がある。これについては第●章(●ページ)で説明しよう。
1 . Hall KD, Hammond RA, Rahmandad H. Dynamic interplay among homeostatic, hedonic, and
cognitive feedback circuits regulating body weight. Am J Public Health. 2014 Jul;104(7):
1169 ‒75 .
2 . Taubes G. The science of obesity: what do we really know about what makes us fat? An
essay by Gary Taubes. BMJ. 2013 Apr 15 ;346 :f1050 .
3 . Kraschnewski JL, Boan J, Esposito J, et al. Long-term weight loss maintenance in the United
States. Int J Obes(Lond). 2010 Nov;34(11): 1644 ‒54 .
4 . Luo S, Romero A, Adam TC, Hu HH, Monterosso J, Page KA. Abdominal fat is associated
with a greater brain reward response to high-calorie food cues in Hispanic women. Obesity
(Silver Spring). 2013 Oct;21(10): 2029 ‒36 .
5 . Page KA, Seo D, Belfort-DeAguiar R, et al. Circulating glucose levels modulate neural control
of desire for high calorie foods in humans. J Clin Invest. 2011 Oct;121(10): 4161 ‒69 .
24 . DeFronzo RA. The effect of insulin on renal sodium metabolism. A review with clinical
implications. Diabetologia. 1981 Sep;21(3): 165 ‒71 . Review.
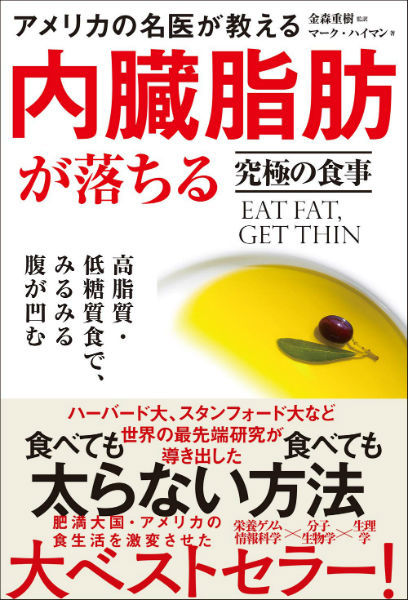
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
- 脂質の大誤解を解き、健康を手軽に手に入れよう
- 好きなだけ食べても太らないという衝撃の新事実
- 肉を食べれば、内臓脂肪が落ちる!?
- 脂質がもたらす驚きの健康効果
- 「内臓脂肪を落とす食事」実践編





