(本記事は、藤原正明氏の著書『収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則』クロスメディア・パブリッシングの中から一部を抜粋・編集しています)
近年明らかになってきた、不動産業界の歪み
日本は人口減少社会に入っています。国連の「2019 Revision of World Population Prospects」によれば、おおよそ日本の人口は2030年には1億2,076万人、2060年には9,833万人、2100年には7,496万人になるとの見通しが発表されています。
また、国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した「日本の将来推計人口」(図表3)でも、2053年には1億人を割り、2065年には8808万人になるとしています。同発表では、出生数が現状のまま低位であれば、2049年には1億人を割るとされています。

加えて、出生率も低迷を続けています。国はさまざまな出生率をあげる政策を打ち出していますが、2018年は1.42にとどまっています。過去最低を記録した2005年の1.26よりは改善していますが、人口数の維持に必須だとされる2.07には遠く及びません。
そもそも、現在、政府が掲げる出生率の目標値は1.8です。もはや国は、人口が増えることを目指しておらず、いかに減少率を抑えるかというフェーズに入っているのです。
こうした社会状況にもかかわらず、不動産業界や建築業界、それも先にあげたような大手ハウスメーカーやアパートビルダーは、ある一定の数を建築しなければ企業として立ち行かなくなるため、需要に関係なく賃貸物件を新たに作り続けています。
正確には、土地オーナーや土地を持たない不動産投資家に対して、なりふり構わず土地にアパートやマンションを建てることを強く推奨し続けているのです。
その結果、昨今の報道で散見されるような不動産・建築業界の「歪み」が複数現れています。
1つは不良施工問題です。代表例が某アパートビルダーです。監督官庁である国土交通省からの指摘を受け、第三者委員会が全国にあるアパートを全棟調査した結果、7割を超える建物で不備が見つかったそうです。
上場もしているとあるハウスメーカーでも、近年、建築基準法に適合していない物件が数千規模で見つかり、大きな問題になりました。
「大手だから安心」と考えてアパートやマンションを建築した人も少なくないと思いますが、「大手ならリスクがなく安心」と言い切ることがいかに危険であるかを端的に表しています。
また、土地オーナーのみなさんが直接関係するわけではありませんが、女性向けシェアハウスをフルローンで買えると謳いサラリーマンなどへ販売していたベンチャー企業が、2018年に破産しました。
信用力のないサラリーマンにも、収益不動産向け融資を積極的に行っていた某地方銀行も関係しています。同問題は、不正融資問題としても大々的に報道されたので、ご存知の方も多いでしょう。
同じく、東証一部にも上場している比較的歴史の浅い建設会社も、顧客の融資を通しやすくするために、書類の改ざんを違法的に行っていたと指摘され、業務停止命令を受ける事態になりました。
さらに、投資用区分マンションを販売していたいくつかの不動産業者は「フラット35」という住宅金融支援機構による自宅向け住宅ローンを、不動産投資目的で不正利用していたとして、2019年に問題視されました。
業者は「自己資金なしで投資が可能」と謳い、新築・中古ワンルームマンションなどを割高な価格で販売していたそうです。これは融資契約違反です。
このように、収益不動産に関連する不動産業界・建築業界の問題には、枚挙に暇がありませんが、その根底にあるのは、顧客利益を無視した営業攻勢とコンプライアンス軽視です。その歪みが、ここ数年で一気に露見してきているのです。
アパート・マンションは建てて終わりではない
アパート・マンションを建築さえしてしまえば、後は自然と家賃が入ってきて、滞りなく返済が済んでいく、と考えている土地オーナーの方々がたくさんいます。
ある意味では、それも仕方ない部分もあります。これまで見てきたように、土地オーナーに対して営業攻勢をかけてきた大手ハウスメーカーやアパートビルダーの営業担当者は、「建物さえ建てれば、後は何も考えなくてよい」と錯覚するようなセールスを行ってきたからです。
土地オーナーのみなさんとしても、相続税対策という目先の目的があるため、この点を深く追求することなく、建築プランを進めていったのです。
当然のことながら、アパートもマンションも、建てたら終わりではありません。ざっと考えても、「入居する人を探す」「不具合が出た設備を直す」「建物のメンテナンスをする」「退去者が出た部屋のクリーニングやリフォームを行う」「家賃を回収する」といったことが必要です。一般に、これらのことを賃貸管理と言います。
もちろん、こうしたやるべき賃貸管理業務の一部、もしくはすべてを、別の誰かに依頼する(アウトソーシング)することは可能です。
しかし、“外部委託できること”と“何もしなくとも自然にお金が入ってくること”は、まったく別の話です。
つまり、あらゆるビジネスと同じように、賃貸経営にもリスクが存在するということです。残念ながら、賃貸経営のリスクをきちんと網羅的に理解しているという土地オーナーの方は多くありません。これから土地活用について検討している人、不動産投資に興味を持ち始めた人は、ぜひ知っておくべきです。
アパート・マンションを建てた後に考慮しなければいけない代表的なリスクは、以下の通りです。

これらのリスクへの対応について、ここでは簡単に言葉の説明をしていきます。
「空室リスク」は、空室が出ることによって、賃料が入ってこなくなるリスクです。
「家賃下落リスク」は、建物の経年劣化や周辺環境の変化によって、家賃が下落していくリスクです。
「修繕リスク」は、入居者の入れ替え時などに発生する原状回復費と、建物全体のメンテナンスにかかわる大規模修繕費です。
「家賃滞納リスク」は入居者が何らかの理由で家賃を滞納するリスクです。
「金利上昇リスク」は、現金一括で建物を建築して賃貸経営を行う場合を除き、金融機関から融資を受ける場合に発生するリスクです。変動金利を選んだ場合には、金利が上昇して、毎月の返済額が増えるという可能性があります。
「罹災リスク」は地震、火災、台風、水害といった災害に遭うリスクです。
そのほかにも、入居者が室内で死亡するという「事故リスク」もありますし、建物の壁が剥がれ落ち、通行人に後遺症の残る怪我を負わせてしまったといった「訴訟リスク」もあります。
近い将来、危機に陥るオーナーが激増する可能性がある
サブリース契約での問題も浮かび上がってきています。サブリースとは、マンションやアパートを不動産会社や建設会社が一括で借り上げ、貸主(転貸人)として第三者へ転貸する制度のことです。
不動産会社や建築会社などの(サブリース)事業者は、先ほど言及したような賃貸経営にかかる面倒な管理業務を請け負う代わりに、入居者から入ってくる賃料の80〜90%をオーナーに支払うというのが一般的です。
土地オーナーのみなさんからすれば、面倒なことをせずに毎月安定した賃料収入が保証されるということで、サブリース契約を選ぶ方が少なくありません。
しかし、サブリース契約には「賃料の見直し」という規定が入っています。ですから、多くの場合、2年ごとにサブリース事業者側から借上賃料の減額交渉ができるようになっています(一定の期間賃料の見直しができないようになっている場合もあります)。
公益財団法人日本住宅総合センターの「民間賃貸住宅の供給実態調査」によれば、築10年以上経過したサブリースの物件オーナーは、7割以上が「借上賃料の減額」を経験しているとしています。
借上賃料の減額を経験していなくとも、修繕費や原状回復費用、そのほか付帯費用などで、サブリース事業者から高額な費用を請求されるということも珍しくありません。
こうしたサブリースの問題は、大手の不動産業者・建設会社でもたびたび問題としてテレビや新聞などのメディアに取りあげられています。

2015年の相続税増税に際して、大手ハウスメーカーやアパートビルダーは一斉に土地オーナーに対して営業攻勢をかけました。このとき、多くの方がサブリース契約を結んでいるのです。
それから5年を経て、土地オーナーに対して“種明かし”を始める頃合いになってきました。
それは、たとえば月100万円での家賃保証をしていたオーナーに対して「家賃相場が下がってきたので、月80万円にしてください」と手のひらを返したように、交渉してくるのです。
当然、ほとんどのオーナーは金融機関から借り入れをしているので、支払いが難しくなっていきます。今後、築年数の経過とともに、さらなる借上賃料の減額が進めば、月々のローンが返済できない人が続出することが予想されます。その結果、「土地を手放さなければならなくなる」という事態に陥ってしまう方も増えるでしょう。
実際、すでに当社に寄せられる任意売却の相談も増加しています。「ローンが払えないので、土地と建物を手放したい」という相談です。
「土地を守るための相続税対策でアパート・マンションを建てたつもりが、結果的に土地を失ってしまった」という結末を迎える人が、現実問題として存在するということです。
なお、国土交通省の調べでは、サブリースの「賃料減額リスク」や「修繕工事費用がかかる」といったことについて、説明を受けたと答えているオーナーは約6割だったそうです。つまり4割の人が説明を受けていないのです。私の肌感覚では、説明を受けたうえできちんとその内容を理解できた人は、半分にも満たないのではないでしょうか。
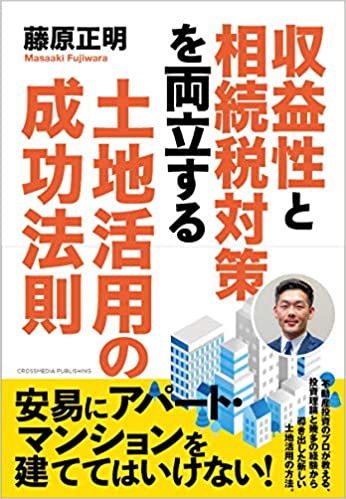
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
- 近い将来、危機に陥るオーナーが激増する?
- 2015年からの相続税増税で何が変わったか
- 融資を利用するならば押さえておくべきイールドギャップ
- サブリースをすると本来得られるお金を失う
- 賃貸需要が見込めないエリアの土地活用戦略とは
- 実家の建て替えに併せ、賃貸アパートを建築した土地活用の事例

