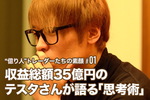前回のコラムでは、「資産運用」と「資産形成」は違うものであり、前者の為に投資信託を使うのならば求めるべき効用の源泉は「運用のエキスパートのスキル」だということをお伝えした。エキスパートで無ければ難しいことをしてくれるからこそ、そこに対価として手数料を支払う価値があるということだ。
この視点で考えた場合、「資産運用」の為に「バランス型投資信託」或いは「ファンドラップ」や「SMA」などの「国際分散投資型の金融商品」を利用することは、昨今の一般的な時流には反するが、筆者は理に適っていないと考えている。別の言い方をすると、「資産運用」を考えて投資信託などの金融商品を購入するなら、迷わず「アクティブ型運用」を選びなさいということだ。そうでなければ、仮にそれが低い料率だとしても「信託報酬」や「購入時手数料」と呼ばれる類のフィーを払う価値は無いと考えている。随分と暴言に聞こえるかも知れないが、長年投資信託の運用、組成、販売とすべてに関わってきた者の本音としてそう考えている。
超富裕層は「単品商品」として「国際分散投資の金融商品」に投資しない

誤解無きように補足するならば、決して「アセット・アロケーションがパフォーマンスの8割以上を決定する」という理論を否定しているのでもなく、またそうして勝つためのアセット・アロケーションの計算にエキスパートのノウハウが要らないとか、誰にでも簡単に出来るとか考えている訳では無い。寧ろその逆だ。アセット・アロケーションこそがパフォーマンスを左右する最大のキーファクターであり、またその決定方法やアプローチは少しばかり投資理論をかじった程度の知識や単純AI(人工知能)で出来るものだなどとはゆめゆめ思っていない。
筆者は前職ではプライベートバンクのISS(Investment Solutions Specialists)ヘッドをしていたが、そこではグローバルに統一された考え方として、すべてのお客様に国際分散投資を基本としたポートフォリオの構築を提案していたし、アセット・アロケーションの決定については行動経済学の博士号を持つエキスパートなど、専門チームが常にロンドンで作業を行っていた。
ならば何故、「資産運用」の為に「バランス型投資信託」などの「国際分散投資型の金融商品」を利用することを理に適っていないと考えるのか?
答えは大きく捉えると2つの側面がある。ひとつは理想や理屈とは別に、実際に今日本で投資出来る「国際分散投資型の金融商品」の商品性の話。もうひとつは「資産運用」の為というニーズから見た話だ。
昨今よく聞く話としては「超富裕層が行っている国際分散投資」というのがある。確かに前述したように多くの欧米のプライベートバンクは顧客に「国際分散投資」のコンセプトによるポートフォリオ運用を是として世界中で提案している。そして多くの超富裕層が行っているのが「国際分散投資」というのは間違いない。だがもしそれを言うならもう少し説明を加えないといけない。
まず超富裕層は「単品商品」として「国際分散投資の金融商品」には投資しない。新規の売込みでどうしても新参のプライベートバンクのアセット・アロケーション手腕を確かめてみようなどと思った時には、敢えてプリフィックスされた商品に投資することはあるが、彼らの「国際分散投資」は基本的にはその超富裕層の「全資産」をひとつのポートフォリオとして捉えている。当然、そうしたアドバイスをプライベートバンカーが提案するか、専門の資産管理人がコントロールしている。