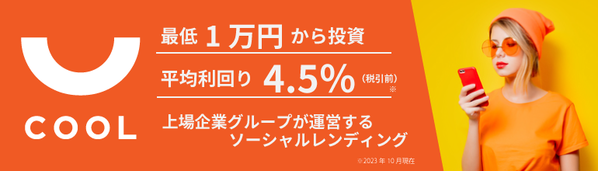貯蓄性がある個人年金保険は、老後資金を準備する手段の1つとしてよく利用される金融商品だ。一方、個人年金保険はおすすめしないといわれることもある。ここでは個人年金保険のメリットとデメリットを挙げ、どのような人に老後資金の準備として妥当なのかを紹介する。
個人年金保険とは

個人年金保険は、60歳もしくは65歳といった一定の年齢まで保険料という形でお金を積み立て、その後はそれまで積立てきたお金を原資として年金を受け取っていく仕組みの保険である。
個人年金保険にはいくつか種類があるが、最も一般的なのは、保険会社が積み立てたお金を契約時に決めた「予定利率」によって運用を行うタイプのものだ。月々に支払う保険料と将来受け取れる年金額はあらかじめ決まっており、「定額個人年金保険」と呼ばれる。通常「個人年金保険」といえばこちらを指すことが多い。
また、将来受け取れる年金額が変動する個人年金保険もある。これらは運用実績によって解約返戻金や年金額が変わるので、「変額個人年金保険」といわれる。円建てで運用するか、外貨建てで運用するかといった運用タイプでも区別され、外貨建てで運用されるものは「外貨建て個人年金保険」といわれる。
個人年金保険はおすすめしないと言われる理由
個人年金保険は将来の年金額を増やすことを目的とした保険だが、資産運用の観点からはおすすめされないこともある。ここでは個人年金保険がすすめられない理由を紹介する。
中途解約のリスクが高い
個人年保険は中途解約した場合のリスクが高い。
なぜなら、個人年金保険を満期前に解約すると、保険契約の解約時にかかる手数料である解約控除が発生し払込保険料から差し引かれるため、解約返戻金が払込保険料に比べて少なくなるからだ。
たとえば、個人年金保険を契約日から2~3年で解約した場合、保険会社や契約の内容にもよるが、解約控除の額が払込保険料の10%程度になることもある。つまり、解約日までに100万円の保険料を払い込んでいたとすると、解約控除として約10万円引かれる計算だ。
解約控除は一般的に契約から経過年数が短いほど高くなり、解約返戻金の金額が払込保険料を上回るには15~20年程度必要といわれている。そのため個人年金保険を途中で解約した場合、支払った保険料より少ない金額しか返ってこないというリスクがあるのがおすすめしない理由の一つだ
資産の流動性が下がる
個人年金保険に多くのお金を回すと、資産全体の流動性が下がる。
というのも、個人年金保険は現金化するまでに手続きが必要だからである。また、年金受け取り前に現金化すると先に紹介した解約控除が差し引かれて損失が出るため、途中解約の心理的なハードルも高い。
たとえば、個人年金保険を契約してから2年後に住宅が破損し、突然リフォーム費用が必要になったとしよう。資産の多くを個人年金保険で貯蓄していると、保険会社に解約の連絡をしなければならない。さらに解約控除がかかり、結局、払込保険料に比べ解約返戻金は目減りするリスクがある。
いつでも引き出せて、元本割れしない銀行預金と比べれば、流動性が低いことはわかるだろう。
このように、個人年金保険は貯蓄性があるとはいえ、すぐに現金化するには向かない保険商品であることに注意したい。
満期まで保有していても運用効率は高くない
今の資産を将来に向けて増やしたいと考えている人にとって、個人年金保険はリターンがいい商品とはいえないかもしれない。
たとえば、次のような個人年金保険を考えてみよう。
<個人年金保険の契約の例>
被保険者 :45歳の男性
保険料払込期間 :20年間
据置期間 :5年間
毎月の保険料 :2万円
受取方法 :10年確定年金
基本年金年額 :49万8,000円
この例では、45歳から65歳まで毎年24万円ずつ合計480万円の保険料を払い、70歳から毎年49万8,000円を10年間、合計約498万円受け取る。受取率は498万円÷480万円×100≒103.7%だ。2023年時点でこの受取率は個人年金保険としては標準的である。
3.7%も増えたのだから運用は成功と思うかもしれないが、これは25年間(受取期間も含めると35年間)運用した結果だ。年率に換算するとわずか0.245%にしかならない。
インフレに弱い
個人年金保険では物価の上昇、つまりインフレに対応できない可能性がある。
なぜなら、個人年金保険(変額個人年金保険や外貨建て個人年金保険を除く)は、契約時に保険料と将来受け取れる年金額が決まっているため、インフレが進んだとしてもそれに応じて年金額が増えることは基本的に期待できないからだ。
たとえば、2022年はインフレが進み、特に10月以降は消費者物価指数が前年同月比で3~4%程度上昇した(2023年3月24日時点)。一方、個人年金保険の運用リターンは先に述べた通り、2023年の商品では0.2~0.3%程度だ。
つまり、これまで100万円で買えていた物やサービスが103万~104万円に値上がりしているにも関わらず、個人年金保険で運用している100万円は100万2,000円~100万3,000円程度にしか増えていない。
今後も2022年と同様のペースでインフレが進むとは限らないが、もし物価が上がり続けると、個人年金保険で運用しているお金は目減りするかもしれない点は注意が必要だ。
変額タイプは為替リスク・価格変動リスクがある
個人年金保険には、保険料として積み立てたお金を運用に回す変額個人年金保険や、外貨で運用する外貨建て個人年金などの種類がある。これらは「保険」という名前がついてはいるものの、実質は投資を行っているため、通常の個人年金保険のように将来受け取れる年金額が決まっていないことは知っておくべきだ。
たとえば、外貨建て個人年金保険では将来円高が進めば受け取れる年金額は少なくなるし、変額個人年金保険も、運用がうまくいかなければ年金額が支払った保険料を下回ることは十分にあり得るのだ。
保険会社の破綻リスクがある
保険契約におけるリスクの1つに、保険会社の破綻(倒産)リスクがある。現時点で経営状況が良好な保険会社であっても、将来経済の状況が大きく変わって経営が傾くことはあり得るし、実際に2000年代に入ってからも破綻した保険会社はある。特に個人年金保険は、実際に年金を受け取るまでの期間が長くなりがちなため、破綻リスクは常に考えておくべきである。
もっとも、保険会社が破綻しても、契約者を守る仕組みとして生命保険契約者保護機構がある。これにより、保険会社が破綻した後は、別の保険会社(救済会社)か、上記の保護機構が保険契約を引き継ぐことになっている。
ただし保険会社が破綻した場合、支払った保険料の全額が保証されるわけではない。保険契約が引き継がれた場合、会社にもよるが、保険の条件は見直され、結果として将来の年金額が少なくなることもあり得る。
個人年金保険をおすすめするのはこんな人
ここまで個人年金保険がおすすめできないといわれる理由を紹介してきたが、個人年金保険もデメリットばかりではない。条件が合えば選択肢の1つとして検討すべきだ。ここでは個人年金保険をおすすめする人を紹介する。
保険料控除を活用したい人
個人年金保険の保険料は生命保険料控除の対象になる。
生命保険料控除とは所得控除の1つで、払いこんだ保険料に応じて一定の金額が所得から差し引かれる制度だ。税率をかける前の所得が少なくなることにより、所得税と住民税の負担が軽減される。
個人年金保険料が、「一般の生命保険料」とは別枠の「個人年金保険料」として認められるには、個人年保険の契約に「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていなければならない。この特約を付加していない個人年金保険は「一般の生命保険料」の控除になるので注意が必要だ。
個人年金保険料税制適格特約が付加できる個人年金は以下の条件を満たす必要がある。
- 年金の受取人は保険料を支払う者、あるいはその配偶者であること
- 保険料は年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって定期的に支払う契約であること
- 年金の支払いは受取人の年齢が60歳になってから、かつ10年以上の定期または終身の年金であること
たとえば、毎月2万円ずつ個人年金保険に保険料を払っている場合を考えてみよう。年間保険料は2万円×12ヵ月=24万円だ。2012年以降に契約した保険であれば、所得税と住民税でそれぞれ次のような所得控除が受けられる。
▽所得税の生命保険料控除の金額(2012年1月1日以後に締結した保険契約分)
| 年間の支払い保険料 | 控除額 |
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 支払保険料×1/2 + 1万円 |
| 4万円超 8万円以下 | 支払保険料×1/4 + 2万円 |
| 8万円以上 | 一律4万円 |
▽住民税の生命保険料控除の金額(2012年1月1日以後に締結した保険契約分)
| 年間の支払い保険料 | 控除額 |
| 1万2,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 1万2,000円超 3万2,000円以下 | 支払保険料×1/2 + 6,000円 |
| 3万2,000円超 5万6,000円以下 | 支払保険料×1/4 + 1万4,000円 |
| 5万6,000円以上 | 一律2万8,000円 |
保険料は24万円なので、所得税で4万円、住民税で2万8,000円の控除が受けられる。仮に所得税と住民税の税率が10%の人であれば、所得税で4,000円、住民税で2,800円税金が安くなる計算だ。
このように、個人年金保険に保険料を払うことで、税金が軽減され手取りを増やす効果が期待できる。
老後資金の準備に集中でき、iDeCoだけでは不安な人
「老後資金」「教育資金」「住宅資金」は人生の3大支出といわれるが、子どもの教育資金と住宅ローンに目処がつき、老後資金の準備に集中できそうな人は個人年金保険も選択肢となり得る。
老後資金を貯めるための私的年金制度としてはiDeCoもあるが、iDeCoは会社員や専業主婦の場合、掛金の上限が1万2,000円~2万3,000円と決して多くはない。したがって、iDeCoだけでは老後資金が不安なのであれば、個人年金保険もプラスすることを検討しよう。
iDeCoと個人年金保険は別制度のため、税額控除の種類が重複せず併用することは可能である。個人年金保険の用途を老後資金に限定できる場合、途中解約のリスクの高さや資産の流動性が下がるデメリットは大きな問題にはならないだろう。
iDeCoでは一般的にリスクを伴う投資信託で運用することがほとんどである。したがって、iDeCoと比較的安定した運用が期待できる個人年金保険を併用すれば、リスク資産と安定資産を組合せてバランスよく老後資金を準備できる点もメリットだ。
個人年金保険をおすすめしないのはこんな人
個人年金保険には、先に述べたような様々なリスクや制約があるので、それらのデメリットの影響を強く受ける人にはおすすめできない。ここでは具体的にどのような人に向いていないのかを紹介する。
資産運用をする意欲がある、または知識を学ぶ時間がある人
個人年金保険は契約後15年〜20年以内に解約すると解約返戻金が払込保険料を下回るものが多く、また満期まで保有していたとしてもリターンは高くないことは紹介した。
高いリターンが期待できずとも将来の年金額が決まっており、予定が立てやすいというのは確かにメリットだが、資産の運用先としては決して優れているものではないことがわかるだろう。
老後までの長い運用期間が確保できるのであれば、より高いリターンが期待できる運用先や、途中で現金化しやすい他の選択肢が存在する。具体的な金融商品は後述するが、自分で資産運用をする意欲がある人は他の運用方法を検討してみるといいだろう。
貯蓄が少ない人
手元に余剰資金がない時に個人年金保険を始めるのもおすすめはできない。というのも、突然お金が必要になった時にすぐ使えるお金(流動性の高い資産)がないと、結局は個人年金保険を中途解約することになり損をしてしまうからだ。
どの程度の貯蓄が必要かは人それぞれだが、1カ月の生活費の3〜6カ月分はみておきたい。
特に個人年金保険は保険料の支払い期間が長くなりやすい。病気や事故で働けなくなったり、会社が倒産したりなどの理由で突然まとまったお金が必要になることはある。
20〜30代で独身の人
独身の時に貯蓄代わりに個人年金保険に加入していた人が、結婚して支出状況が全く変わってしまい、保険を解約することになるケースは意外と多い。独身の時は無理なく保険料を払えていても、結婚資金や住宅ローン、教育費などが重なり月々の保険料が負担になるためだ。
また、保険料の支払いを継続できたとしても、20代〜30代であれば年金の受け取りまで30年以上ある。その間物価が上がらない保証はないことにも留意すべきだろう。
個人年金保険を始める時は、今の状況だけではなくライフプラン全体を通して中途解約のリスクやインフレのリスクを考慮しておきたい。
すでに別の個人年金保険に入っており、保険料控除を活用できない
個人年金保険に加入すると生命保険料控除という所得控除が受けられるが、この控除額には上限がある。具体的には次の通りだ。
▽生命保険料控除の金額(2012年1月1日以後に締結した保険契約分)
| 年間の支払い保険料 | 控除額 |
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 支払保険料×1/2 + 1万円 |
| 4万円超 8万円以下 | 支払保険料×1/4 + 2万円 |
| 8万円以上 | 一律4万円 |
年間の保険料が8万円以上になると、所得控除の額は4万円に固定される。したがって、すでに年間8万円以上の個人年金保険に加入しているのであれば、追加で新たな個人年金保険に加入しても生命保険料控除額が増えるわけではない。
生命保険料控除のメリットを生かすのであれば、年間の支払保険料にも注意する必要がある。
個人年金保険をおすすめしない人に推奨される金融商品
個人年金保険がおすすめできないと言われる理由と、実際におすすめしない人を紹介してきたが、では他に老後資金を貯めるためにはどのような方法があるだろうか。ここでは有力な金融商品を紹介する。
投資信託
個人年金保険の代わりとなる金融商品としてまず考えたいのが投資信託である。投資信託は元本が確保されている金融商品ではないが、個人年金保険に比べ様々なメリットがある。
まず1つめが、インフレに対応できる商品が多い点である。投資信託の中でも株式を組み入れた株式投資信託は、景気に応じて成長することが期待できる。物価が上がる時は一般的に景気がよくなり、株価も上昇するからだ。
2つめは、中途解約によって手数料を取られることがない点だ。投資信託は銀行の定期預金や保険と違って、満期のある商品ではない。売買のタイミングは自分で決める商品である。したがっていつ売却してもペナルティーを受けることはない。ただし、売却するタイミングで投資信託自体の価額が下がっていると、受け取る金額が元本を下回る可能性はある。
2つ目は、比較的現金化しやすいことだ。投資信託はいつでも売買できるため、まとまったお金が必要になった時でも売却して現金化しやすい。もちろん、価額が下がっている時は売却することに抵抗はあるが、投資信託では自分で売却するタイミングを選べるため、価額が上がっている時に現金化しておくことや、損失が出ていても自分が許容できるタイミングで売ることが可能だ。
投資信託は銀行や証券会社で購入できるが、「つみたてNISA」や「iDeCo」などの非課税制度を利用して積立を行うとより有利に運用ができるだろう。これら2つの制度では運用によって生じた利益にかかる税金が非課税になる。
ただしiDeCoには原則として60歳まで引き出せないという制約があるので、上記で紹介した投資信託の「現金化しやすい」というメリットがなくなることには注意が必要だ。その分iDeCoではさらに掛金が全額非課税になるという税制上のメリットがある。
債券
債券は国や地方自治体、会社が資金を調達するために発行する有価証券だ。基本的に発行体が破綻しなければ満期まで保有することで借入元本(額面)が戻ってくるし、その間に利子も受け取れる。安全性が高い金融商品であるため、銀行預金の延長として始めやすい。
日本国内で最も安全な債券は日本国が発行する国債だが、身近な銀行でも購入できる「個人向け国債」の2023年3月時点の金利は、固定5年で0.18%、変動10年で0.33%(いずれも税引前)である。利率を見ても個人年金保険の比較対象となりうる。
株式
運用期間が充分に確保できるのであれば、株式投資も選択肢の1つである。ただし、株式投資の一般的なイメージである、安い時に買い高い時に売って利益を追及するという投資は大きなリスクも伴う。
個人年金保険との比較対象としておすすめする株式投資は、長期間じっくり保有して、会社から分配される配当金や株主優待で利益を得るスタイルである。こうした利益が積み重なると、売却するときに株価が下がっていてもトータルで損になる可能性を低くすることができる。
個人年金保険の概要
個人年金保険は中途解約のリスクが高く、資産の流動性という点からはおすすめできないことを述べてきたが、逆にいえば他の用途に使いづらいため、老後資金を確実に貯めることができるという点はメリットともいえる。
ここでは老後資金としての個人年金保険の種類を紹介する。
終身年金/確定年金/有期年金とは
一口に年金といっても、その受け取り方はそれぞれである。個人年金保険を選ぶ時はそれぞれのニーズに合った受け取り方式の年金を選ぶことが大切だ。個人年金保険の受け取り方による主な種類は次の3つである。
| 終身年金 | 契約時に決めた年齢から、契約者が死亡するまで年金を受け取れる保険 |
| 確定年金 | 契約時に決めた年齢から、契約者の生死に関わらず一定期間年金を受け取れる保険 |
| 有期年金 | 契約時に決めた年齢から、一定期間年金を受け取れる。ただし、受け取れるのは契約者が生きている時に限られる |
個人年金保険が自分に合わないと感じたら
個人年金保険がおすすめされない理由を紹介してきたが、自分に合っていないと感じても慌てて解約すると損をしてしまうかもしれない。もし見直しや他の投資を検討するのなら、資産アドバイザーなどに相談するのも1つの方法だ。
払い済みにして損失を少なくする提案や、老後資金に適した金融商品の紹介など、広い視点のアドバイスを得られるはずである。
平均利回り4.5%の手堅い利回りファンド
融資型クラウドファンディング「COOL」を活用すれば、最低1万円から円建てで値動きのない 手堅い利回り投資をすることができる。
・平均利回りは4.5%(税引前)*23年10月時点
・3ヶ月〜12ヶ月程度の短期運用ができるファンドが多数
・円建てで株のような値動きなし
・最低1万円から投資ができる
過去には、高級焼肉店やすっぽん・フカヒレ店の優待券がもらえる特典付きファンドや、 より安心感のある保証付きのファンド等、申し込みが多く募集開始直後に満額となったファンドもある。
気になるファンドの投資機会を見逃さないためにも、まずは口座開設をしてみてはどうだろうか。
詳細&無料口座開設はこちらから
文・松岡紀史(ファイナンシャル・プランナー、ライツワードFP事務所)