2018年の日経平均株価は年間では7年ぶりに下落。12年末から始まった「アベノミクス相場」では初の下落となった。米中貿易摩擦をはじめ、依然として世界経済の不透明感が漂うなか、2019年はどうなるのだろうか? 新年特集「2019年にお金で泣く人、笑う人」では、全7回にわたり、相場見通しや個人の所得に関わる税制改正動向、不動産市場見通し、新しい投資のカタチなどをお届けしていく。
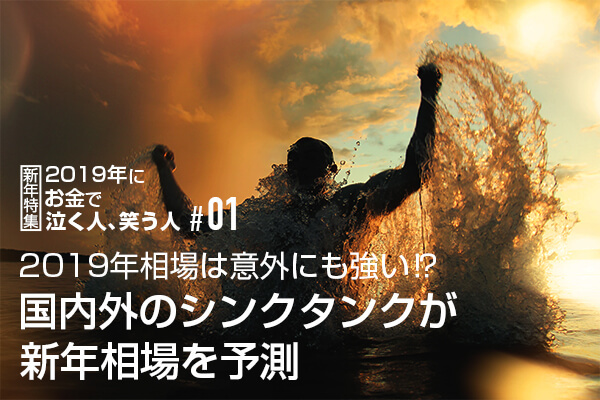
目次
2018年は運用担当者にとって稀に見る「受難の年」となった
2019年の東京株式市場では、企業業績拡大に対する期待感や株主還元強化のトレンドがプラス要因となる一方、米国発の世界的な景気後退や2019年10月に予定される消費税増税がマイナス要因として警戒されている。年末にかけて発行された証券会社などのレポートを読む限り、強気と慎重論が混在し、「市場コンセンサス」と呼べる相場シナリオは固まっていないのが現状だ。
「ファンド勢は全滅に近い」……。外資系証券の営業担当者は2018年の世界の金融市場を振り返り、大口の売買注文を入れる機関投資家の成績不振を指摘する。
2018年大納会(12月28日)の日経平均株価は昨年末比で12.1%下落。この間、米ダウが6.7%安のほか、英FTSE100が12.4%、独DAXが18.3%と欧州主要国でも株価が大幅に下落。トルコや南アフリカ、ベトナムなど新興国株式も軒並み下げ、中国・上海総合指数に至っては24.6%安と世界の主要市場の中で最悪のパフォーマンスに終わった。わずかにインドとブラジルの2カ国でプラスを確保したものの、2018年は世界株安の1年だったと言える。
欧米や新興国の債券も値下がりしたほか、原油や金、銅などの国際商品市況も軟化した。株式や債券、原油など投資するマーケットは異なっても、2018年が運用担当者にとって稀に見る「受難の年」であったことに違いはないようだ。
株式市場では、運用担当者の苦境がより深刻だった。日経平均は12.1%安だったが、多くの機関投資家がベンチマークとする東証株価指数(TOPIX)は17.8%安。米国でも機関投資家が使うS&P500指数は7.0%安と、ダウの6.7%安よりも下落率が大きかった。TOPIXやS&P500といった機関投資家向けの株価指数の下落率が大きいことは、機関投資家の選択眼にかなう好業績の優良銘柄の売り圧力が強く、運用が難しかったことを示している。