本記事は、安西洋之氏、中野香織氏の著書『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』(クロスメディア・パブリッシング)の中から一部を抜粋・編集しています
本物と偽物
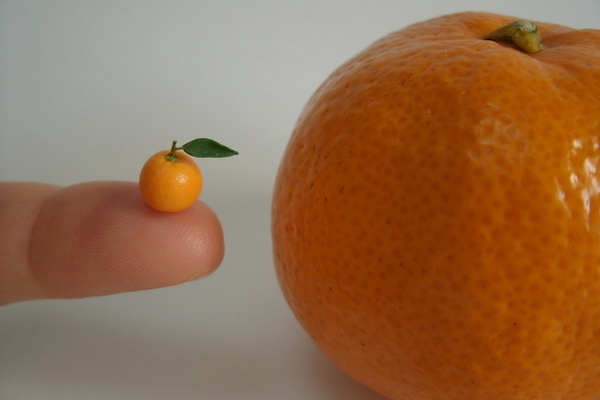
ラグジュアリーの普遍的な知覚として不可欠な「オーセンティシティ(正統性、本物であること。形容詞オーセンティックの名詞形)」について考えてみましょう。
本物(オーセンティック)に高い価値が与えられるからこそ、常につきまとうのが偽物(フェイク)です。従来のラグジュアリービジネスにおいても、「偽物の排除」は常に課題となってきました。
現在は多くのハイブランドがリセール市場(中古市場)に参入していますが、その主な目的は、市場から偽物を排除すること。もはや本物をつくったブランド関係者しか見分けられないので、ブランド側が直々、リセール市場に参入し、たとえば「認定中古」なるジャンルをつくって本物の価値を守り続けているという状況です。
フェイクと知って購買する層の中には、「自分で楽しむだけなら問題ないだろう」と楽観視する人や、あえて偽物を身に着けるスリルを楽しむという人もいて、偽物市場をいっそう複雑にしています。財務省の統計によれば、2021年上半期の商標侵害品の輸入差し止め実績は34万点で、前年同期比8割増とのことです。すり抜けている偽物も相当数あると推測されます。
NFT時代に突入し、デジタルの偽物まで問題化しています。エルメスは2022年1月、自社のバッグ「バーキン」をデジタル上で模した作品の製作者に対し、商標権侵害を理由にニューヨーク連邦裁判所に提訴しました。デジタルも含めた偽物との闘いは、今後さらに激化することが予想されます。
「偽物」がアートに転じるとき
ラグジュアリーの知的財産(知財)侵害は、主にブランド名やロゴですが、先ほど触れたエルメスのバーキンのように立体商標を取るブランドもあれば、ティファニーのブルー、ヴーヴ・クリコのイエロー、クリスチャン ルブタンの靴底の赤、スターバックスのグリーンのように色で商標登録をしているブランドもあります。
「本物」の肥大化とともに偽物も氾濫する。そんな時代に、本物と偽物の攻防そのものを一段高いところに立って利用するかのような現象も出現しました。2018年にアレッサンドロ・ミケーレ率いるグッチは、「ダッパー・ダン」コレクションで「本物と偽物とのコラボ」なるものをやってのけました。
ダッパー・ダンとは、1982年から1992年にかけて、ニューヨークのハーレムを拠点にハイブランドの華麗なる海賊版(ブートレグ)をつくり、「ブートクチュール」というジャンルを生んだアフリカ系アメリカ人のデザイナーです。当時のヒップホップ界のスターやボクサーの間で人気でしたが、最終的にはブランド側に訴えられてビジネスを終えました。
グッチも当時の「被害者」だったわけですが、ミケーレはブランド価値を毀損したほかならぬその「加害者」とコラボして、「正規」のコレクションをつくったというわけです。フェイクと融合した本物は、もはや真偽を問うことすらナンセンスにしてしまう妖しのオーラを放っていました。ちなみにグッチはこのコラボを「ファッションサンプリングの比類ない例」と自賛しています。
ハイブランドが海賊版もどきをつくって高く売ってしまう例もあります。
2016年にヴェトモンのデムナ・ヴァザリアは、DHL(国際宅急便)の赤いロゴが入った黄色のTシャツを発表しました。従来の基準では到底エレガントとはいえず、むしろ「バッタもの」にしか見えなかったこの製品は、約330ドル(約3万5,000円)で売られ、黒海沿岸の国・ジョージア出身のデザイナーは一躍、スターになります。
その後、ヴァザリアはバレンシアガのクリエイティブディレクターに抜擢され、イケアの青いショッピングバッグ(100円)と酷似した青いレザーバッグを2,145ドル(約23万円)で販売します。安っぽい「本物」と高品質で品格さえたたえた「海賊版」(とあえて書いてしまいます)は、本物/偽物論争の出口なき迷宮に私たちを連れ込んでいき、議論されればされるほどヴァザリアの名声も上がりました。
実際、本物と偽物の関係には、知的な興味を呼び起こさせるケースが少なくありません。両者は互いに互いを必要とし、時に世の価値観を転覆してしまうことさえあります。
シャネルが生んだ「偽物」ムーブメント
その最たる例が、ココ・シャネルによるコスチューム・ジュエリーでしょう。「本物のジュエリー」誇示を下品と断罪し、「偽物」で遊ぶことこそ洗練の証としてコスチューム・ジュエリーを世に出したことは、前述したとおりです。本物と偽物を融合してしまったシャネルは、結果として、アクセサリーの可能性を大幅に広げることに貢献します。
物理的組成において同じであることを「本物」の条件とするならば、現在、普及が拡大している合成ダイヤモンドも、「本物」として堂々、ダイヤモンドの仲間入りをすることになります。
天然資源は有限です。地球環境に配慮するならば、資源を枯渇させるまで「天然」に唯一絶対の「本物」としての価値を求めるという発想は、新しいラグジュアリーを考えるときには、どこかで転換しなくてはならないものなのかもしれません。理屈ではそのように受け取られていますが、合成ダイヤは今のところ、手頃な価格の代替品の地位に甘んじており、ラグジュアリーにはなりえていないように見えます。
物理的組成が同じであれば、天然でなくても、合成ダイヤは養殖真珠のようにラグジュアリーになりえてもよいのではないか? なぜなりえないのか?
違いは「ロマン主義」的な観点に立つと見えてきます。
天然ダイヤと組成が同じ合成ダイヤは「美しい」ですが、今のところ、崇高な感覚をもたらしません。そこには、ビジネスを行う人の、ロマン主義的視点を取り入れた何らかのアプローチが必要なのではないでしょうか。
ラグジュアリーは、ロマン主義だけでつくることはもちろんできませんが、物理的条件やマーケティング法則をすべて満たせば成立するというものでもありません。「美」を超えて「崇高」の歓喜に至る、そこに何らかのロマン主義的要素が求められるということです。
コピーされることは本物の証?
ジュエリー界の判断はいったんさておき、ファッションの知財の話に戻しますと、シャネルがコスチューム・ジュエリーをファッション化したことで、(洋服・バッグと同様に)シャネルのロゴをつけたアクセサリーのコピー商品も大量に出回ります。
それに対してシャネルは、「コピーされることは本物の証」としてまったく動じませんでした。世が本物/偽物をめぐって右往左往すればするほど、彼女自身のブランド価値は高まっていきました。
現在のシャネル社は、ほかのハイブランドと同様、コピー商品に対して厳格な態度をとっていますが、ココ・シャネルの存命時は、なぜコピー放置の氾濫がかえって本物のシャネルの価値上昇に貢献することになったのか。ビジネスは本当に毀損されなかったのか。時代がのどかだったためか、シャネル本人とシャネル製品の稀有な特質のためなのか。
いまだ謎も残りますが、「モード、それは私よ」と言い切り、修道院育ちであるというオリジンに立ったオーセンティックな自分が生み出すものは、世間の評価を覆してさえ本物になる。そんな創造を続けたシャネルのロマン主義的な態度は、ラグジュアリーをつくり出す側のインスピレーションの源泉になるはずです。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます
