(本記事は、ジム・ロジャーズ氏の著書『日本への警告 米中朝鮮半島の激変から人とお金の動きを見抜く』の中から一部を抜粋・編集しています)

故郷にとどまるな
私は娘たちに「家からできるだけ離れた大学に行きなさい」と言い続けている。それが自分自身のことを知り、世界のことを知り、やがては故郷の本当の姿を教えてくれることになるからだ。
結婚をする前の若い頃は、少なくとも2年は自国を離れて自分自身や世界について学ぶべきと私は考える。故郷にとどまろうなどとは決して思うべきではない。
私はアラバマ州の田舎で育った。そしてずっと遠くに行きたいと願っていた。
今でも覚えているのだが、16歳のときにガールフレンドに「他の場所に行ったことがない」と打ち明けると、彼女は「私はバーミンガムにもモービルにも行ったことがあるわよ」と答えた。それはいずれもアラバマ州の中の都市なのだが……。私が望んだのはそういうことではない。アラバマのことをいくら見ても意味がない。そう思っていた。
私の言葉に少しでも共感するのなら、外へ出て、誰も知り合いがいない、言葉も通じない国へ行ってみよう。冒険は人生を素晴らしいものにしてくれることを私は保証する。
「私は日本のことをよく知っているが、他の国のことはあまり知らない」と言う人がいる。そうした人は、実は日本を半分しか知らないのだ。本当の意味で日本を知るには、日本をいったん立ち去る必要があるのだから。
故郷を離れるのであれば、遠ければ遠いほど望ましい。ところが、残念ながら日本人は内向き志向だ。それはパスポートの取得件数にも表れている。
統計によると、日本のパスポート保有率(2017年)は22.8%にとどまっているという。アメリカの同年のパスポート保有率が42%であることを踏まえると、日本の低さがわかるのではないだろうか。しかも、日本のパスポートならビザなしで入国できる国の数が189ヵ国もあり、パスポートの自由度では韓国と並んで世界1である。実は日本人は世界で最も海外に出やすい環境が整っているにもかかわらず、まったく活かされていないというわけだ。
このような状況は何年もの間変わっていないが、歴史を振り返ると、かつては日本も確かに外向きの時代があった。だからこそ、日本人はあれほどの成功を収めたのだ。
日本では素晴らしいイタリア料理を食べることができるが、これは世界の料理に触れ、一流のイタリア料理が何たるかを学んだからこそではないか。もし日本人が今のまま内向き志向を続ければ、今後は日本でも二流のイタリア料理しか食べられなくなるかもしれない。そうなる前に、世界を見て一流のものを日本に取り入れよう。
今はパスポートを取ることも、ビザを取ることも昔より簡単にできる。自国から出るのに必ずしもお金は必要ない。留学はもちろん、バックパック、ヒッチハイク、外国で仕事を見つける……。さまざまな方法がある。私のように車やバイクで世界一周をしろとは言わない。せめて住み慣れた場所を離れ、見知らぬ土地に身を置いてみよう。
そこで、成功につながる機会を見つけられるかもしれないのだから。
結婚・出産を急ぐな
かつての私は、「子どもなど絶対につくらない」と考えていた。
5人兄弟の長男として育った私は、弟たちの世話がとても大変で、大人になったら絶対に子育てなどという余計な苦労を抱えたくないと思っていたのだ。
子育てにはたくさんのお金と時間とエネルギーがかかる。だから、以前の私は子どものいる人たちのことを、とても気の毒に思っていた。何と愚かなことを、人生を台無しにしている、と。
今は自分が間違っていたことがわかる。完全な間違いだった。2人の娘は本当に可愛く、24時間一緒にいたいと思っている。娘たちを授かってから幸福感は高まり、人生の喜びを感じ、涙する機会も圧倒的に増えた。子どもが生まれると人生が変わる、と多くの人が言う。若い頃にはとても信じられなかったが、今はその言葉が真実であることを知っている。
しかし、若いうちから結婚や出産といったものに関わることには反対だ。私の娘たちにも、「28歳までは結婚してはいけない」と何度も言ってきた。「もしその前に結婚したいというのなら、ちょうどいい年齢まで部屋に閉じ込めるぞ」と。
ほとんどの人間は23歳のときには何も知らないものだ。自分自身についても、そして世界についても。自分がどのような人生を歩み、どんなパートナーを望むのかも、なかなか理解することができないだろう。物事がわかるようになるまで結婚を待つことは、人生で成功を得るうえで重要なことだ。
もっとも、私自身、結婚に関しては手痛い失敗を経験している。20代のときに経験した最初の結婚は大失敗で、自殺を考えたくらいだ。やはり、自分のことを何も知らない若者にとって、結婚は悲劇となり得る。
私が人生で初めて子どもを授かったのは60歳を過ぎてからだった。もし私が30歳の頃に子どもがいたとしたら、子どもにとっても、子どもの母親にとっても、そして私自身にとっても、ひどいことになっていたことだろう。
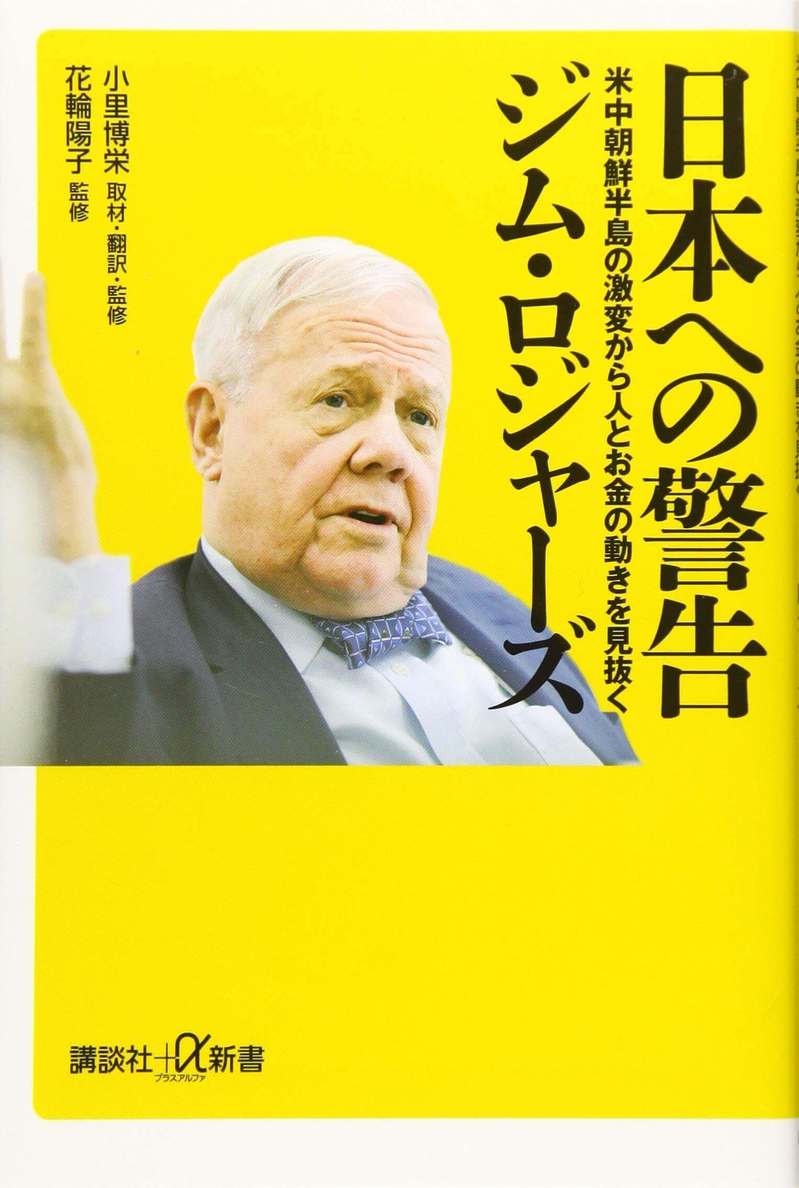
※画像をクリックするとAmazonに飛びます