(本記事は、久慈直登の著書『ビジネスで使えるのは「友達の友達」』株式会社CCCメディアハウス2018年12月15日刊の中から一部を抜粋・編集しています)
短期のコラボこそが最高のコラボ

2000年代初頭、ブライアン・ウッツィはトップレベルの研究チームがどのように結成され、協力するのかに関心を抱いた。とりわけさまざまな業界の社会的ネットワークがチームに与える影響に興味を持ち、調査を科学の世界からスタートして他分野へと広げていった。すると科学界では、チームワークが画期的な発見をもたらすケースが増加していた。
ウッツィはステファン・ボクテ、ベンジャミン・ジョーンズと共同で研究を行い、メンバーの多い研究チームが影響力のある科学論文を生む率が急速に高まっていることを突き止めた。ウッツィたちは1955年から2000年までに発表された2000万本近い論文と200万を超える特許を集めて、調査した。すると1つの研究チームに属するメンバーの数は、45年間でほぼ2倍に増えていた。55年には研究チームの平均人数は1.9人で、研究者が1人で働く傾向が強いことを示唆していたのが、00年には3.5人にまで増加していた。
科学者が1人でこなす仕事量と、チームで取り組む仕事の量も変わった。社会科学者に限っていえば、チーム体制で発表された論文は50年代の17.5%から、00年には51.5%に増加した。つまり研究室で1人こつこつ実験に励む天才科学者のイメージは50年代には的を射ていたのだが、最近の科学者はチーム体制でその才能を発揮しているのだ。
ウッツィとボクテとジョーンズの3人組はまた、ソロ活動よりもチームワークのほうがその分野に大きなインパクトを与える傾向が顕著になっていることも突き止めた。論文のインパクト(影響度)を判断するには、被引用数を使うのがベストだ。後発の論文に引用された回数は、その論文の質とインパクトを推し量る指標として重宝されている。
50年間の研究を調べると、執筆者が複数いる論文は執筆者が1人だけの論文よりも被引用数が多く、その傾向は年と共に強くなっていた。50年代、共著の論文が引用される回数は単独の論文の1.7倍だったが、00年には2.1倍まで増えていた。自己引用(過去に自分が書いた論文を自分で引用すること)の数を調整しても、共著の論文のインパクトは変わらず、被引用数の上昇も変わらなかった。チームワークの評価が高まっているならば、次に知りたいのは「最強チームの作り方」だ。
ウッツィは新たに研究グループを編成し、このテーマに取り組んだ。今回のグループでは、55年から04年までに発表された科学論文を調査した。前回より論文の本数は減ったが、それでも11万5000人の執筆者が32の学術誌に発表した約9万本の論文を調べたのだから、規模が小さいとはいえない。
ロジャー・ギメラ、ルイス・アマラル、ジャレット・スピロと共にウッツィがとりわけ関心を寄せたのは、同じチームで共同作業を行った回数だった。天才的な洞察は、少人数のチームが長年共同で研究を重ねた賜物なのか。それとも短期のコラボレーションから生まれるのか(論文を発表するたびに共同執筆者の顔ぶれが少しずつ入れ変わることからもわかるとおり、ウッツィは後者の可能性を信じていたようだ)。
謎を解くには、論文のクオリティを吟味しなければならない。研究チームは論文が掲載された学術誌のインパクトを、クオリティの指標にした。すると意外なことに、何度も共同研究をしているチームの論文が掲載されたのはインパクトの弱い学術誌だった。一方、インパクトの強い学術誌には、初めて結成されたチームによる論文が多く見られた。後者は論文が発表されると解散し、メンバーはそれぞれ別のチームへと散っていった。どうやら臨時のチームこそが、最強のチームらしい。
この結果は、科学研究の性質にも起因している。仮説を立てて、データを集め、草稿を準備――。論文の発表にこぎ着けるまでには、多大な労力がかかる。冴えた仮説が1つあれば影響力のある論文が書けるわけではない。仮説はデータの山で支えてやらなければならない。たいていそうした論文の作成に最適なのはステータスが高く、発想力に定評のあるベテラン研究者と、経験不足を時間と体力で補える若手の混成チームだ。
だがここからが悩ましいところ。せっかく強いチームを結成しても、そのままのメンバーで研究を続けると、往々にして効果は減っていく。最初のプロジェクトが成功しても、次のプロジェクトには最初と同じ時間と体力を割けないのだ。グループは、常に新鮮な「血」を必要とする。そして新鮮な血を補給するには、すみやかに協力体制を組むことができて、なおかつ新入りを調達できるネットワークが要る。これは科学の分野に限った話ではない。
ペイパル・マフィアの面々はeBayを辞めたその足で、新しい会社を設立したりはしなかった。そのまま一緒に会社を作るかわりにいったんテクノロジー業界に散らばり、昔の同僚が提供してくれるアイデアや資金を享受しつつ、新しい協力者とタッグを組んだ。大物イノベーターがただ寄り集まってチームを結成するのではなく、散らばって新会社を立ち上げたことに意義があった。
「人柄も仕事の癖も知り抜いた仲間ならではの効率のいいコミュニケーションを犠牲にしてでも、創造性を高めるのにメンバーの入れ替えは欠かせない」と、ウッツィは説明している。
eBayによる買収後、ペイパルの面々は新しいチームを探し、さまざまなプロジェクトに関わることを余儀なくされた。元同僚が新たに起業家と組んだチームにしばらく参加し、プロジェクトが終われば次に移るといった働き方も、彼らの中ではめずらしくなかった。会社を立ち上げ、別の会社に投資し、さらにまた別の会社の顧問を務めるというふうに複数のプロジェクトに同時進行で関わるメンバーも大勢いた。シリコンバレーのネットワークに散ったメンバーの関係性は、科学者のコラボレーションのあり方とよく似ている。
個人にとって、ペイパル・マフィアの成功が意味するところは明らかだ。ネットワークはあればいいというものではなく、大切なのはその密度。前章で見た通り、クラスタと協力者を見つけることは非常に重要だ。新旧のツテを取り混ぜて簡単にチームを作れるならば、あなたのネットワークは素晴らしくバランスが取れている。そうしたチームが作れないならば、同じ相手と働きすぎているのかもしれない。またプロジェクトを立ち上げるたび新しい仕事のチャンスをつかむたび、メンバーをいちから新規開拓しなければならないなら、そのネットワークは理想的とはいえない。
一方、組織にとって、マフィアの成功が意味するところはもう少し重い。会社はたいてい組織図の上に成りたっており、組織図は部署と部署の間にしっかりと壁を設けている。効果的な協力体制を敷くのに、こうした壁は百害あって一利なしだ。組織は階層型の縦割構造にするよりも、科学者のネットワークのように広く、ペイパル・マフィアのように密度を濃くしたほうがたいてい成功する。
組織を流動的なネットワークに変える
組織のなかでは、おおむね組織図がネットワークを決める。会社が大きくなれば、スタッフ全員が同じ場所で全員と協力して働くのは不可能になる。そこで自然と上下関係ができる。専門ごとにグループ分けがされ、直属の上司を割り当てられる。そうすることで、上下間のコミュニケーション速度はたしかに上がる。
だが横のコミュニケーションは減速するか、ときにはストップしてしまう。さらに悪いことに、プロジェクトに新しい協力者を引き入れる余地はほぼ皆無になる。チームは「同じ上司の下で働く人々」として定義され、メンバーの入れ替えは異例の事態となる。だが多彩な才能をプロジェクト単位で入れ替えることを、異例どころか鉄則にした企業もあるのだ。
世界的に知られるデザインコンサルタント会社IDEO(アイディオ)は、そんな企業の鑑。IDEOは91年に4つのデザイン事務所が合併して生まれた。今も幹部の1人として会社を率いる共同設立者のデービッド・ケリーによれば、彼らが創業時に目指したのは、親しい友人とともに働ける職場だった。また「友達と働く」感覚を大事にするためだろう、40人を超える規模にはしたくないとも述べていた。
だがIDEOは成長した。しかも急速に。アップル社初のコンピューターマウスをデザインし、映画『フリー・ウィリー』のために全長が7.5メートルもある機械仕掛けのイルカを作り、ABCの報道番組『ナイトライン』で一般的なショッピングカートをデザインし直すプロセスを公開するといった華々しい成功を連発した。90年代を通じてIDEOほどデザイン関係の賞をいくつも受賞したデザイン事務所は、ほかにない。成功はさらなる成功を呼び、さらなる成功はさらなる注文を引きよせ――会社は拡大を迫られた。
今日、IDEOは世界中にオフィスを展開し、スタッフは700名を超える。「こぢんまりとした会社で友達と働く」感覚を保つのはさすがに難しいが、プロジェクトごとに組織図を作ることで、そんな感覚をなくさずにいる。IDEOではクライアントから注文が入るたび、いちからプロジェクトチームを立ち上げる。エンジニアに建築家、心理学者に人類学者など、その顔ぶれは実に多彩だ。
多彩なバックグラウンドを持つ人材をミックスすることで大方の企業にとっては夢のような多様性と創造性を実現しているのだが、その裏にはIDEOならではのユニークな構造がある。チームでプロジェクトに取り組み、終われば解散して別のチームに散っていくやり方が、1つの成功のカギなのだ。プロジェクトごとにチームを作るので、その構成は毎回変わる。いずれのチームも優秀なデザイナーを他分野のスペシャリストと組ませることで、素晴らしい相乗効果を生んでいる。
「IDEOのデザイナーは精鋭揃いだから、そのときどきで身体の空いているデザイナーをランダムに組みあわせるだけでチームが組める」と、デービッド・ケリーは説明する。「そして最後には奇跡を起こす。冴えた発想で突破口を開き、クライアントに満足してもらう」
実際のチーム作りはランダムにはほど遠い。パーフェクトな人材選びには、社内のソーシャル・プラットフォームが使われる。このプラットフォームには全従業員のプロフィールが掲載され、学歴、能力、過去のプロジェクトでの実績といった情報を提供する。プロフィールは社内全体で共有され、検索やタグづけも可能。これがあるからこそ、社内全体から素速く効率よく適材を探すことができるのだ。逆に、スタッフがプラットフォームを使って自分のスキルと興味分野に適したプロジェクトを探すこともできる。
ユニークなやり方でチームを作りユニークなプロジェクトに取り組むIDEOの組織図は、ペイパル・マフィアのネットワークに近い。ただしIDEOの場合は組織内のネットワークだ。新しいプロジェクトが生まれるたびに幅広い人材の中からチームが結成され、数カ月してプロジェクトが終わればチームは解散する。メンバーは社内の大きなネットワークに戻って、次の業務を待つ(解散前に次の仕事に関わっている場合も多い) 。そして次のプロジェクトに参加すれば、そこには新しいチームメート――と、昔なじみが数人――待っているという具合だ
ペイパル・マフィアの大規模なネットワークであれ、科学者の研究チームであれ、IDEOのようなデザイン会社であれ、教訓は同じ。チームを流動的に組めるネットワークこそが、最高のネットワークだ。チームを組むとなると、人はとかく昔から一緒にやってきた信頼できる相手に声をかける。長年固い絆で結ばれてきたチームこそが、最高のチームだと思いこむ。けれどもチームやネットワークの性質に焦点を当てた研究を参考にするなら、最も生産性が高いのはその場限りのチームなのだ。
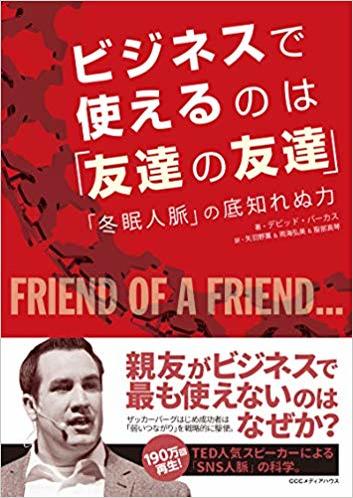
※画像をクリックするとAmazonに飛びます





