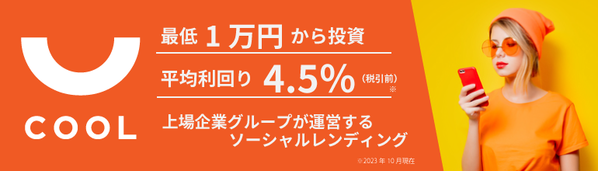「医療費控除の金額は保険金をもらった場合にどう変わるのか?」。医療保険などから保険金(給付金)が支給された場合には、医療費控除額の計算の際に、医療費の額から保険金(給付金)の額を差し引くことが必要だ。この記事では、保険金や給付金が支給された場合の医療費控除の計算方法や、それらが医療費より多かった場合などにどうすればよいかを解説する。
医療費控除保険金/給付金に関するQ&A
Q.医療費控除とは?
A.医療費控除とは、10万円以上(または所得金額の5%)の医療費を支払った場合に税金が減額される制度だ。減額となった税金は還付金として戻ってくる。手続きは、サラリーマンでも確定申告が必要になる。
A.医療費控除とは、10万円以上(または所得金額の5%)の医療費を支払った場合に税金が減額される制度だ。減額となった税金は還付金として戻ってくる。手続きは、サラリーマンでも確定申告が必要になる。
Q.保険金/給付金を受け取った場合、医療費控除にどう影響する?
A.医療保険などからの保険金(給付金)を受け取った場合は、保険金額を医療費の額から差し引くことが必要だ。したがって、受け取った金額分だけ医療費控除額は少なくなる。
A.医療保険などからの保険金(給付金)を受け取った場合は、保険金額を医療費の額から差し引くことが必要だ。したがって、受け取った金額分だけ医療費控除額は少なくなる。
Q.保険金/給付金が医療費より多い場合は?
A.受け取った保険金(給付金)が、実際にかかった医療費より多いケースもあるだろう。この場合は医療費控除は申請できない。ただし、保険金(給付金)の計算はあくまでも対象となる医療費ごとに計算するから、ある治療の保険金が治療費を上回った場合でも、上回った分を別の治療費から差し引くことは必要ない。
A.受け取った保険金(給付金)が、実際にかかった医療費より多いケースもあるだろう。この場合は医療費控除は申請できない。ただし、保険金(給付金)の計算はあくまでも対象となる医療費ごとに計算するから、ある治療の保険金が治療費を上回った場合でも、上回った分を別の治療費から差し引くことは必要ない。
保険金/給付金を受け取ったら確定申告は必要?
保険金や給付金を受け取ったからといって「必ず確定申告が必要」というわけではない。そもそも医療保険などで受け取れる入院給付金や手術給付金などは「非課税」とされており、いくら受け取っても所得税はかからない。
ただし、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要だ。領収書や医療費通知(医療費のお知らせ)などは紛失しないよう大切に保管しておこう。
【合わせて読みたい】
・【保存版】インフレから資産を守る。債券投資の基本を学ぶ記事21選
・【保存版】今更聞けない資産運用の基本を学べる記事31選
・[PR]全国190万の選択肢から最適な資産アドバイザーを選べる―― ZUU Advisorsに寄せられた口コミを紹介
医療費控除額の計算から保険金/給付金を差し引く
医療保険などに加入している場合、給付金を受け取ることもあるだろう。給付金を受け取ったら、医療費控除額の計算の際に給付金額を差し引かなければならない。
医療費控除の算出法は、支払った医療費から10万円(または総所得金額の5%)と、受け取った給付金額の両方を、下式のとおり差し引くことになる。
医療費控除額
= 1年で払った医療費- 10万円(または総所得金額の5%)- 受け取った保険金額
●差し引く必要がある保険金/給付金の種類
差し引く必要がある保険金(給付金)の種類は以下のものだ。
・生命保険や損害保険により給付される医療保険金や入院給付金、手術給付金、通院給付金、がん診断給付金、特定疾病(三大疾病)給付金など
・社会保険や共済などから給付される出産育児一時金や高額療養費など
・事故などの際に受け取った損害賠償金
・会社の互助会などから受け取るお見舞金など
●還付金額の計算方法
医療費控除の還付金額は、前述のとおり医療費控除額に税率をかけたものとなり、下の式で表される。
還付金額 = 医療費控除額 × 税率
税率は、住民税は10%だが、所得税は、課税所得金額により税率が異なるため、下表から税率を求める必要がある。
【課税所得金額による所得税率一覧】
| 課税所得金額 | 所得税率 |
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超~330万円以下 | 10% |
| 330万円超~695万円以下 | 20% |
| 695万円超~900万円以下 | 23% |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
例として、年収900万円(課税所得金額650万円)の人が、医療費として50万円支払って20万円の給付金を受け取った場合を考えてみよう。医療費50万円—給付金20万円=30万円で、そこからさらに10万円を差し引くと、医療費控除の金額は「20万円」とわかる。
上の所得税率一覧で見ると、この人の所得税率は20%となっている。還付金として戻ってくるのは、医療費控除額20万円×所得税率20%=4万円だ。(※現在は所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が発生するが、ここでは考慮していない。)このほか、20万円×住民税率10%=2万円分、翌年の住民税が安くなる。
受け取った保険金/給付金が医療費より多い場合は?
医療保険などの加入状況によっては、受け取った保険金や給付金が医療費より多いケースもあるだろう。この場合どうすればよいのか。
●保険金/給付金が多い場合、原則として医療費控除は受けられない
医療費控除の金額は前述のとおり、医療費の金額から10万円と、受け取った保険金(給付金)の金額を差し引いたものとなる。したがって、医療費より受け取った額が多い場合は、医療費控除は受けられないのが原則だ。
●対象となる医療費ごとに計算し、ほかの医療費からは差し引かない
保険金(給付金)を差し引く計算は、対象となる医療費ごとに行う。ある医療費で給付金が上回っても、上回った分の金額をほかの医療費から差し引く必要はない。
例えば、ある年に病気での入院と歯の治療の両方をしたとしよう。入院については入院給付金を受け取り、その金額が入院のための実際の費用を上回ったとする。一方、歯の治療では、給付金は特に受け取らなかったとする。これらの費用と給付金の金額が以下のようだとしてみよう。
・入院……医療費:15万円、給付金:20万円 ・歯の治療……医療費:20万円、給付金:なし
この場合、入院について実際の費用を上回った分の給付金額5万円を、歯の治療費20万円から差し引く必要はないのである。
したがって、入院費用については医療費控除の対象とならないが、歯の治療費は対象となる。歯の治療費20万円から10万円を差し引いた残りの「10万円」が、医療費控除の額となるのだ。
保険金/給付金の申告漏れはバレる? バレない?
「もらった保険金を申告しなくてもバレないのでは?」と思う人もいるのではないだろうか? しかし、申告漏れはバレる可能性があるので注意しよう。
例えば、年末調整で「生命保険料控除」を受けながら、一方で生命保険からの保険料を計算に入れずに医療費控除申告をしたとする。すると、税務署が「おかしい」と思う可能性が当然のこと高くなる。
このような場合、税務調査が入ることも大いにあり得る。税務調査で不正申告が明らかになると、医療費控除が修正されたうえに、延滞税と重加算税もかかってくる。保険金の申告漏れは絶対にやめるべきだ。
治療が年をまたいだ場合の保険金/給付金額の計算は?
治療が年をまたぐことはよくあることだ。計算例として、医療費の支払いが12月と1月の2回にわたり、給付金の受け取りは2回分を一括で受け取った以下のケースを考えよう。
・医療費……12月支払い:20万円、1月支払い:10万円
・給付金……2回分の一括受け取りで6万円
この場合は、12月分と1月分の支払金額により、給付金額の「按分」を行う。按分とは、支払額を比率によって割り振るものだ。
12月分の支払額と1月分の支払額の比率は「20万円:10万円」だから「2:1」だ。したがって、給付金額の2/3を12月分に、1/3を1月分に割り振れば、支払額の比率となるから、12月分・1月分それぞれの給付金額は次のように按分される。
・12月分の給付金額……6万円 × 2/3 = 4万円
・1月分の給付金額……6万円 × 1/3 = 2万円
保険金/給付金の支払いが翌年になった場合は?
給付金の支払いが治療の翌年となり、3月15日の確定申告期限に間に合わないこともあるだろう。この場合どうすればよいか。
●保険金/給付金額が確定している場合
給付金の金額が確定していて、支払いが確定申告期限に間に合わなかった場合は、確定している給付金額を医療費から差し引く。基本的な考え方として、給付金の支払いが翌年になっても、医療費からの差し引きは医療費を支払った年に行うようにするのである。
●保険金/給付金額が未確定の場合
医療費を支払った年の翌年に受け取る予定の給付金の金額が、確定申告期限までに決まっていないこともあるだろう。
その場合、金額が未確定でも受け取り予定の給付金は、給付金の額を見積もって、医療費控除額を計算する。
翌年になり実際に給付金が支払われた際、見積もった給付金額が支払われた給付金額と一致すれば、手続きはそれで終わりだ。しかし、支払われた給付金の額が見積もり額より多かった、あるいは少なかった場合には、以下の手続きが必要となる。
・支払われた保険金/給付金が見積もり額より多かった場合
申告した医療費控除額は実際の医療費より多かったことになるから、「修正申告」をして支払いが足りない分の税金を追加で支払うことになる。
・支払われた保険金が見積もり額より少なかった場合
申告した医療費控除額は実際の医療費より少なかったことになるから、「更正の請求」をして払いすぎた税金の還付を受ける。
医療費の支払者と保険金/給付金の受取人が違う場合は?
医療費の支払者と保険金の受取人が違う場合はどうすればよいのだろう。例えば、共働きである妻の出産費用を夫が支払ったとする。その後、妻の会社から出産給付金が支給されたとしよう。すると、医療費の支払いは夫で、給付金の受け取りは妻ということになる。
しかし、この場合でも、妻が受け取った給付金を夫の医療費から差し引く必要がある。受取人が誰であっても、出産給付金は出産費用を補填するために支払われたものだからだ。
出産育児一時金なども保険金/給付金に含まれる?
「出産育児一時金なども給付金に含まれるのか」と迷う人もいるだろう。前述のとおり出産一時金も、給付金に含まれる。
基本的な考え方として、医療費を補填する目的で支払われたお金は、その名称が何であろうと医療費から差し引かなければならない。一方、「出産手当金」などのように、産休中の給与を補填する目的で支払われるお金については、医療費から差し引く必要はない。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間で一定額以上の医療費を支払った場合に、税金が減税になるものだ。医療費は1月1日~12月31日までの間に支払ったもののうち、原則として10万円を超えた部分が対象となる。ただし、総所得金額が200万円以下なら、総所得金額の5%を超えた部分が対象だ。
所得税、復興特別所得税及び住民税が対象で、減税は所得控除により行われる。所得控除とは、医療費控除の金額を総所得金額から差し引くものだ。したがって、実際に減税される金額は、医療費控除の金額に税率をかけたものになる。
医療費控除を受けるためには、サラリーマンでも年末調整では行えず、確定申告が必要だ。確定申告をすることで、所得税の場合、減税分の金額は還付金として戻ってくる。住民税の場合は、翌年の税額に反映されることになる。
医療費控除はぜひとも活用したい制度だが、ここまで紹介したとおり仕組みがやや複雑でわかりにくい。とくに本業の忙しい方にとっては、確定申告時に大きな負担となるだろう。
保険や税金、さらに資産運用まで含めたお金の問題については、横断的な知識を持ったプロにまとめて相談するのも1つの手だ。ZUU onlineではそのような資産アドバイザーと個人をマッチングするサービスを行っており、複数の専門家から無料で提案を受けることが可能だ。会員登録は以下のフォームから行える。
融資型クラウドファンディング「COOL」を活用すれば、最低1万円から円建てで値動きのない 手堅い利回り投資をすることができる。
・平均利回りは4.5%(税引前)*23年10月時点
・3ヶ月〜12ヶ月程度の短期運用ができるファンドが多数
・円建てで株のような値動きなし
・最低1万円から投資ができる
過去には、高級焼肉店やすっぽん・フカヒレ店の優待券がもらえる特典付きファンドや、 より安心感のある保証付きのファンド等、申し込みが多く募集開始直後に満額となったファンドもある。
気になるファンドの投資機会を見逃さないためにも、まずは口座開設をしてみてはどうだろうか。
詳細&無料口座開設はこちらから
【関連記事】
・保険代理店は何をしてくれる?メリット・デメリット、信頼できる代理店の見つけ方とは?
・国民共済より県民共済?「都道府県民共済」がコスパ最強といわれるワケ
・失業保険と扶養控除は両方もらえる?選ぶならどちら?
・生命保険加入時に告知義務違反をするとどうなる?保険金がもらえない?
・個人年金保険のメリット・デメリット 保険で個人年金の積み立てができる